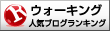半世紀後の復習
毎週木曜日は国語をおさらいする日。
今週の課題は「もし」です。
どうして漢字で「若し」と表記するのか、そう問われても説明する言葉が
ありません。
辞書にはこうありました。
<もし:①将来起こりうると予想される事態が起こった場合を仮定する様子。
②(ありえないことだが)事実と反対の事態を想定してみる様子>
(新明解国語辞典 より)
漢字表記は<若し>と説明が添えられていますが、それを使う理由は
書かれていません。
辞書は「若しか」「若しく」「若しそれ」「若しも」と続き、いずれにも
「若」の漢字が使われているけれど説明はありません。
当たり前に、何の不信感も抱かずに、「若い」の若が「も」と読まれています。
何故?
ネットで情報を集めていたらこんな解説が見つかりました。
<若しの書き方は古くからあり漢文が由来>(Ray雑学 より)
更にこんな解説も。
<「若しくは」は漢文の読み方を日本語に直した語が語源とされている。
漢文では「若」を「ごとし」と読み、日本語として副詞「もし(若し)」
に副詞語尾「く」係助詞「は」が付いた語>(言葉の読み方辞典 より)
高校の授業で古文漢文は大の苦手。
半世紀も経つと言うのに再び苦しめられるとは。
教えて!ハナシマ先生
嫌々ながら漢文の解説を開いてみました。
よく分からないので丸写しです。
<若:①~のようである、読み方は「ごとシ」
②~と同等である、読み方は「しク」
③もし~ならば、読み方は「もシ」
④お前あるいはあなた、読み方は「なんじ」>
①から④の見分け方として以下の解説が。
<若の前に「不」があれば②、不若の形で~には及ばないとの意味になり
物事の優劣を表す>
<若の後文に「則」とか「~せば」という送り仮名がある場合は③の意味>
<①については送り点(特にレ点)がほぼ付き、④に関しては送り点がほぼ
付かないとの特徴がある>
この呪文の様な解説の最後にこの一文がありました。
<なお漢文では「若」に「若い」の意味は無い>(ハナシマ先生の教えて!漢文 より)
つまり古い時代には「若し」しか存在せず「若い」は使われていなかった、と
勝手に解釈しました。
何だか骨の折れるおさらいになりました。
こんな苦労をしながら「あるくあかるく」の駄文書きをどうして続けている
のかと言えば、目的のひとつは頭の体操。
肉体的な衰えには運動で抗い、頭の体操で気持ちをスッキリさせて精神的
な若さは保ちたい。
そんな期待を込めての悪あがきです。
文字にするならば「気、若くありたい」です。
今週のおさらいになぞって「若く」を「もく」と読まれちゃ困ります。
毎週木曜日は国語をおさらいする日。
今週の課題は「もし」です。
どうして漢字で「若し」と表記するのか、そう問われても説明する言葉が
ありません。
辞書にはこうありました。
<もし:①将来起こりうると予想される事態が起こった場合を仮定する様子。
②(ありえないことだが)事実と反対の事態を想定してみる様子>
(新明解国語辞典 より)
漢字表記は<若し>と説明が添えられていますが、それを使う理由は
書かれていません。
辞書は「若しか」「若しく」「若しそれ」「若しも」と続き、いずれにも
「若」の漢字が使われているけれど説明はありません。
当たり前に、何の不信感も抱かずに、「若い」の若が「も」と読まれています。
何故?
ネットで情報を集めていたらこんな解説が見つかりました。
<若しの書き方は古くからあり漢文が由来>(Ray雑学 より)
更にこんな解説も。
<「若しくは」は漢文の読み方を日本語に直した語が語源とされている。
漢文では「若」を「ごとし」と読み、日本語として副詞「もし(若し)」
に副詞語尾「く」係助詞「は」が付いた語>(言葉の読み方辞典 より)
高校の授業で古文漢文は大の苦手。
半世紀も経つと言うのに再び苦しめられるとは。
教えて!ハナシマ先生
嫌々ながら漢文の解説を開いてみました。
よく分からないので丸写しです。
<若:①~のようである、読み方は「ごとシ」
②~と同等である、読み方は「しク」
③もし~ならば、読み方は「もシ」
④お前あるいはあなた、読み方は「なんじ」>
①から④の見分け方として以下の解説が。
<若の前に「不」があれば②、不若の形で~には及ばないとの意味になり
物事の優劣を表す>
<若の後文に「則」とか「~せば」という送り仮名がある場合は③の意味>
<①については送り点(特にレ点)がほぼ付き、④に関しては送り点がほぼ
付かないとの特徴がある>
この呪文の様な解説の最後にこの一文がありました。
<なお漢文では「若」に「若い」の意味は無い>(ハナシマ先生の教えて!漢文 より)
つまり古い時代には「若し」しか存在せず「若い」は使われていなかった、と
勝手に解釈しました。
何だか骨の折れるおさらいになりました。
こんな苦労をしながら「あるくあかるく」の駄文書きをどうして続けている
のかと言えば、目的のひとつは頭の体操。
肉体的な衰えには運動で抗い、頭の体操で気持ちをスッキリさせて精神的
な若さは保ちたい。
そんな期待を込めての悪あがきです。
文字にするならば「気、若くありたい」です。
今週のおさらいになぞって「若く」を「もく」と読まれちゃ困ります。