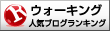別に珍しくは無い
ひと休みしようと森林公園のベンチに腰を掛けたら、ズボンに小さな
ごみの様な物がへばりついていました。
5mm程の楕円形の物体をルーペで覗くと、極小さな触角や足があり全体
の印象はゾウムシでした。
しかし頭の部分は押し潰された風で、特有の長い鼻がありません。
全身灰色っぽい色をしていますが、翅に黒っぽい紋が付いています。
その辺りを手掛かりに帰宅後に調べて、ヒレルクチブトゾウムシと言う
奇妙な名前を知りました。
この虫は成虫のまま落ち葉の下などで冬を越し、春になると活動を始め
産卵します。
孵化した幼虫は初夏から夏の盛りに成虫に育ち、また卵を産みます。
ここから孵化した幼虫は10月頃に成虫になり、そのまま冬を越して春を
待ちます。
幼虫は植物の根を食べ、成虫はサクラやウメなどの葉を食します。
初めて見たのでさぞや変わった種類かと期待しましたが、特段珍しい虫
では無いようです。
小さ過ぎるのでこれまで私が気付かなかっただけで、実は日本全国に極一般
的に生息している虫でした。(Wikipedia より)
名前の由来
ゾウムシの特徴的な長い鼻は、口吻と呼ばれ先端に口が付いています。
他の虫では届かない植物の奥深くにある種を食べ、産卵の為の孔を掘るのに
役立ちます。
卵を孔に産み付けるとセメントの様な物質を出して、すっかり埋めてしまいます。
(コスタリカ昆虫中心生活 より)
ヒレルクチブトゾウムシには長い鼻がありません。
短吻類と呼ばれるグループに属していて、この仲間は葉を食べるのに都合の
良い口をしています。
ヒレルの場合は毛むくじゃらな平たい口をしています。
ところでヒレルってどんな意味なのでしょう?
ゾウムシの仲間は種名の付いたものだけでも日本に千種、全世界には6万種
もいるそうです。
甲虫類の中でも際立って種類の多いグループです。
それだけ多ければ訳の分からぬ名前があっても不思議ではありません。
そうなのですが、由来が分からないのは何とも落ち着きません。
後半の部分は口の太いゾウムシだと容易に想像がつきますが、初っ端の「ヒレル」
が厄介です。
捻る?
思わず首をひねってしまいます。
<学名はOedophrys Hilleri。
Oideoは膨れ上がる、ophrysは眉、合わせて「膨らんだ眉」を意味している。
生態を研究したヒラー氏の名をラテン語読みしてヒレルと名付けられた。>
(鎮さんの自然観察記 より)
このヒレルさん、昆虫の研究に励んで他にも幾つかの虫に「ヒレル」を
残しているそうです。
由来が分かって漸くもやもや感が消えました、やれやれです。
あー、ヒレルはつかれる。
ひと休みしようと森林公園のベンチに腰を掛けたら、ズボンに小さな
ごみの様な物がへばりついていました。
5mm程の楕円形の物体をルーペで覗くと、極小さな触角や足があり全体
の印象はゾウムシでした。
しかし頭の部分は押し潰された風で、特有の長い鼻がありません。
全身灰色っぽい色をしていますが、翅に黒っぽい紋が付いています。
その辺りを手掛かりに帰宅後に調べて、ヒレルクチブトゾウムシと言う
奇妙な名前を知りました。
この虫は成虫のまま落ち葉の下などで冬を越し、春になると活動を始め
産卵します。
孵化した幼虫は初夏から夏の盛りに成虫に育ち、また卵を産みます。
ここから孵化した幼虫は10月頃に成虫になり、そのまま冬を越して春を
待ちます。
幼虫は植物の根を食べ、成虫はサクラやウメなどの葉を食します。
初めて見たのでさぞや変わった種類かと期待しましたが、特段珍しい虫
では無いようです。
小さ過ぎるのでこれまで私が気付かなかっただけで、実は日本全国に極一般
的に生息している虫でした。(Wikipedia より)
名前の由来
ゾウムシの特徴的な長い鼻は、口吻と呼ばれ先端に口が付いています。
他の虫では届かない植物の奥深くにある種を食べ、産卵の為の孔を掘るのに
役立ちます。
卵を孔に産み付けるとセメントの様な物質を出して、すっかり埋めてしまいます。
(コスタリカ昆虫中心生活 より)
ヒレルクチブトゾウムシには長い鼻がありません。
短吻類と呼ばれるグループに属していて、この仲間は葉を食べるのに都合の
良い口をしています。
ヒレルの場合は毛むくじゃらな平たい口をしています。
ところでヒレルってどんな意味なのでしょう?
ゾウムシの仲間は種名の付いたものだけでも日本に千種、全世界には6万種
もいるそうです。
甲虫類の中でも際立って種類の多いグループです。
それだけ多ければ訳の分からぬ名前があっても不思議ではありません。
そうなのですが、由来が分からないのは何とも落ち着きません。
後半の部分は口の太いゾウムシだと容易に想像がつきますが、初っ端の「ヒレル」
が厄介です。
捻る?
思わず首をひねってしまいます。
<学名はOedophrys Hilleri。
Oideoは膨れ上がる、ophrysは眉、合わせて「膨らんだ眉」を意味している。
生態を研究したヒラー氏の名をラテン語読みしてヒレルと名付けられた。>
(鎮さんの自然観察記 より)
このヒレルさん、昆虫の研究に励んで他にも幾つかの虫に「ヒレル」を
残しているそうです。
由来が分かって漸くもやもや感が消えました、やれやれです。
あー、ヒレルはつかれる。