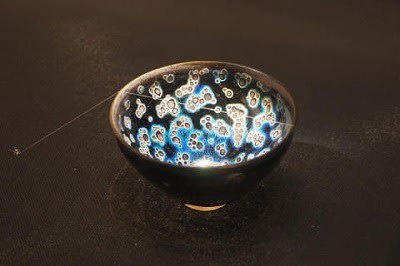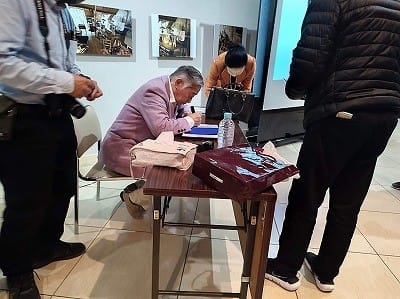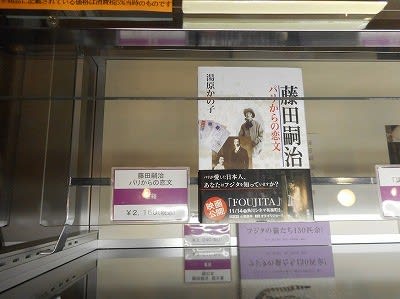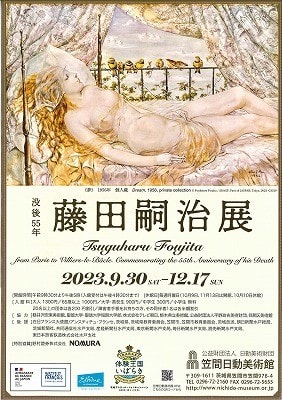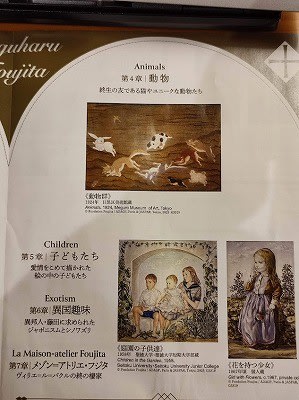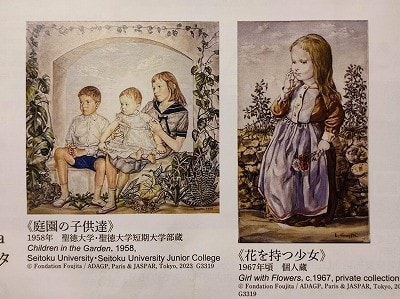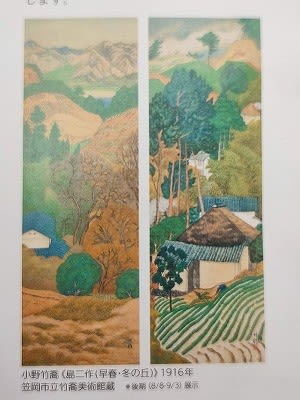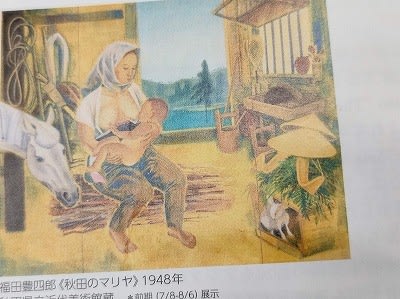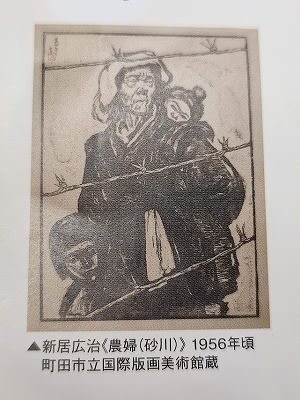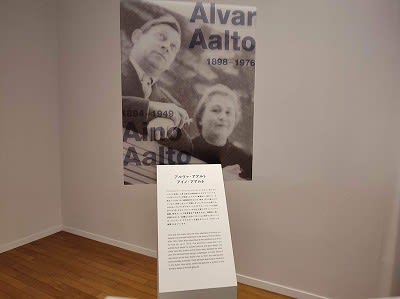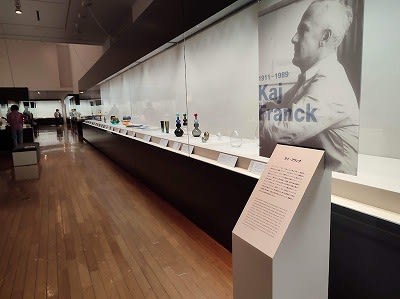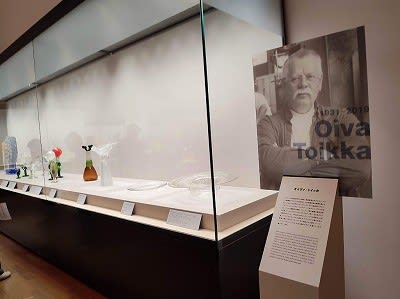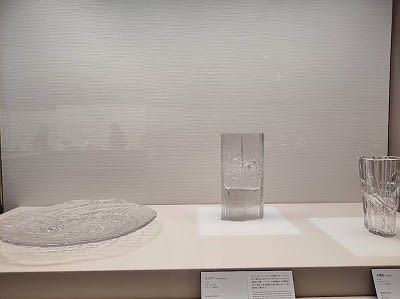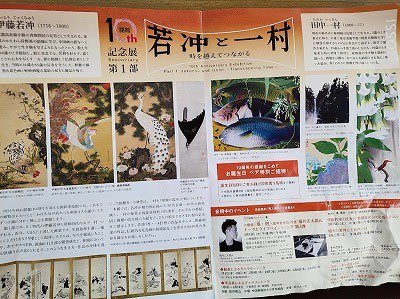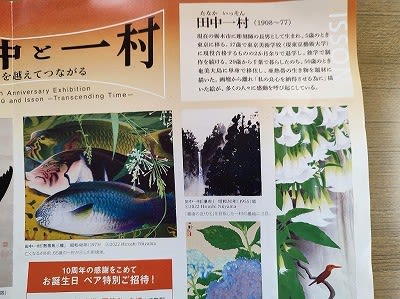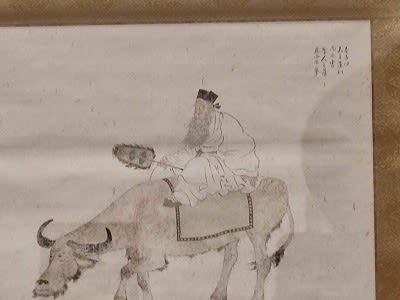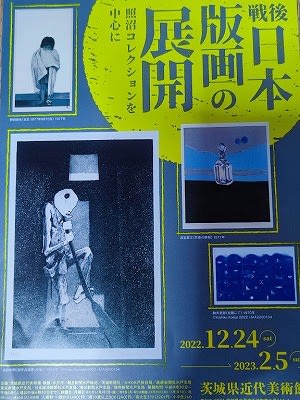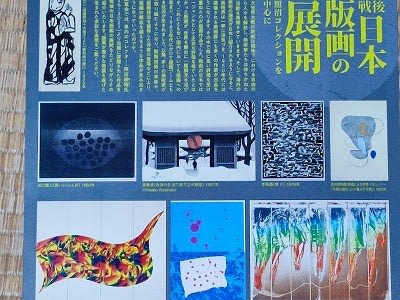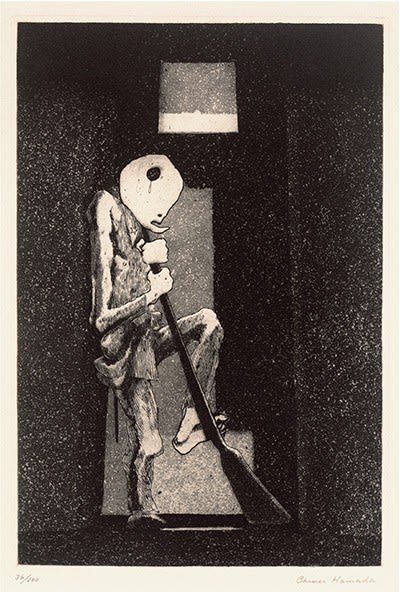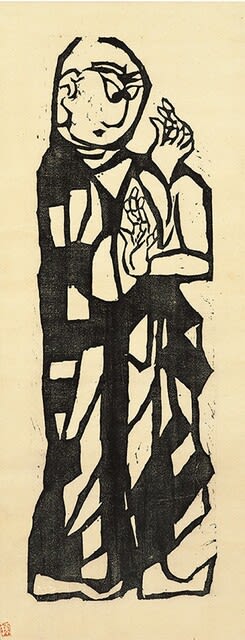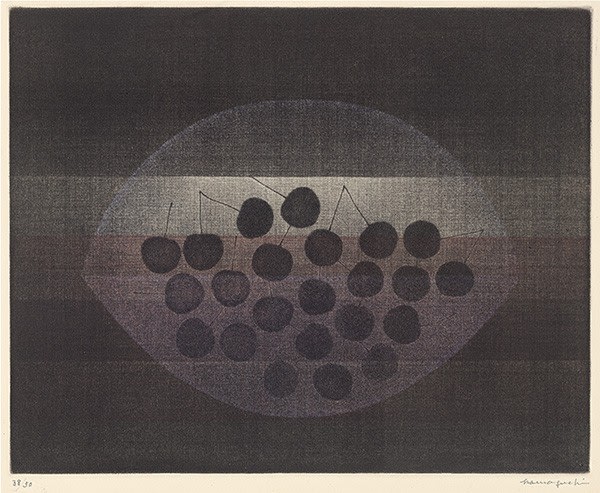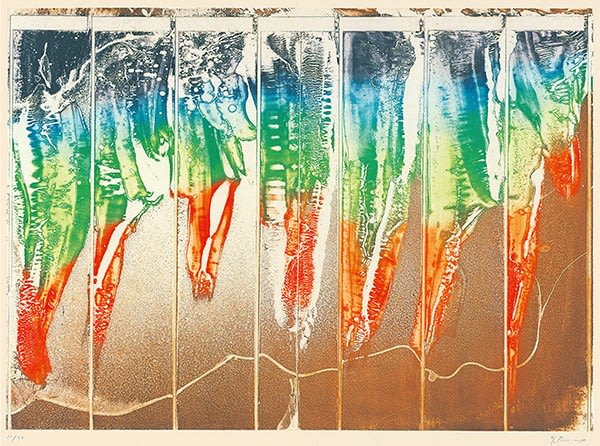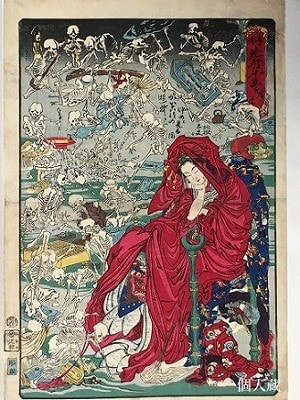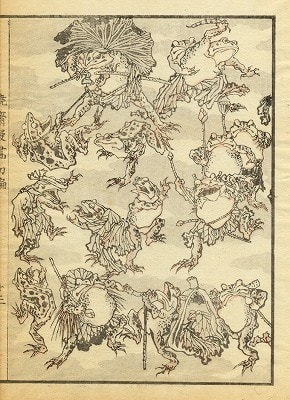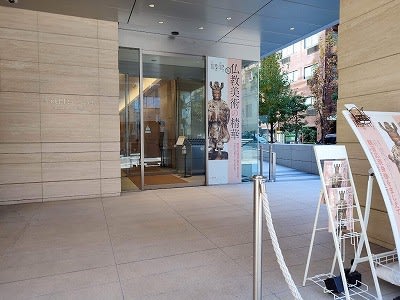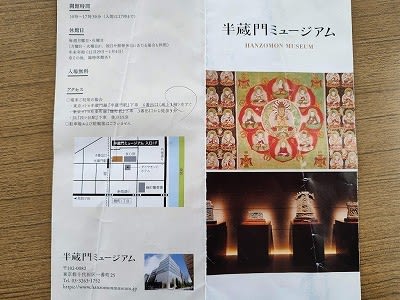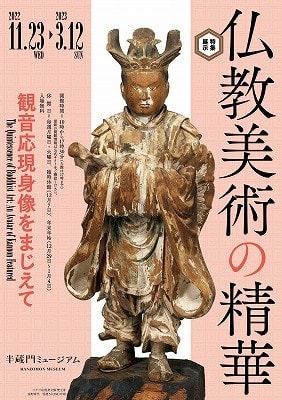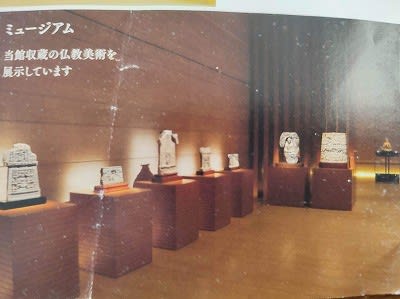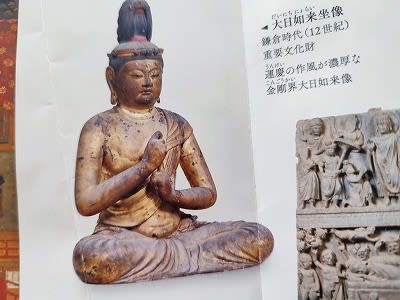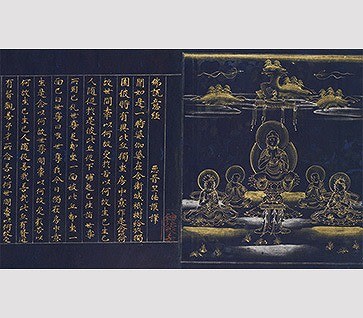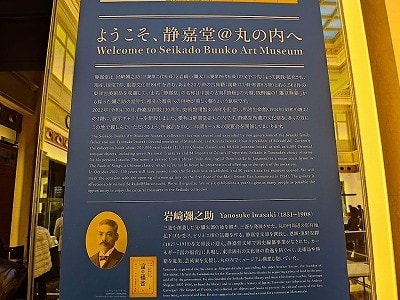石岡瑛子Iデザイン@茨城県近代美術館
2024年4月27日(土)~7月7日(日)
「資生堂」や「PARCO」のポスターなどのデザインで知られる石岡瑛子(1938-2012)の展覧会で「スゴい人がいた」のサブタイトルにあるように「凄い人」だった。
アメリカに活動拠点を移す前、1960-80 年代の仕事を中心に、アートディレクターとして采配を振るったポスターやCM、グラフィックアートからスケッチまで、約500点が展示された。



常に革新的なヴィジュアルを目指した石岡のデザイン哲学と、彼女が表現者として生涯にわたって磨き抜いた「I=私」を浮き彫りにする。
「I=私」――自らを鍛錬し続けること、そして他者とのオープンな協働を通して培った「本当の“自分力”」 ――は、彼女のデザインを唯一無二のものとした。



PARCO(パルコ)の存在も含め、新鮮でインパクトがあった。







雑誌の表紙や教科書などまで、多様な分野への創作意欲が感じられる。

映画のポスター

全仕事のカタログブック?
本展は予想以上の展示内容で、日を改めて再見したいと思った。
県美の単独企画なのか、或いは巡回展なのか?
単独としたら県美の仕事としては快挙だ!
2024年4月27日(土)~7月7日(日)
「資生堂」や「PARCO」のポスターなどのデザインで知られる石岡瑛子(1938-2012)の展覧会で「スゴい人がいた」のサブタイトルにあるように「凄い人」だった。
アメリカに活動拠点を移す前、1960-80 年代の仕事を中心に、アートディレクターとして采配を振るったポスターやCM、グラフィックアートからスケッチまで、約500点が展示された。



常に革新的なヴィジュアルを目指した石岡のデザイン哲学と、彼女が表現者として生涯にわたって磨き抜いた「I=私」を浮き彫りにする。
「I=私」――自らを鍛錬し続けること、そして他者とのオープンな協働を通して培った「本当の“自分力”」 ――は、彼女のデザインを唯一無二のものとした。



PARCO(パルコ)の存在も含め、新鮮でインパクトがあった。







雑誌の表紙や教科書などまで、多様な分野への創作意欲が感じられる。

映画のポスター

全仕事のカタログブック?
本展は予想以上の展示内容で、日を改めて再見したいと思った。
県美の単独企画なのか、或いは巡回展なのか?
単独としたら県美の仕事としては快挙だ!