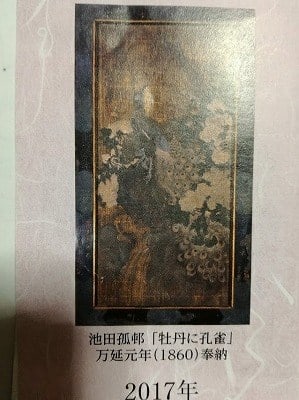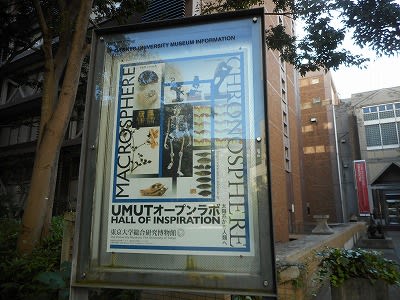旧芝離宮恩賜庭園@東京都港区海岸

浜松町からスカイデッキを歩いてウォーターズ竹芝あたりの新しい景色を眺めた帰途、旧芝離宮恩賜庭園に立ち寄った。


2008年に訪問してから15年を経過しての再訪で当時の記憶があいまいだが、周囲にビルが林立し、さらに増えそうな気配だ。
大久保忠朝上屋敷の庭園楽寿園が始まりで、宮内庁管理の離宮を経て、大正13年(1924年)東京市に下賜され、旧芝離宮恩賜庭園として公開された。


江戸初期の典型的な回遊式泉水庭園で、池を中心とした庭園の区画や石の配置は非常に優れており、国の名勝指定を受けている。
作庭当時は海の水を引き込んでいたが、周辺の埋め立てが進み、現在では淡水の池となっている。


浙江省にある西湖の蘇堤を模した西湖の堤をはじめ、池の中央にある中島には中国で仙人が住むといわれた蓬莱山を模した蓬莱石組みもある。

大きな石柱が4本。
この石柱は、小田原北条家に仕えた戦国武将の旧邸から運ばれた。
ここが小田原藩(大久保家)の上屋敷であった当初、茶室として使われていたといわれる。

古い灯篭に紅葉が映える。

「根府川石」の山
根府川石は神奈川県小田原市根府川で産出される、単斜輝石斜方輝石安山岩。
山と積まれているが、園内にはこの石がふんだんに使用されている。

浜松町からスカイデッキを歩いてウォーターズ竹芝あたりの新しい景色を眺めた帰途、旧芝離宮恩賜庭園に立ち寄った。


2008年に訪問してから15年を経過しての再訪で当時の記憶があいまいだが、周囲にビルが林立し、さらに増えそうな気配だ。
大久保忠朝上屋敷の庭園楽寿園が始まりで、宮内庁管理の離宮を経て、大正13年(1924年)東京市に下賜され、旧芝離宮恩賜庭園として公開された。


江戸初期の典型的な回遊式泉水庭園で、池を中心とした庭園の区画や石の配置は非常に優れており、国の名勝指定を受けている。
作庭当時は海の水を引き込んでいたが、周辺の埋め立てが進み、現在では淡水の池となっている。


浙江省にある西湖の蘇堤を模した西湖の堤をはじめ、池の中央にある中島には中国で仙人が住むといわれた蓬莱山を模した蓬莱石組みもある。

大きな石柱が4本。
この石柱は、小田原北条家に仕えた戦国武将の旧邸から運ばれた。
ここが小田原藩(大久保家)の上屋敷であった当初、茶室として使われていたといわれる。

古い灯篭に紅葉が映える。

「根府川石」の山
根府川石は神奈川県小田原市根府川で産出される、単斜輝石斜方輝石安山岩。
山と積まれているが、園内にはこの石がふんだんに使用されている。