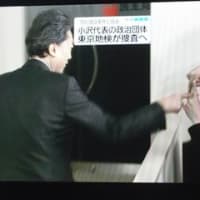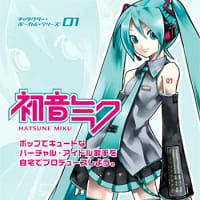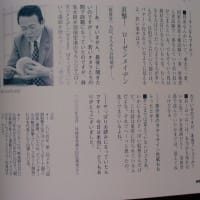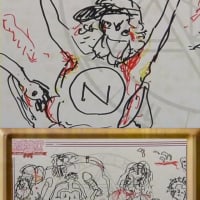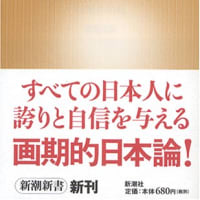政治家が好んで使う言葉に「憲政の常道」というものがある。
例えば、今日も石破茂議員が次のように云っていた。
自民党の石破茂農水相は6日のフジテレビの番組で、党執行部が特別国会での首相指名選挙は白紙投票で調整していることについて「白紙で入れるのはどんな理屈を付けても国会議員としての職場放棄だ。白紙は憲政の常道に反する行為だ」と述べ、反対する考えを改めて示した。
(時事ドットコム 2009年9月6日 14:47)
石破さん、憲政の常道をどのような意味で使っているのだろう。
また、先の衆院選挙の翌日、朝日新聞の一面には次のような論説記事が載っていた。
大正から昭和にかけ、当時の2大政党が交互に政権を担う時代があった。
「憲政の常道」と呼ばれた慣行である。
(朝日新聞 2009年8月31日)
なお、こちらの文章は政治エディターの根本清樹さんのもの。
「二大」を「2大」と算用数字を使って表記していることにもかなりの違和感があるが、憲政の常道の解釈にも幾ばくかの違和感を拭えない。
と言っても、責める気はない。
「憲政の常道」は好んで使う人が多い反面、かなり複雑で難しい言葉だからだ。
「憲政の常道」とは、ウィキペディアの定義をそのまま借りると、
「天皇による組閣の命令(いわゆる大命降下)は衆議院の第一党の党首に下されるべきこと。また、その内閣が失政によって倒れたときは、組閣の命令は野党第一党の党首に下されるべきこと」とする大日本帝国憲法下の政党政治時代における政界の慣例。あくまでも慣例であり、法的拘束力はなかった。
となる。
ウィキにしてはなかなか的確な説明だ。(偉そう!)
これを解り易く書くと
一、衆議院の第一党が政権をとること。
二、その政権が失政によって倒れたときには、野党第一党が代わって政権をとること。
となる。
一の「衆議院の第一党が政権をとる」はこんにちでは当り前のことで、わざわざ常道なんていうのは不思議に感じるかも知れないが、当時は非政党人や軍人が首相になることが多く、政党が政権をとるべきだということを敢えて云う必要があったのだ。
しかし、複雑なのは二の「その政権が失政によって倒れたときには衆議院の野党第一党が代わって政権をとる」だ。
一見、これも普通のことのように思えるが、ここでは選挙を想定していない。
つまり、選挙を経ずして野党第一党が政権をとることになる。
すると、どういうことが予想されるかというと、野党は国会における少数派ゆえに野党なのであって、すべて多数決の国会において法案が一つも通らないことになってしまうのだ。
さらに、「失政によって」という条件がある以上、なにを以って失政と定義するかが非常に困難になる。
それでも、戦前において憲政の常道が機能した理由は戦前の政界では現在とは異なる力関係が存在したからだ。
それは、元老の存在だ。
現在では内閣総理大臣(首相)は国会における指名によって選ばれる。
戦前では主に元老が指名した首相候補に対し、天皇が大命降下をくだすという形式をとっていた。
だから、ライバル党であっても「元老が指名した人だから」「天皇から大命も下っているし」と少数与党に協力したのだ。
これが実際に機能したのは朝日新聞の記事にもあるように大正から昭和にかけてだ。
もう少し詳しく言えば、加藤高明内閣(憲政会)から第一次若槻禮次郎内閣(憲政会)、田中義一内閣(政友会)、濱口雄幸内閣(民政党)、第二次若槻内閣(民政党)、犬養毅内閣(政友会)までとなる。
元号で云うと、大正十三年から昭和六年あたりまで。
実は戦後も「憲政の常道」に従った例がある。
それが、第一次吉田茂内閣(日本自由党)の後の片山哲内閣(日本社会党)だ。
昭和二十二年四月に第一次吉田内閣のもと、日本国憲法施行後初の衆議院選挙が行われた。
そのとき、吉田はトップ当選したが、選挙の結果は日本自由党131議席、社会党143議席、日本民主党124議席、国民協同党31議席(以下略)と社会党に敗れ、第一党の座を奪われた。
普通はここで同じ保守勢力である民主党と連立を組んで政権に就くところなのだが、吉田は敢えてそうはせず、選挙後の首班指名で社会党党首の片山哲をほぼ全会一致で指名し、片山内閣が誕生した。
しかし、元老が居なくなった戦後では憲政の常道に従った政権交代はうまく機能しなかった。
社会党は民主党と国民協同党を与党に迎えたが、社会主義政党である社会党と保守政党民主党はウマが合わず、社会党内も右派と左派で争い分裂。
わずか十ヶ月で崩壊してしまった。
つまり、「憲政の常道」とはあくまでも大日本帝国憲法下において機能した概念であり、戦後の日本国憲法下において「憲政の常道」はもはや機能しないのだ。
それにもかかわらず、よく野党議員は「憲政の常道に従って政権を譲るべきだ」という言い方をする。
しかし、いままで述べて来たように国会で過半数以上の議席を持たない野党に選挙を経ずして、政権を渡したところですぐに政権運営に行き詰まるのがオチだ。
いまの時代に「憲政の常道」を口走るのは時代錯誤と心得るべし。
さて、冒頭の石破さんの言葉に戻ろう。
石破さんは国会の首班指名で「白紙は憲政の常道に反する行為だ」と云う。
確かに、憲政の常道に従うならば、自民党議員は全員、衆議院の第一党となった民主党の党首、すなわち鳩山由紀夫を指名するべきで、白紙で投票することは当然、憲政の常道に反する。
だから、石破さんは「自民党議員は鳩山由紀夫に投票すべきだ」と云うのかと思いきや、同記事によると、石破さんはこのあと
「麻生(太郎総裁)さんの名前を書くのも民意の否定だ。両院議員総会長でも、去年の総裁選で2位だった与謝野(馨財務・金融相)先生でもいい」
と続けている。
これならどちらにせよ憲政の常道に反することになる。
次に朝日新聞の根本さんの記事。
「大正から昭和にかけ、当時の2大政党が交互に政権を担う時代があった。
「憲政の常道」と呼ばれた慣行である」
これは誤用ともいえなくないが、二大政党が交互に政権を担っていたわけではない。
すでに書いたように加藤内閣から、犬養内閣までの政党は、
憲政会→憲政会→政友会→民政党→民政党→政友会という順で、別段交互ではない。
これは「憲政の常道」の二にあった「失政によって」の文言が重要になってくる。
加藤内閣は首相の加藤高明が肺炎をこじらせたことによる病死によって倒れたので失政によってではない。
したがって、あとに同じく憲政会の若槻禮次郎が首相に指名された。
濱口内閣は濱口雄幸が右翼の佐郷屋留男に銃撃され、その傷が元で登院できないようになり総辞職、という具合だ。
また、憲政の常道は二大政党である必要はない。
二大政党が交互に政権を担うことを憲政の常道というのはやはりちょっと違和感がある。
今後、無理矢理この「憲政の常道」を機能させるには、今度の民主党政権に失政があったとき民主党政権が野党第一党である自民党に政権を譲ることだ。
その上で、少数与党の自民党政権に協力すれば憲政の常道となる。
が、こんなこと現実に起きるはずがないことは誰にでもわかる。
「憲政の常道」は思わず使ってみたくなる言葉だが、使用にはくれぐれも御用心。
例えば、今日も石破茂議員が次のように云っていた。
自民党の石破茂農水相は6日のフジテレビの番組で、党執行部が特別国会での首相指名選挙は白紙投票で調整していることについて「白紙で入れるのはどんな理屈を付けても国会議員としての職場放棄だ。白紙は憲政の常道に反する行為だ」と述べ、反対する考えを改めて示した。
(時事ドットコム 2009年9月6日 14:47)
石破さん、憲政の常道をどのような意味で使っているのだろう。
また、先の衆院選挙の翌日、朝日新聞の一面には次のような論説記事が載っていた。
大正から昭和にかけ、当時の2大政党が交互に政権を担う時代があった。
「憲政の常道」と呼ばれた慣行である。
(朝日新聞 2009年8月31日)
なお、こちらの文章は政治エディターの根本清樹さんのもの。
「二大」を「2大」と算用数字を使って表記していることにもかなりの違和感があるが、憲政の常道の解釈にも幾ばくかの違和感を拭えない。
と言っても、責める気はない。
「憲政の常道」は好んで使う人が多い反面、かなり複雑で難しい言葉だからだ。
「憲政の常道」とは、ウィキペディアの定義をそのまま借りると、
「天皇による組閣の命令(いわゆる大命降下)は衆議院の第一党の党首に下されるべきこと。また、その内閣が失政によって倒れたときは、組閣の命令は野党第一党の党首に下されるべきこと」とする大日本帝国憲法下の政党政治時代における政界の慣例。あくまでも慣例であり、法的拘束力はなかった。
となる。
ウィキにしてはなかなか的確な説明だ。(偉そう!)
これを解り易く書くと
一、衆議院の第一党が政権をとること。
二、その政権が失政によって倒れたときには、野党第一党が代わって政権をとること。
となる。
一の「衆議院の第一党が政権をとる」はこんにちでは当り前のことで、わざわざ常道なんていうのは不思議に感じるかも知れないが、当時は非政党人や軍人が首相になることが多く、政党が政権をとるべきだということを敢えて云う必要があったのだ。
しかし、複雑なのは二の「その政権が失政によって倒れたときには衆議院の野党第一党が代わって政権をとる」だ。
一見、これも普通のことのように思えるが、ここでは選挙を想定していない。
つまり、選挙を経ずして野党第一党が政権をとることになる。
すると、どういうことが予想されるかというと、野党は国会における少数派ゆえに野党なのであって、すべて多数決の国会において法案が一つも通らないことになってしまうのだ。
さらに、「失政によって」という条件がある以上、なにを以って失政と定義するかが非常に困難になる。
それでも、戦前において憲政の常道が機能した理由は戦前の政界では現在とは異なる力関係が存在したからだ。
それは、元老の存在だ。
現在では内閣総理大臣(首相)は国会における指名によって選ばれる。
戦前では主に元老が指名した首相候補に対し、天皇が大命降下をくだすという形式をとっていた。
だから、ライバル党であっても「元老が指名した人だから」「天皇から大命も下っているし」と少数与党に協力したのだ。
これが実際に機能したのは朝日新聞の記事にもあるように大正から昭和にかけてだ。
もう少し詳しく言えば、加藤高明内閣(憲政会)から第一次若槻禮次郎内閣(憲政会)、田中義一内閣(政友会)、濱口雄幸内閣(民政党)、第二次若槻内閣(民政党)、犬養毅内閣(政友会)までとなる。
元号で云うと、大正十三年から昭和六年あたりまで。
実は戦後も「憲政の常道」に従った例がある。
それが、第一次吉田茂内閣(日本自由党)の後の片山哲内閣(日本社会党)だ。
昭和二十二年四月に第一次吉田内閣のもと、日本国憲法施行後初の衆議院選挙が行われた。
そのとき、吉田はトップ当選したが、選挙の結果は日本自由党131議席、社会党143議席、日本民主党124議席、国民協同党31議席(以下略)と社会党に敗れ、第一党の座を奪われた。
普通はここで同じ保守勢力である民主党と連立を組んで政権に就くところなのだが、吉田は敢えてそうはせず、選挙後の首班指名で社会党党首の片山哲をほぼ全会一致で指名し、片山内閣が誕生した。
しかし、元老が居なくなった戦後では憲政の常道に従った政権交代はうまく機能しなかった。
社会党は民主党と国民協同党を与党に迎えたが、社会主義政党である社会党と保守政党民主党はウマが合わず、社会党内も右派と左派で争い分裂。
わずか十ヶ月で崩壊してしまった。
つまり、「憲政の常道」とはあくまでも大日本帝国憲法下において機能した概念であり、戦後の日本国憲法下において「憲政の常道」はもはや機能しないのだ。
それにもかかわらず、よく野党議員は「憲政の常道に従って政権を譲るべきだ」という言い方をする。
しかし、いままで述べて来たように国会で過半数以上の議席を持たない野党に選挙を経ずして、政権を渡したところですぐに政権運営に行き詰まるのがオチだ。
いまの時代に「憲政の常道」を口走るのは時代錯誤と心得るべし。
さて、冒頭の石破さんの言葉に戻ろう。
石破さんは国会の首班指名で「白紙は憲政の常道に反する行為だ」と云う。
確かに、憲政の常道に従うならば、自民党議員は全員、衆議院の第一党となった民主党の党首、すなわち鳩山由紀夫を指名するべきで、白紙で投票することは当然、憲政の常道に反する。
だから、石破さんは「自民党議員は鳩山由紀夫に投票すべきだ」と云うのかと思いきや、同記事によると、石破さんはこのあと
「麻生(太郎総裁)さんの名前を書くのも民意の否定だ。両院議員総会長でも、去年の総裁選で2位だった与謝野(馨財務・金融相)先生でもいい」
と続けている。
これならどちらにせよ憲政の常道に反することになる。
次に朝日新聞の根本さんの記事。
「大正から昭和にかけ、当時の2大政党が交互に政権を担う時代があった。
「憲政の常道」と呼ばれた慣行である」
これは誤用ともいえなくないが、二大政党が交互に政権を担っていたわけではない。
すでに書いたように加藤内閣から、犬養内閣までの政党は、
憲政会→憲政会→政友会→民政党→民政党→政友会という順で、別段交互ではない。
これは「憲政の常道」の二にあった「失政によって」の文言が重要になってくる。
加藤内閣は首相の加藤高明が肺炎をこじらせたことによる病死によって倒れたので失政によってではない。
したがって、あとに同じく憲政会の若槻禮次郎が首相に指名された。
濱口内閣は濱口雄幸が右翼の佐郷屋留男に銃撃され、その傷が元で登院できないようになり総辞職、という具合だ。
また、憲政の常道は二大政党である必要はない。
二大政党が交互に政権を担うことを憲政の常道というのはやはりちょっと違和感がある。
今後、無理矢理この「憲政の常道」を機能させるには、今度の民主党政権に失政があったとき民主党政権が野党第一党である自民党に政権を譲ることだ。
その上で、少数与党の自民党政権に協力すれば憲政の常道となる。
が、こんなこと現実に起きるはずがないことは誰にでもわかる。
「憲政の常道」は思わず使ってみたくなる言葉だが、使用にはくれぐれも御用心。