江戸時代の刑法は身分によって大きく分かれていました。
武士の身分の者に適用された死刑は「斬刑」で、
一般庶民の死罪と同じ打ち首ですが、
庶民の死体は刀の試し切りなどにされるのに対し、
武士はありませんでした。
しかし、最も大きな違いは、武士には切腹があった事です。
切腹は江戸時代の刑法典に
正式に規定されたものではありませんが、
武士の名誉に配慮した形で、
幕府や主君から賜わる恩典と一般的に見なされていました。
有名な赤穂浪士に対し幕府が下した判決は切腹で、
浪士達は非常に喜んだと伝えられています。
もちろん武士で斬刑に処せられた者はいましたが、
大名となると、幕府の役務中に刃傷を起こした内藤忠勝や、
江戸城中で刃傷に及んだ浅野内匠頭でさえも、
それぞれ切腹でした。
しかし、江戸幕府260余年でただ1人、
打ち首になった大名がいました。
それは、肥前島原4万石の藩主松倉勝家です。
松倉勝家は、初代島原藩主重政の嫡男として、
1597年(慶長2年)に生まれます。
重政と共に島原城とその城下町の新築、
参勤交代の費用など種々の口実を設け、
また独自に検地を実施して
実質4万石程度の石高を10万石と過大に見積もり、
領民に10万石相当の過重な年貢・労役を課しました。
1630年(寛永7年)に重政が急逝した後を受けて
藩主となってからは、
父をも凌ぐ過酷な収奪を行って領民を苦しめます。
1634年(寛永11年)は悪天候と旱魃による凶作でしたが、
勝家は容赦せず重税を取立てます。
米や農作物の徴収だけでなく、
人頭税や住宅税などありとあらゆる税を新設して
厳格に取り立てたことが多くの記録に残っているとの事です。
勝家は年貢を納められない農民や、
村の責任者である庄屋から、妻や娘を人質に取るようになり、
島原の乱の記録を残した
長崎のポルトガル人ドアルテ・コレアは、
人質の若い娘や子供に藁蓑を着せて火をつけ、
もがきながら焼死する姿を
「蓑踊り」と呼んでいたという記録を残しています。
1637年(寛永14年)、口の津村の庄屋・与左衛門の妻は
身重のまま人質にとられ、
冷たい水牢に裸で入れられてしまいます。
村民は庄屋宅に集まり年貢を納める方法を話し合いましたが、
納める事が出来ず、
庄屋の妻は6日間苦しみ、水中で出産した子供と共に絶命します。
たまりかねた領民は蜂起し、
代官所を襲撃して代官を殺害しますが、
これが島原の乱の始まりです。
乱の鎮圧後、勝家は肥前唐津藩主寺沢堅高と共に
反乱惹起の責任を問われ、
勝家は改易、所領を没収され、
美作津山藩主森長継に預けられます。
勝家は悪政を布いたことを否定し、
キリシタンによる反乱を主張し続けますが、
その後松倉家の邸宅から
折檻された農民の遺体が発見されると容疑は定まり、
1638年(寛永15年)、
幕府は正式に松倉を江戸に召喚して評定を重ねた結果、
死罪と決して
7月19日、森家の江戸屋敷で斬首に処せられました。
その遺骸は松倉家の家臣に引き取られ、
芝の金地院に葬られました。
大名が切腹さえも許されず
一介の罪人として斬首刑に処せられたことは、
大反乱を引き起こす原因を作った勝家の失政を
幕府側が極めて重大な罪と見なしていたことを
示しているのでしょう。
武士の身分の者に適用された死刑は「斬刑」で、
一般庶民の死罪と同じ打ち首ですが、
庶民の死体は刀の試し切りなどにされるのに対し、
武士はありませんでした。
しかし、最も大きな違いは、武士には切腹があった事です。
切腹は江戸時代の刑法典に
正式に規定されたものではありませんが、
武士の名誉に配慮した形で、
幕府や主君から賜わる恩典と一般的に見なされていました。
有名な赤穂浪士に対し幕府が下した判決は切腹で、
浪士達は非常に喜んだと伝えられています。
もちろん武士で斬刑に処せられた者はいましたが、
大名となると、幕府の役務中に刃傷を起こした内藤忠勝や、
江戸城中で刃傷に及んだ浅野内匠頭でさえも、
それぞれ切腹でした。
しかし、江戸幕府260余年でただ1人、
打ち首になった大名がいました。
それは、肥前島原4万石の藩主松倉勝家です。
松倉勝家は、初代島原藩主重政の嫡男として、
1597年(慶長2年)に生まれます。
重政と共に島原城とその城下町の新築、
参勤交代の費用など種々の口実を設け、
また独自に検地を実施して
実質4万石程度の石高を10万石と過大に見積もり、
領民に10万石相当の過重な年貢・労役を課しました。
1630年(寛永7年)に重政が急逝した後を受けて
藩主となってからは、
父をも凌ぐ過酷な収奪を行って領民を苦しめます。
1634年(寛永11年)は悪天候と旱魃による凶作でしたが、
勝家は容赦せず重税を取立てます。
米や農作物の徴収だけでなく、
人頭税や住宅税などありとあらゆる税を新設して
厳格に取り立てたことが多くの記録に残っているとの事です。
勝家は年貢を納められない農民や、
村の責任者である庄屋から、妻や娘を人質に取るようになり、
島原の乱の記録を残した
長崎のポルトガル人ドアルテ・コレアは、
人質の若い娘や子供に藁蓑を着せて火をつけ、
もがきながら焼死する姿を
「蓑踊り」と呼んでいたという記録を残しています。
1637年(寛永14年)、口の津村の庄屋・与左衛門の妻は
身重のまま人質にとられ、
冷たい水牢に裸で入れられてしまいます。
村民は庄屋宅に集まり年貢を納める方法を話し合いましたが、
納める事が出来ず、
庄屋の妻は6日間苦しみ、水中で出産した子供と共に絶命します。
たまりかねた領民は蜂起し、
代官所を襲撃して代官を殺害しますが、
これが島原の乱の始まりです。
乱の鎮圧後、勝家は肥前唐津藩主寺沢堅高と共に
反乱惹起の責任を問われ、
勝家は改易、所領を没収され、
美作津山藩主森長継に預けられます。
勝家は悪政を布いたことを否定し、
キリシタンによる反乱を主張し続けますが、
その後松倉家の邸宅から
折檻された農民の遺体が発見されると容疑は定まり、
1638年(寛永15年)、
幕府は正式に松倉を江戸に召喚して評定を重ねた結果、
死罪と決して
7月19日、森家の江戸屋敷で斬首に処せられました。
その遺骸は松倉家の家臣に引き取られ、
芝の金地院に葬られました。
大名が切腹さえも許されず
一介の罪人として斬首刑に処せられたことは、
大反乱を引き起こす原因を作った勝家の失政を
幕府側が極めて重大な罪と見なしていたことを
示しているのでしょう。














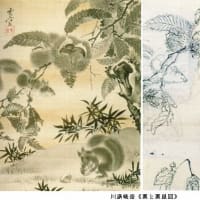







勝家の領民の生活を無視した収奪は、一説には幕府への賄賂を捻出する為と云う事も有った様です。この様な賄賂大名は松倉だけでは有りませんし、他のも多く居ました。江戸中期に自藩の苛政で大一揆をおこした、ええと誰だったかな?名前が出てきません??。この男も幕府への昇進狙いの献上金の為に、領民から年貢を収奪した結果起きた、大一揆でした。その結果は改易に成りました。こう云う事例は、徳川250年の間に何度も有った様です。死罪、打ち首は、島原の乱の責任者、勝家だけかも知れませんね。
江戸時代の付け届けの習慣は、今の生活からすると想像を超えたものがあったようです。
猟官運動のためには、とにかくお金が必要で、そのため泣かされた農民などは多かったでしょうね。
それ以外でも、藩主の華美な普請好きなど、農民にしわ寄せが行く事が多かったようです。
東遊雑記には、仙台藩がその体面を保つために、華美な行列を組むなどで費用がかかり、藩札を発行するのですが、それが信用されなかったとの話も出て来ました。
財政の基本を農業に頼っていた藩では、農民は過重な負担を強いられていたのでしょうね。
そうですね。
日本は、西洋と比べると暴君は少ないような気もしますが、
松倉勝家は酷い暴君だったようですね。