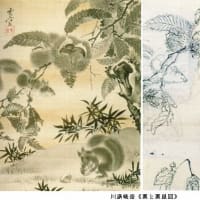武蔵坊弁慶は、平安時代末期の僧兵で、源義経の郎党と言われている人物です。
多くの人が知っている弁慶は、元は比叡山の僧で武術を好み、
五条の大橋で義経と出会って以来、郎党として彼に最後まで仕えた事でしょう。
講談などでは、義経に仕える怪力無双の荒法師として名高く、
その他の創作の世界でも義経と並んで主役格の人気があり、
怪力の者や豪傑の代名詞としても広く用いられています。
当時の歴史書である「吾妻鏡」には、わずかに義経の郎等として名前が載るのみです。
「平家物語」でも同じで、
いずれも出自や業績、最期等については全く触れられていません。
詳しく載っているのが、源義経とその主従を中心に書いた作者不詳の軍記物語
「義経記」(ぎけいき)ですが、
これは、南北朝時代から室町時代初期に成立したと考えられています。
能や歌舞伎、人形浄瑠璃など、後世の多くの文学作品に影響を与え、
今日の義経やその周辺の人物のイメージの多くは「義経記」に拠っています。
この弁慶の武具と言われているのが、弁慶の七つ道具です。
7つは何かとなると、説によって少し違いがありますが、
薙刀、鉄の熊手、大槌、大鋸、刺又、突棒、袖搦になる事が多いようです。
薙刀は、長い柄の先に反りのある刀身を装着した武具で、
誕生した過程についてはハッキリとはしませんが、
平安時代から徒歩戦用の武具として使われていたようです。
鉄の熊手は、長い柄の先に熊の手を模した鉄製の爪をつけたもので、
平安時代末期より武器として使用され、
敵を引っ掛けて倒したり、馬上から引きずり下ろしたりするなどの目的で
用いられていました。
大槌と大鋸は、立木を刈り倒して地面に杭を打ち柵や塀を築く築城や、
逆に敵側が築いた門扉や柵などを破壊する工兵器材として用いられ、
半ば応急的に武器として振るわれることもあったと考えられています。
刺又は、U字形の金具に2・3mの柄がついており、
金具の部分で相手の首や腕などを壁や地面に押しつけて捕らえる道具で、
江戸時代に作られた捕物道具です。
突棒も、江戸時代に使用された捕り物道具のひとつで、
頭部は鉄製で、形はT字型であり、多くの歯がついていて
2・3mほどの長い柄につけてあります。
袖搦は、先端にかえしのついた釣り針のような突起を持つ先端部分と
刺のついた鞘からなり、鞘に木製の柄に取り付けて使用するもので、
容疑者の衣服に先端部分を引っ掛けて絡め取る事で相手の行動を封じる武具です。
刺又、突棒などとともに捕り物の三つ道具とよばれ、
抵抗する人を取り押さえる際に使用された武具です。
以上のように、7つの内3つは、明らかに江戸時代から使われ始めたものです。
弁慶の七つ道具と言われるようになったのも、江戸時代からなのかも知れません。
江戸時代の川柳に、
「武蔵坊 ともかく支度に 手間がとれ」がありますが、
確かにこれだけの道具を準備して出掛けるとなると時間は掛かったでしょうね。
多くの人が知っている弁慶は、元は比叡山の僧で武術を好み、
五条の大橋で義経と出会って以来、郎党として彼に最後まで仕えた事でしょう。
講談などでは、義経に仕える怪力無双の荒法師として名高く、
その他の創作の世界でも義経と並んで主役格の人気があり、
怪力の者や豪傑の代名詞としても広く用いられています。
当時の歴史書である「吾妻鏡」には、わずかに義経の郎等として名前が載るのみです。
「平家物語」でも同じで、
いずれも出自や業績、最期等については全く触れられていません。
詳しく載っているのが、源義経とその主従を中心に書いた作者不詳の軍記物語
「義経記」(ぎけいき)ですが、
これは、南北朝時代から室町時代初期に成立したと考えられています。
能や歌舞伎、人形浄瑠璃など、後世の多くの文学作品に影響を与え、
今日の義経やその周辺の人物のイメージの多くは「義経記」に拠っています。
この弁慶の武具と言われているのが、弁慶の七つ道具です。
7つは何かとなると、説によって少し違いがありますが、
薙刀、鉄の熊手、大槌、大鋸、刺又、突棒、袖搦になる事が多いようです。
薙刀は、長い柄の先に反りのある刀身を装着した武具で、
誕生した過程についてはハッキリとはしませんが、
平安時代から徒歩戦用の武具として使われていたようです。
鉄の熊手は、長い柄の先に熊の手を模した鉄製の爪をつけたもので、
平安時代末期より武器として使用され、
敵を引っ掛けて倒したり、馬上から引きずり下ろしたりするなどの目的で
用いられていました。
大槌と大鋸は、立木を刈り倒して地面に杭を打ち柵や塀を築く築城や、
逆に敵側が築いた門扉や柵などを破壊する工兵器材として用いられ、
半ば応急的に武器として振るわれることもあったと考えられています。
刺又は、U字形の金具に2・3mの柄がついており、
金具の部分で相手の首や腕などを壁や地面に押しつけて捕らえる道具で、
江戸時代に作られた捕物道具です。
突棒も、江戸時代に使用された捕り物道具のひとつで、
頭部は鉄製で、形はT字型であり、多くの歯がついていて
2・3mほどの長い柄につけてあります。
袖搦は、先端にかえしのついた釣り針のような突起を持つ先端部分と
刺のついた鞘からなり、鞘に木製の柄に取り付けて使用するもので、
容疑者の衣服に先端部分を引っ掛けて絡め取る事で相手の行動を封じる武具です。
刺又、突棒などとともに捕り物の三つ道具とよばれ、
抵抗する人を取り押さえる際に使用された武具です。
以上のように、7つの内3つは、明らかに江戸時代から使われ始めたものです。
弁慶の七つ道具と言われるようになったのも、江戸時代からなのかも知れません。
江戸時代の川柳に、
「武蔵坊 ともかく支度に 手間がとれ」がありますが、
確かにこれだけの道具を準備して出掛けるとなると時間は掛かったでしょうね。