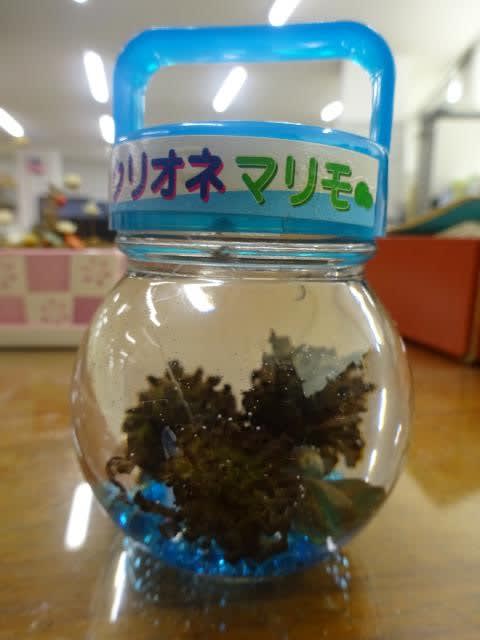憧れの谷川岳にとうとう来ました。
昨年は台風で周辺の道路が通行止め。
当然ロープウェイも運行停止で泣く泣く諦めましたが、
今年はロープウェイも順調に運行しており、あとはお天気次第。
今年のお盆休みは天候が悪く今年も駄目かと覚悟していたら、
この日に限って晴れてくれました。



ロープウェイの出発駅は土合口駅(標高746m)。
谷川岳ベースプラザの6階にロープウェイの切符売場をはじめ、
カフェテリア、売店などがある。
このプラザでビックリしたのは自走式立体駐車場で700台も収容できる巨大さだ。
http://www.tanigawadake-rw.com/

谷川岳ロープウェイ切符売場の所には天神平のお天気情報が出ていた。
真夏の暑い日に気温19℃とは、やはり山は涼しい。

これが谷川岳天神平の超シンプルな案内図。
ロープウェイで天神平駅に行き天神山と高倉山の麓が冬は天神平スキー場になる。
この図の右側に行くと谷川岳になる。

谷川岳と聞くとスミダマンの昔の印象は遭難事故が多くあった山。
しかも滑落の死亡事故が多発した山というイメージが強く残っている。
ですから登山カードは命綱といった感じだ。


ご覧のようにロープウェイ乗り場は長蛇の列。
乗るまでに約20分間ほど並んだ。


谷川岳のロープウェイは複式単線自動循環式ゴンドラ(通称フニテル)で
山岳の厳しい環境に対応した輸送の安全性を確保することを目的として誕生した。
風に強い安定性と快適性、高水準の機能はすべての人に安心して利用できる。
厳冬期の観光にも適応した設計で、足元を気にすることなく
駐車場からロープウェイ、天神平までを2,400m、最速7分で結んでいる。
なお、ベースプラザから天神平駅までの高低差は573mだ。

天神平駅に降りると群馬県の名物キャラクター「ぐんまちゃん」と
なぜかとなりのトトロのキャラクターが並んで出迎えてくれる。


谷川岳ロープウェイ「フニテル」で標高1,319mの天神平駅に着くと
目の前に極上の大自然の天神平が広がる。
春から秋の約半年間は高山植物のお花畑や
色鮮やかな紅葉の高原をのんびりウォーキングできる。
5月までのスノーシーズンには天神平自慢のサラッサラのパウダースノーを
スノボやスキーで満喫できる。

この日のこの時間に限ってご覧のように素晴らしい天候になり、
天神平から雄大・圧巻・幻想的な山々の風景を眺めることができた。
左から笠ヶ岳(1,852m)、朝日岳(1,945m)、山頂に雲がかかった山・白毛門(1,720m)だ。




天神平駅を降り、次に天神峠リフトに乗り換える。
このリフトはリフト長428m、高低差168m、頂上の天神峠駅は標高1,502mの所にある。
満席のリフトから周囲の素晴らしい風景を見ていた所に
大きな「ぐんまちゃん」人形が乗ったリフトとすれ違った。
「リアリー!?オーマイゴッド! イッツジョーク!」といった感じ。

リフトから振り向くと眼下に天神平駅。
天空のレストラン、ビューテラスてんじんなどの建物が小さく見える。
いやー、迫力ある風景ですネー。


天神峠駅に到着。
天神峠展望台から見た谷川岳連峰。
谷川岳は上信越国立公園内にあり、日本百名山の一つだ。
標高は1,977m、頂上はオキの耳(1,977m)とトマの耳(1,963m)だ。
その鋭く美しい山容とシルエット。
標高2,000mに満たないこの山が全国のアルピニストから熱い視線を注がれ、
数々の文学の舞台にもなっているのは、
この山の歴史が「日本のロッククライミング史そのもの」だからだ。
そのロッククライミングのメッカがこの山頂の裏手にある
一ノ倉沢、マチが沢だが、残念ながらここからは見えない。


ここ天神峠からは天神屋根ウォーキングコース(約2時間30分)、
さらに谷川岳山頂登山コース(約5時間30分)があり、
あこがれの高山頂上へ極上の大自然を自分の足で満喫できる。


片やこちらは奥利根の山々。
遠くにうっすら見えるのは赤城の山々か。



谷川岳の双耳峰のあたりもロッククライミングの本場としての
厳しい岩場の山肌を臨むことができる。


天神峠駅の近くに、なぜか諸天善神獄(中院)という天満宮が奉られている。
こんな山の山頂にも神社とは日本はやはり神の国だ。



時間はちょうど昼時になり、昼食は天神平駅近くのビューテラスてんじんでとることにした。
ここは冬のスキーシーズンはスキー客でごったがえしているのが目に浮かぶ。
システムはセルフスタイル。

そしてこれがメニュー。
そばにうどん、ラーメン、カレーと定番メニューが並ぶ。


塩ラーメン1,000円と冷したぬきソバ1,000円。
空気の美味しい所でタップリ歩いた後の昼食は街中で食べるよりずっと乙な味がする。



レストランの名の通り、ここはビューテラス。
目の前をロープウェイのゴンドラが迫ってきてそれを見ているだけでも楽しい。
さらに天空のレストランと言うだけに谷川連峰も窓から一望でき、
「花より団子」というよりは「団子より花」の場所だ。

冒頭のポスターは初夏バージョンだったが
山頂のポスターは秋の紅葉ポスターに変わっていた。