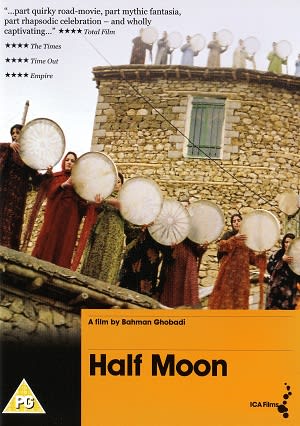東京外大「中東カフェ」と国際交流基金共催のシンポジウム『中東の今と日本 私たちに何ができるか』に出席した(2010/11/23)。

なお、以下は当方の理解に基づく聞き書きであり、各氏の正確な発言録ではない。※印は当方の所感。
■ アフガニスタン情勢 われわれはどう関わっていけるのか
(1) 田中浩一郎(エネ研) 「投げる匙、加減する匙」
○2001年の暫定政権成立以降、今はもっとも治安が悪く、いつの間にかイラク以下になっている。外国軍は最大規模の15万人ながら、武装勢力が「点」から「線」になってきている。
○誤算は地域性や民族性であり、全国横断的な政治団体はできないということ。
○国際的なカルザイ政権批判は主に汚職についてだが、それだけに着目すべきではない。
○集団的自衛権の発動は「オープン・エンド」であり、どこまでやれば終わるのか定められていない。
○イラク戦争への助走時に、アフガンを成功例として脚色した側面がある。
○ISAF(国連治安支援部隊)は治安維持よりむしろ武装勢力の掃討を実施している。
○NATOは2014年以降の治安維持委譲計画を持っている。
○日本においては、米国的見方への気遣いがレンズを曇らせてしまった。またテロ特措法による給油活動が論点をすり替えてしまい、まるで民生支援であるかのように見なされてしまった。
○現在、自衛隊の医務官を派遣し、軍医育成を行う議論がなされている。一方、日本ではNGOや市民を中心に「軍隊アレルギー」が強い。しかし、軍にしかできないことがある。
※軍にしかできないことがある、との理屈は既に軍の理屈ではないのか、という印象がある。
(2) 伊勢崎賢治(東京外大)
○現在、タリバンは勝てると思っているわけであり、アフガンでの仲介など無理な状況である。
○民主党は、テロ特措法によるインド洋での給油活動の停止をせざるを得なかった。その代わりに、米国を納得させるため、鳩山政権が5年間で総額50億ドルの援助を合意した。
○50億ドルの使途は、①治安支援(優秀な国軍と警察を作る)、②タリバン兵の社会復帰支援、③民生支援。
○①については、警察を短期間に急増させることになり、腐敗の象徴と化している。これを命令したのはブッシュ政権下のラムズフェルドである。カルザイ政権にとっては、カネで結びつけることができる力が増えたわけで、歓迎だろう。こんな恥かしい使途を公言するのは日本くらいだ。
○②については、結局はタリバンとの関係がグレーな民兵にカネが流れることになり、逆効果。
○③については、軍事組織が人道支援などすべきではないし、NGOがターゲットになってしまう。
○誰もがNATOに出ていってもらいたいわけだが、それは責任ある戦略をもってでなければならない。
○カルザイ政権は現在唯一の解である。しかし、日本のように彼を喜ばせるような活動はやめたほうがよい。
○ハードターゲットが狙われるのは当たり前であり、ちょっとした攻撃で引き下がると、日本の外交姿勢を疑われてしまう。
○(NATO撤退後の姿に関する質問に対して) 地下資源を狙う中国や、インドの対パキスタン戦略にも影響を与えるだろう。しかし、単純なNATO撤退は考えにくい。望ましくないが、空軍が無人機を利用するという方法もある。国を分割するという出口が最悪であり、テロリストにサンクチュアリを与えてしまう。パキスタンの政治にも影響することが必至で、インドがもっとも恐れていることだろう。
○(なぜ、そもそも国外がアフガンに介入しなければならないのか、という質問に対し) 立場上「介入ありき」である。
(3) 保坂修司(エネ研) 「アフガニスタンの異邦人」
○自爆テロを行った者たちの行動や動機を分析。
○インターネット上の掲示板では、米国・イスラエルへの怒りやイラクに関する書き込みがほとんどであった。しかし、米国やイスラエルに攻撃を仕掛けるのではなく、なぜアフガンで自爆テロを行う必然性があるのか。このような例は少なくない。
○彼らにはジハード、殉教への憧れがある。すなわち、彼らにとっては、より大きな大義のために死ぬことが目的と化している。
○自爆テロは、死にたいと思う人がインターネットで関係するテキストなどを探し、自分の行動を正当化するような「再生産」を繰り返している。テキストやヴィデオなどを見てその影響で自爆するわけではない。
○オサマ・ビン・ラーディンが発言するような「わたしはアッラーの道に殺されたい。それから生き返って、また殺され、また生き返って殺され・・・」といった考えが、アフガン、イラク、ソマリアでの殉教者の見本となっている。
○(自爆テロの源流に関する質問に対して) 19世紀インドでの対英ジハードであるムジャヒディン運動、80年代レバノンでのシーア派などが挙げられる。また、1972年ロッド空港での日本赤軍の乱射事件には、多くのアラブ人たちが共鳴した。現在では、自爆テロはOKだという認識が一般的なものとなってしまっている。
※日本赤軍に関するコメントには少なからず驚きを覚えた。
■ 石油産出国とどうつきあうか 産油国の抱える問題
(1) 武石礼司(東京国際大学) 「湾岸産油国経済の持続可能性」
○湾岸産油国の外国人比率は非常に高く(UAEでは74%)、どのようにまとめていくのか、どのように産業を育てていこうというのかという問題がある。
○石油収入額はどの国も伸びており、特にサウジが突出している。カネの使い道として武器がある。
○国内ではカネは不動産にしか入っていかず、たとえば自動車産業にしても設備だけの問題ではなく育成が難しい。
○(原発入札での日本の韓国への敗退について) 韓国サイドは60年保証という破格の条件に加え、途上国という隠れ蓑も影響した(連結決算すら一般的でない)。しかし実務上は、マスコミが騒ぐような話ではなく、実務的には日本サイドが受注する構造もある。
○中東でユニチャームが広まったのは「快適だから」である。日本人が日本から出たくないのは快適だからだ。つまり、日本が貢献したりビジネスを行ったりする種はあるはずだ。しかし、その気持ちが出てこない。
(2) 中川勉(外務省)
○イラクとアフガンの間にあるイランのプレゼンスが圧倒的なものとなってきている。現在、正規軍40万人+革命ガード10万人=50万人の軍隊を擁している。核開発問題もあり、イスラエルが攻撃を仕掛けるのではないかという危惧がある。
○イランのアフマディネジャド政権は安定している。しかし三選は不可能であるから、2013年には新大統領が誕生する。そのときに何が起きるか。
○日本は石油の90%をGCC(湾岸協力会議)諸国に依存している。一方、米国は輸入先をアフリカなどにもシフトし、エネルギー依存度を下げている。
○(原発入札での日本の韓国への敗退について) 日本政府にとってもショックだった。今後は政府によるトップセールスを積極的にしていく方向に変わってきた。
○(イランのような独裁国では情報が必要にもかかわらず、NHKなどによるニュース配信が不十分だとの指摘に関して) 賛成だが、「仕分け」が厳しく、政府のカネはなかなか使えない。またNHKは国民の受信料を使っているのであり、海外のために利用するのは問題があるとの意見もある。
(3) 河井明夫(中東調査会)
○中東と日本との重層的関係パートナーシップは、日本の教育システムの導入が下支えしている面がある(しつけ、挨拶、公文式)。
○サウジでも若者の失業問題が深刻で、日本の技術に関する職業訓練校を立ち上げる試みがある(その後その企業で働く)。
■ 中東和平の現状と日本 市民にできることは何か
(1) 池田明史(東洋英和女学院大学) 「パレスチナ問題の現在~袋小路の構造と背景~」
○小さいパレスチナにおいて、欧州、アラブ、ユダヤという三つ巴のナショナリズムが対抗していた。そこから欧州が離脱し、アラブとユダヤの二項対立・全否定の関係となった。
○ゴラン高原はイスラエルがシリアから奪ったものであり、構図はわかりやすい。一方、ヨルダン川西岸やガザ地区は「誰から奪った」かが明確でないため、「誰に返すか」もはっきりしない構図。というのも、お互いに相手を認めないからだ。その意味で、返す相手を設定したオスロ合意(1993、1995年)は、ゼロから1になったという大きな意義があった。
○パレスチナ自治が拡がって行ったが、イスラエルに自治地域間を封鎖されてしまうと、都市間の移動が不可能になった。むしろ移動に関しては占領下のほうが自由であった。つまり自治により閉塞感が強まるという逆説だが、このことに国際社会は気付かない。
○パレスチナは、ヨルダン川西岸のファタハとガザ地区のハマスとに分裂した。ハマスはイスラエルを認めない集団であり、ハマスの総選挙での勝利には国際社会は困惑した。
○占領下におかれた時間の長さという非対称的な力関係を考慮に入れる必要がある。
○国家はカネの使い道にプライオリティを付けるものである(例:戦後日本)。一方、パレスチナでは「一度に全部やりたい、そのために援助が必要だ」という論理であり、国を作っていき一体感を醸成する形でなくなっている。
○和解協議は責任不在による持ち越しの連続である。特に、治安組織をハマス、ファタハ、イスラエルがどのように持つのかが難しい問題であり、和解を不可能なものとしている。
○インターネットでの情報の遮断は行われていない。しかし、意識の共有が進まないのは、相手の情報にアクセスしたくないという心理的な要因が働いているからではないか。特に壁の構築が大きな分岐点となった。
○パレスチナの政治的一体性を確保した方が国際的には都合がよいのであり、窓口をひとつにするプロセスには国際社会はあまり立ちいってはならないのではないか。2006年のハマス勝利以降の国際社会介入は判断ミスであった。
(2) 立山良司(防衛大学校) 「中東和平の現状と日本:対パレスチナ援助の現状と問題点」
○1994~2009年の対パレスチナODA援助合計は157億ドル、うちDAC(OECD開発援助委員会)諸国は74億ドル、うち日本は10億ドル。
○日本の対パレスチナ援助の中には、ヨルダン川西岸地域へのごみ処理施設+システム導入なども含まれている。
○パレスチナ経済は貿易収支が大幅赤字という特徴を持ち、支援が赤字の半分以上を補填する構造となっている。また、直接投資がきわめて少ない。
○イスラエルの封鎖により、ガザ地区の1人あたりGDPは急減している。
○イスラエルの占領政策による「de-development」(サラ・ロイ:「経済の内在的な成長に必要な(資本などの)投入が妨げられているため、経済の成長・拡大の能力が蝕まれ弱められるプロセス)、援助依存体質の拡大、援助を受ける一部の人々の金持ち化・腐敗、和平より日常生活への関心のシフト、占領者が持つ実権、といった特徴もある。
○ハマスの中にもいろいろな者がおり、また地域によっても異なる。ハマスがいないふりをすることはできないのであり、公的にも私的にも聴く耳を持つ必要がある。
※de-development、援助漬け、一部の歪な肥大、当事者が持たざる実権など、沖縄に重なる点が多い。
(3) 田中好子(パレスチナ子どものキャンペーン)
○(池田氏の指摘に関して) パレスチナではNGOが昔から活動しており民度が高い。そのため、開発独裁が難しい。
○ガザ地区では8割の人が援助物資に頼っている。
○建設物資以外はカネで手に入る。停電が多いという問題もある。
○facebookが盛んだが、それで知り合って大学の前で歩いていた男女がハマスに拘束されたという事件があった。すでに文化的拘束がはじまっている。
●参照
○ソ連のアフガニスタン侵攻 30年の後(2009/6/6)
○ガザ空爆に晒されるひとたちの声
○酒井啓子『<中東>の考え方』
○酒井啓子『イラクは食べる』