勤務先の小学校でつかっている算数の教科書の後のほうには、
切り取って使える図形の付録がついています。
色んな四角形と三角形が7つ組み合わさって大きな正方形を作っているのを、
ミシン目に沿って切り取り、自分たちで組み合わせて色々な形と大きさの
四角形を作ってみるのです。
少人数担当の先生は、この導入部を2時間少しかけてやりました。
使うピースの数だけを指定して、自由に四角(ここでは、長方形と正方形)を作らせます。
「2枚で四角」は、みんな結構すぐに作ります。三角二枚で四角というのは良く刷り込まれているようです。
「3枚で四角」「4枚で四角」「5枚で四角」「6枚で四角」「7枚で四角」
となると、やり方も色々。
細長い四角を作る子もいれば真四角に近づけようとする子もいます。
なかなか四角にならないという子もいます。
お手上げ状態の子には、
「できた子のをチラッとだけ見せてもらっていいよ。」
と、促します。
どうしても出来そうにない子は、本人の気力が途切れないうちに、
私が早めのフォローに入ります。
たいがい途中までは作ってあるので、
はまってしまっているところを見つけ、ちょこっと動かすだけですけど、
それだけで止まっていた手が動き始めるんですね。
出来れば嬉しい。だから次にチャレンジしようという気が起きる。
そうして、自分で取り組む時間はだんだん伸びていきます。
図形最初の授業は、切り取って、それに名前を書いて、
残り時間はひたすら四角作りで終わりました。
さて、2時間目。
この日の課題も丸きり同じでした。
「2枚で・・・」「3枚で・・・」「4枚で・・・」・・・・
1時間目には、
六角形なのに、「できたぁ!!」
と喜んでいたN君も、
枚数の指定を聞き逃して、自分勝手な作り方をしていたH君も、
最後の1枚がどうしてもはまらなくて困ってしまうM君も
「どうするの。どうするの。」と騒いでいたKちゃんも、
コツをつかんだらしく、
それぞれのペースでちゃんと四角を作っていきます。
(kちゃんは相変わらずうるさいけど・・)
出来た子は嬉しいので、しばらく机の上に置いておきますから、
それをみて、同じ枚数でも違う形の四角にくみ変えたりもして、
枚数が増えても、
「わからない!できない!」
という声がでなくなりました。
授業の最後に、
「今使った7枚をね、ふたつの仲間に分けて欲しいの。さぁどう分ける?」
と、5分ほど。それぞれの理由を言わせて、
「辺」と「頂点」という言葉を習ってこの日はおしまい。
3時間目も、最初の10分ほどが、「四角作り」でした。
もう、私の手を必要とする子はいません。自分たちで勝手に作り始めます。
結構、チエと根気を必要とする作業なのですけど、全員楽しそうに集中しています。
初日、私の占有率が一番高かったR君も自信満々でピースを動かしています。
「導入」に具体物を使うのは学校では良くあることです。
でもね、もしもこの「導入の授業」が、1時間目だけで終わっていたら、
こんな雰囲気は生まれていないだろうなって思います。
最初の授業では、私も思いっきり走り回ります。
「周りの皆が出来ていく中、自分だけが出来ない」
という劣等感や、
「何をしたら良いのかわからない」
という理由で、自信なく手を止めている子の
気持ちを「行動」に向けるためです。
そのサポートで、子ども達の止まっていた手は動きだします。
動けば、また何かが見つけられる。
それが、授業内での個別フォローの良さだと思っています。
でも、本当の意味での達成感は、やはり
「手助けなし」のときのほうが大きいんです。
2時間、3時間と同じ課題が与えられ
(課題内容を掴みにくい子も1時間目に個別フォローで理解済みです)、
焦らされずに取り組む時間があり、
わからなければ、出来た子のを「チラッとだけ」
見せてもらってもいい。
という安心感が子ども達の集中力を呼ぶんだと思うんです。
「チラッと見てもいい」ことになっていても最初からみる子はいません。
図形の学習を進めていくときに、「直角」に気付く事ができるか出来ないかは、
今後大きな差になっていきます。
「直角」という言葉を知らなくてもいいんです。
こうしてじっくり形作りに取り組みながら、
四角というのは、角が段々になっていたり、とがって飛び出していたりしちゃいけないんだ。
カクンって曲がるところが4つあればいいんだ。
っていう事を、手と目で覚えていくのに、この時間はとても大事だったなぁと思います。
切り取って使える図形の付録がついています。
色んな四角形と三角形が7つ組み合わさって大きな正方形を作っているのを、
ミシン目に沿って切り取り、自分たちで組み合わせて色々な形と大きさの
四角形を作ってみるのです。
少人数担当の先生は、この導入部を2時間少しかけてやりました。
使うピースの数だけを指定して、自由に四角(ここでは、長方形と正方形)を作らせます。
「2枚で四角」は、みんな結構すぐに作ります。三角二枚で四角というのは良く刷り込まれているようです。
「3枚で四角」「4枚で四角」「5枚で四角」「6枚で四角」「7枚で四角」
となると、やり方も色々。
細長い四角を作る子もいれば真四角に近づけようとする子もいます。
なかなか四角にならないという子もいます。
お手上げ状態の子には、
「できた子のをチラッとだけ見せてもらっていいよ。」
と、促します。
どうしても出来そうにない子は、本人の気力が途切れないうちに、
私が早めのフォローに入ります。
たいがい途中までは作ってあるので、
はまってしまっているところを見つけ、ちょこっと動かすだけですけど、
それだけで止まっていた手が動き始めるんですね。
出来れば嬉しい。だから次にチャレンジしようという気が起きる。
そうして、自分で取り組む時間はだんだん伸びていきます。
図形最初の授業は、切り取って、それに名前を書いて、
残り時間はひたすら四角作りで終わりました。
さて、2時間目。
この日の課題も丸きり同じでした。
「2枚で・・・」「3枚で・・・」「4枚で・・・」・・・・
1時間目には、
六角形なのに、「できたぁ!!」
と喜んでいたN君も、
枚数の指定を聞き逃して、自分勝手な作り方をしていたH君も、
最後の1枚がどうしてもはまらなくて困ってしまうM君も
「どうするの。どうするの。」と騒いでいたKちゃんも、
コツをつかんだらしく、
それぞれのペースでちゃんと四角を作っていきます。
(kちゃんは相変わらずうるさいけど・・)
出来た子は嬉しいので、しばらく机の上に置いておきますから、
それをみて、同じ枚数でも違う形の四角にくみ変えたりもして、
枚数が増えても、
「わからない!できない!」
という声がでなくなりました。
授業の最後に、
「今使った7枚をね、ふたつの仲間に分けて欲しいの。さぁどう分ける?」
と、5分ほど。それぞれの理由を言わせて、
「辺」と「頂点」という言葉を習ってこの日はおしまい。
3時間目も、最初の10分ほどが、「四角作り」でした。
もう、私の手を必要とする子はいません。自分たちで勝手に作り始めます。
結構、チエと根気を必要とする作業なのですけど、全員楽しそうに集中しています。
初日、私の占有率が一番高かったR君も自信満々でピースを動かしています。
「導入」に具体物を使うのは学校では良くあることです。
でもね、もしもこの「導入の授業」が、1時間目だけで終わっていたら、
こんな雰囲気は生まれていないだろうなって思います。
最初の授業では、私も思いっきり走り回ります。
「周りの皆が出来ていく中、自分だけが出来ない」
という劣等感や、
「何をしたら良いのかわからない」
という理由で、自信なく手を止めている子の
気持ちを「行動」に向けるためです。
そのサポートで、子ども達の止まっていた手は動きだします。
動けば、また何かが見つけられる。
それが、授業内での個別フォローの良さだと思っています。
でも、本当の意味での達成感は、やはり
「手助けなし」のときのほうが大きいんです。
2時間、3時間と同じ課題が与えられ
(課題内容を掴みにくい子も1時間目に個別フォローで理解済みです)、
焦らされずに取り組む時間があり、
わからなければ、出来た子のを「チラッとだけ」
見せてもらってもいい。
という安心感が子ども達の集中力を呼ぶんだと思うんです。
「チラッと見てもいい」ことになっていても最初からみる子はいません。
図形の学習を進めていくときに、「直角」に気付く事ができるか出来ないかは、
今後大きな差になっていきます。
「直角」という言葉を知らなくてもいいんです。
こうしてじっくり形作りに取り組みながら、
四角というのは、角が段々になっていたり、とがって飛び出していたりしちゃいけないんだ。
カクンって曲がるところが4つあればいいんだ。
っていう事を、手と目で覚えていくのに、この時間はとても大事だったなぁと思います。










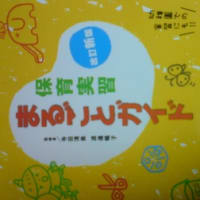




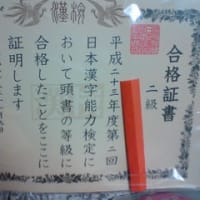




息子のクラスで「導入部分」は「みんな当然知っているはず」ということで殆ど省かれているようです。習熟度別でやっているのにですよ。
時間がないんだそうです。
なので、我が家でフォローすることになりますが・・・。
「導入部分」に時間を掛けるということはある意味「急がば回れ」の様なものでとても大切だと思っています。
seiさんの様な方に息子のクラスで子ども達の学習を一押しして頂けたら助かる子どもが(息子も含めて)随分いるのになと思うこの頃です。
『導入』がただのきっかけ作りに終わるか、子ども達の中にしっかりと刻みこまれる物になるのか、その辺りが先生の工夫のしどころなんだと、色んなタイプの先生方の授業を拝見してそう思います。
先生達が持っている指導用の教科書(赤い字がびっしり書き込んであるもの)では、そう長い時間とっていないんですね。最初の1時間で終わっちゃう。
だから、マニュアルを外れる度胸のある先生でないと、なかなかそういう授業が組み立てられないのかなとも感じます。
のんびりちゃんの親としては、『導入』という感じではなくて、その単元の間中、授業の最初の5分とか10分をこんな取り組みに当てたらどうかなぁなんていうことも考えます。
1度や2度、3度でも要領がわからない娘ですが、繰り返せばやる事がわかってきて楽しめるようになりますから。
そういうお子さんって、教室に必ずいるんですよね。