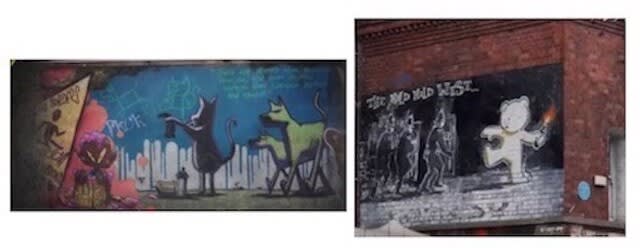世界各地に足を運んでいる村上春樹さんが、アイスランドを訪れていたのを、紀行エッセイで知りました。「緑の苔(こけ)と温泉のあるところ」(「ラオスにいったい何があるというんですか?」(文春文庫)所収)がそれです。国土の一部が北極圏に属する厳しい自然の中で、36万人の人々が、生活を楽しみ、自然と親しむ暮らしぶりが興味深く、また、春樹さん流の心温まるエピソードも堪能しました。さっそくご紹介することにします。どうぞ最後までお付き合いください。
★本好きの国★
2003年9月、春樹さんは、アイスランドの首都レイキャビクで行われた「世界作家会議」に招待され、自作の朗読、公開インタビュー、講演会などを行いました。いまや世界的作家である彼を呼ぶところが、いかにも読書好きのお国柄です。
事実、春樹さんによれば、人々は読書に熱心で、家にどれだけきちんとした書棚があるかでその人の価値が測られる、というのです。人口の割に大きな書店も多く、「たぶん冬が長くて、屋内で過ごすことが多いということもあるのだろう」(同書から)との推測に頷けます。
本を読むだけではなく、「書く」ほうにも熱心な国です。1955年にはハルドール・ラクスネスが、ノーベル文学賞を受賞しており、彼が亡くなった時には、作品が数週間にわたってラジオで朗読されるなど国を挙げてその死を悼んだといいます。レイキャビクだけで、340人が作家登録している、というのにも驚きました。
★パフィンを守る国★
パフィンという鳥をご存知でしょうか。成鳥は、ご覧のように、オレンジ色の大きなクチバシをした可愛い鳥です。(ネットから)

北極近辺の海の断崖に集団コロニーを形成し、巣穴で子育てをします。アイスランドにはその集団コロニーが集中し、なんと600万羽が棲息するパフィン王国です。春樹さんも、国の南岸のウェストマン諸島の中で、唯一、人が住むヘイマエイ島(人口4400人)を訪れました。
さあ、パフィン見物、と張り切る春樹さんに、地元の人は、この時期(9月)には、親パフィンはいず、子供たちが少し残っている程度かも、と言うのです。こういうことです。
8月末頃に、親鳥たちは、子供たちを置いたまま、一斉に、7か月にもわたる海上生活に入ります。地上には一度も降りず、ひたすら魚をエサにしての生活です。子パフィンしかいない時期に行き合わせたことになります。でも、これが春樹さんに、貴重で心温まる体験をもたらしました。
巣に残された子パフィンは、本能を信じて、自力で飛び立つしかありません。うまく羽ばたけて、風に乗れればいいのですが、失敗するパフィンもいます。そして、飛び立てたとしても、エサの魚が穫れなければ、生き延びられない、という厳しい世界です。
中には、うまく飛び立てたものの、灯りにひかれて街に迷い込む子パフィンがいます。街の人たちは、それらを救出してやるのです。見つけたら、段ボールなどに入れて、エサを与えます。体力がついたら、崖の上から放してやるのです。海上生活ができることを願いながら・・・
春樹さんも救出に参加すべく街へ出ましたが、港で死んだ子パフィン1羽を見つけただけでした。その写真です。(同書から)

子パフィンは外敵から身を守るためなのでしょうね、ご覧の通り、クチバシも含め全身ほぼ黒ずくめです(1年ほどで成鳥になれば、あの鮮やかなクチビルになるそう)。
さて、首都へ帰る飛行機便が欠航となって、フェリーで帰途についた春樹さんは、放鳥の現場を目撃します。乗っていた父親とその息子が、ダンボールから子パフィンを取り出して、頭をなで、強風の中に投げ上げたのです。「子パフィンは「あれあれ」という感じで、しばらくのあいだそのへんの空をぎごちなく飛んでいたが、やがて海上に降りて、そこに浮かんだ。そしてあっという間に、小さな黒い点になって、波間に見えなくなった」(同前)
春樹さんも「がんばれよ」と思わず声をかけたといいます。
★温泉の国★
火山国アイスランドといえば「温泉」です。車で走っていると、あちらこちらに白い湯気を上げている小川があるといいます。春樹さんが体験したのは、温排水を利用した広大な人工の温泉です。レイキャビクから車で1時間ほどのところにある「ブルー・ラグーン」は、小さな湖ほどの広さがある観光スポットで、春樹さん(写真手前)も水着着用で楽しみました。スケールが大きい分、しっかり料金を取られて、国の収入に貢献したとのこと。

いかがでしたか?う~ん、若い頃にこの情報があれば、間違いなく行ってますね。なお、以前、椎名誠さんのアイスランド紀行を話題にしました。リンクは、<第475回 椎名誠のアイスランド>です。併せてご覧いただければ幸いです。それでは次回をお楽しみに。










 <
<