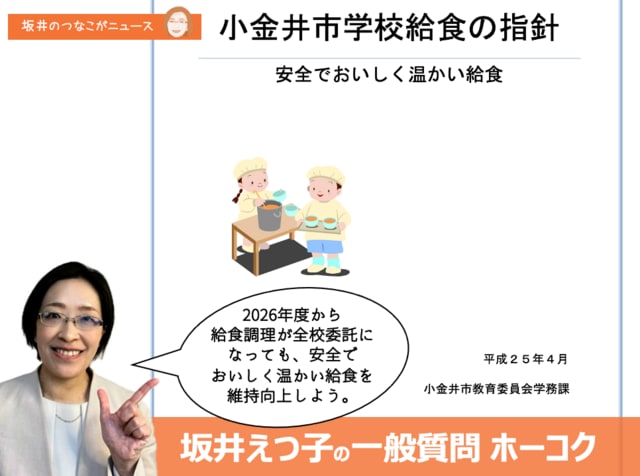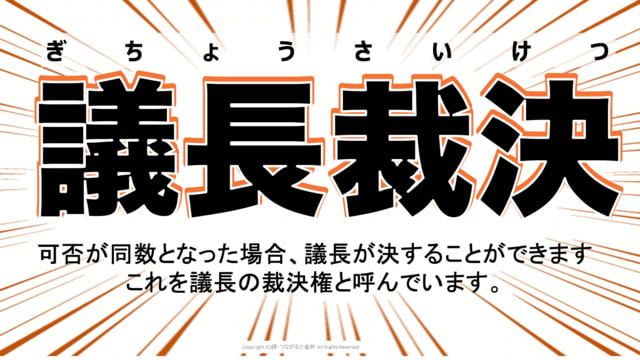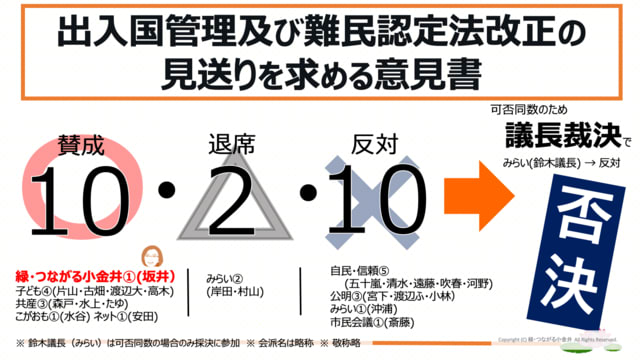。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。.。
1 “障がいのある児童もない児童も共に学び共に生きる”学童保育所を。
2 はけと野川をこわす道路はいらない
。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。゚+。.。・.。.。
今回は2項目取り上げました。1つずつ振り返ります。

“障がいのある児童もない児童も共に学び共に生きる”学童保育所を。
YouTubeは🐔ここ🐔から
小金井市には、「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例」があります。共に学び共に生きるための環境を整えれば、よりゆたかな社会になると考えています。学童入所申請の手引きについて、保護者の方の声をお聞かせいただく機会があり、取り上げた方が良いと考えたので質問しました。
それは、学童保育所入所申請の手引の表記が差別的で異議があるとのこと。
小金井市 学童保育所入所申請の手引には、心身に障がいのある児童という項目があります。それによると、入所については、いくつかの要件に該当することが必要となります。そのひとつが、”集団保育に支障なく適応 ”することです。
”集団保育に支障なく適応 ”
(坂井)
”集団保育に支障なく適応”することは、学童に通うすべての児童に求められることである。すべての児童に求めるわけではなく、障がいのある児童にのみ要件しているのは、差別的と考えるが見解は?
(答弁)
ご指摘の通り。ご指摘の表現等も含め、障がい者サービス担当部署の助言をいただきながら、現在、表記の検討を進めているところです。
手引ではわからないけれど、合理的配慮がなされている現場。
実際の対応を確認したところ、例えば、医療的ケアが必要な場合は、定時的に看護師が学童保育所を訪問する、概ね障がい児2名に対し、1名の職員を加配(当該障がい児に常時対応する職員配置ではない)するなど、対応されていることがわかりました。
入所にあたっての基本的な考え方は、”共に学び生活する場”
坂井が表題にした「“障がいのある児童もない児童も共に学び共に生きる”学童保育所を」は、学童保育所の職員も念頭においている理念であるとの答弁がありました。例えば、ある学童保育所では、班活動のリーダーである3年生たちが、障がいのある児童との交流を積極的に図る等、学童での集団保育が、共に学び生活をする場となっているそうです。
学童への送迎が保護者対応になっている点は課題
「通所に際しては、保護者等による送迎が可能であること。ただし、市⻑が特別な理由があると認める場合はこの限りではありません」という要件もあります。市の答弁では、「集団保育の対応に支障がない範囲で、学童から目視できる距離での来所支援を行う場合もある」ということ。
保護者が送迎するにしても、他のサービスを探すにしても大変。本当は、移動支援が使えると良いのですが、制度に課題があるところです。
入所申請の手引きの表現が変わる見込み
現状の入所申請の手引きと実際の対応が違うので、現状に即した表現にかえるように提案したところ、検討してくださるとのことでした。
今後のご対応に注目してまいります。
今回は、要件にもある障がいの程度については触れませんでした。
答弁で”交流”という言葉があったのをスルーしていたのは反省点です。