がん患者の悩みに寄り添うプロの「伴走者」 医療コーディネーターを知っていますか?
がんの闘病生活は精神面のケアも重要だ。仕事や、子育て、介護はどうすればいいか。治療法は最善か。患者のあらゆる悩みに寄り添う存在がいる。(編集部・吉岡秀子)
医師から「がんです」と告知を受けたとたん、患者にはやるべきことが次々と襲いかかってくる。治療法をどうするか、セカンドオピニオンは誰に聞くか、入院か通院か、職場には何と説明したらいいか、家族にどう話せばいいか……。病魔と闘いながらさまざまな問題を解決しなければならない。混乱するなというほうが無理だろう。
4年半前、ステージIVの肺腺がんと診断された元銀行員の女性(57)は、がん専門病院で抗がん剤治療を続けてきた。
独身で一人暮らし。離れて暮らす80歳を超える母親に心配をかけまいと、がんのことはきょうだい以外誰にも言わず、治療のこと、仕事のこと、すべてひとりで決めてきた。
●病院で教わらない情報
気丈な女性の心が折れかかったのは治療を始めて2年が過ぎたころ。薬が効かず、医師から「もう手立てがない」と宣告された。頭の中が真っ白になった。
そんな時だ。あるがんのシンポジウムで「医療コーディネーター(メディカルコーディネーター、以下MC)」の話を聞いた。MCとは、医療の専門知識を持ち、患者の希望に応じて医療機関との橋渡しや、闘病生活のサポートをしてくれる人だ。
「在宅のがん治療もあります、という説明にハッとしました。治療法はもうないと言う病院の視点とは違うなと感じました」
その場で声をかけ、このMCが所属する「日本医療コーディネーター協会」に連絡。初めて会った最高顧問の嵯峨崎泰子さんの対応は期待を超えていた。
病院では教えられなかった種類の抗がん剤や、抗がん剤以外の治療法も残っていることなどについて、丁寧でわかりやすい説明を受けた。転院できる病院があるかどうかも、嵯峨崎さんの臨床看護師のネットワークから情報を得た。
●手術中に母の付き添い
「豊富な医療知識に裏付けられたアドバイスと治療に結びつくサポートが頼もしかった。『大丈夫、安心しなさい』と言われた言葉は忘れられません」 以来、MCには検査結果を聞くのに同行してもらったり、新しい治療法を教えてもらったり。不安な時に連絡を取る。ひとりで闘っているんじゃない、と思えることが回復力をアップさせるようだ。
そもそもがんと闘うには、医療の力だけでは不十分だ。病気からくる不安や、闘病生活の悩みなどを相談する相手が必要になる。だが多くの場合、忙しい担当医に長時間かけて相談はできないし、プライベートな問題を医療現場に持ち込むことは気が引ける。そんな医療の枠を超えたサポートができるのもMCの特徴だ。
税理士の女性(60)は、婦人科で「卵巣が腫れている」と、がんの疑いを指摘された。手術を受けることになったが、2人暮らしの90歳の母親が手術中、病院で待つという。
「ひとりで大丈夫だろうか」
そこで知人のMCに母の付き添いを頼んだ。病院で母の話し相手になってもらう。MC用語で「傾聴」と呼ばれる「相手を落ち着かせるためにじっくり話を聞く」役目だ。女性も安心して手術に臨めたという。
患者の小さな悩みも聞き入れる。それが医師でもない、家族でもない相談者として、MCが注目されてきた理由だ。
10年前からMCとして活動している同協会理事の高橋菜子さんによると、患者からの相談は次の四つが多いという。(1)主治医との関係づくり、(2)治療法など意思決定の際のサポート、(3)家族や仕事などの悩み、(4)生活や食事の指導。
●気兼ねない第三者
相談によっては、がん相談員やソーシャルワーカー、栄養管理士などに相談することもできるが、多くは院内でのサポートで、受付時間も限られている。その点、MCは個人が独立して活動しているため、いつでもどこでも対応してくれる。医療の“顧問弁護士”のような存在といっていいだろう。
実は、患者の悩みで深刻なのは人間関係だ。家族と主治医が合わなかったり、幼い子どもや介護が必要な親がいたりする場合など、患者は自分の病気よりも周囲に気を使い疲れてしまう。
「こうしたことは気兼ねのない第三者が介入したほうがうまくいくケースが多いんです。MCの基本は、患者さんの心身のバランスを整え、自分で納得して治療を受けられるようにすること。心に寄り添い、できる範囲のことはすべてします」(高橋さん) MCはボランティアではなく、依頼費は同協会の場合1時間1万800円。その後30分ごとに5400円がかかる。安くはないが、医療知識を持ち、伴走者のように患者の日常を支えてくれる人はそういない。現在、同協会の認定MCは約100人。「認定」と名乗る場合は、医療や福祉資格を持つ人に限る。
栃木県在住の木原明子さん(52)は協会に相談し、がん患者の悩みを聞く「がんサロン」を開いた。MC活動のひとつだ。
木原さんは48歳の時、突然舌がんを宣告された。受験を控えた2人の子どものことを考えると心が痛んだ。それでも落ち着いて抗がん剤治療と手術を乗り越えられたのは、看護師の妹の存在が大きかったという。
●医療と福祉をつなぐ
「治療法の相談をしたり、主治医との面談に同席して専門的な説明をわかりやすく解説してもらったりしました。思えば妹が私のMCだったわけです」
と木原さんは振り返る。「信頼できる理解者・医療者の存在」がこれほど心の支えになるとは。そう痛感した。
「医療者と患者の信頼関係は、対話して心を通わせることから始まる。日本の医療現場は忙しすぎて、その根本的なことができていないと思う」(木原さん)
サロンでは、必要に応じて専門知識を持つMCや医療機関を紹介する。悩みを聞くだけで患者や家族は冷静さを取り戻せる。木原さんは、MCがもっと一般的になって、全国的な仕組みになることを願う。
市民医療協議会がん政策情報センターが行った「がん患者意識調査2010年」で、「がんの診断や治療で抱いた悩み」で最も多かったのは、「痛み、副作用、後遺症などの身体的苦痛」で60.5%。続いて、「落ち込みや不安、恐怖などの精神的なこと」で59.3%だった。心のケアのニーズは高い。
北里大学医学部附属新世紀医療開発センターの荻野美恵子講師は、今後MCの必要性が高まると見ている。高齢化により最後まで自宅で過ごす人が、ますます増えるからだ。地域医療の仕組みを強化すべきだという。
「ソーシャルワーカーやケアマネジャーなどは医療や介護の制度には詳しいが、医学的な視点は弱い。地域に根ざしたMCと連携することで、医療と福祉の両面をつなぐ人材ネットワークが地域にできる。これは患者や家族はもちろん、医療者にとってもメリットです」(荻野さん)
病は突然やってくる。そのときMCという存在が、闘病生活と人生を支えてくれる。
※AERA 2015年9月7日号














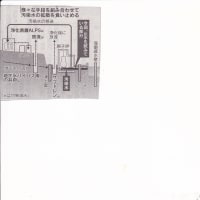
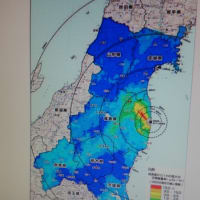
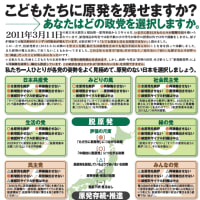





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます