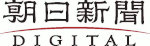新型ウイルス、中国国内の死者80人 感染者2300人超に
■いじめや成績不振の共通の原因
いじめや不登校、成績不振、人間関係……。子どもの学校生活の問題について、多くの親はなぜこんな事になったのかと、友人関係や学校など、どこか自身(養育者)と子どもの関わり方とは関係のない場所から原因を見つけようとします。
ところが、これらの問題に共通してあげられている原因として、「幼少期の愛着形成」があります。
愛着とは、「特定の対象に対する特別な情緒的な結びつき」のことで、その基盤は幼少期に形成されると言われています。幼少期の子どもと養育者の間に形成される愛着は、どのように育まれ、どのようなことに影響するのでしょうか。
■愛着の量より質が重要
親(養育者)と子どもの愛着形成は、生後間もなくからスタートしています。子どもから発せられる信号(泣いたり笑ったり不安そうだったりという感情の表れ)に対して、敏感に察知し、それに応えてあげることが愛着形成の重要な過程です。
多くの研究が、幼少期の子どもが親に助けを求めた時に、親がどれくらいそれを受け入れてあげることができているか、情動的な観点から、親がどのくらい子どもに対して対応してあげられているかによって、子どもの愛着形成に大きな差が出てくると報告しています。愛着の形成に重要なのは、「どのくらい子どもの感情的な変化について敏感に察知し、対応してあげられるか」であり、子どもと関わる時間の長さそのものではありません。
例えば、ひと昔前は、“抱き癖がつく”という理由で、泣いている赤ちゃんをすぐに抱っこしない方が良い、とされていました。現在は、赤ちゃんの頃から沢山抱きしめて安心させてあげましょう、という考え方が主流になっています。
また、幼児期の子どもがお手伝いをしようとしても、「危ない」あるいは「余計な手間になる」などの理由から、お手伝いをさせてあげない、目の前にいるのに子どもが話しかけても(スマホやその他のことをしていて)あまり向き合ってくれないなどと、親からの拒否傾向を子どもが感じていると、安定した愛着形成ができないことが明らかになっています。
■最初の愛着形成があらゆる人間関係のテンプレートに
安定した愛着は、なぜ必要なのでしょうか。
子どもは親の対応から、自分は受け入れてもらえる存在なのか、保護や注意を払ってもらえるだけの価値があるのかという、自己や他者に対する自信や期待をどのくらいもっていいのかというような概念を形成していきます。
感受性が高い養育者は、時々刻々と変化する子どもの心の状態を読み取り敏感に対応するため、子どもはその養育者のもとで、自分が受け入れられる存在であることに安心し、安定した愛着を形成することができます。その結果、安心して、相手(養育者)の心を読むこともできるようになっていきます。
■愛着不形成が起こすさまざまな問題
ところが、養育者が子どもの情動に対して適切に対応していない場合、子どもは養育者の気まぐれな行動から生じる自分自身の混乱や苦痛のほうにより注意が向いてしまい、相手の心の状態を読み取ることにも困難が生じます。
子どもにとって、最初の人間関係である養育者との関係性のあり方は、その後の人間関係のテンプレートになります。その結果、養育者との安定した愛着を形成できた子どもは、その後も相手の心をきちんと理解し、相手への信頼や、自尊心(自分への適切な自信)を持ち、安定した人間関係を作っていけるのです。
逆に、人の感情が理解できなかったり、自信の無さから見捨てられる不安が強くなったりして、試し行動などを頻繁にしてしまう人は、幼児期における不安定な愛着形成と関連があることも明らかになっています。ただし、そのような場合でも、親元を離れ、特定の異性と関わっていく中で、愛着が安定してくることがあることも報告されています。
■幼少期の親子関係が、「やりきる力」にも影響する
おそろしいことに、幼少期の親(主に接触時間が長い母親との報告が多い)との愛着関係が与える影響は、その後の人間関係だけではありません。中学生になったときに、「自分の能力を伸ばそうと難しいことに挑戦・努力して目標を達成することや、何か新しいことを習得するようなチャレンジ力にも大きな影響を及ぼします。
不安なときや困ったときには助けてくれる、そんな親への安心感・信頼感があって初めて子どもは新しいことにチャレンジできるのです。私の研究からも、目標に向かって努力をする学生は、頑張るほどに不安が高くなる傾向が示されており、頑張り続けるためには安全地帯があることが重要になってくるのでしょう。
さらに、親への安心感や信頼感が低い子は、不登校になる傾向が高く、学校生活における規則やルールを守ることができないなどの問題行動が多いことや10代での妊娠、薬物使用などが多いことも明らかになっています。また、自己制御力が弱く青年期に暴力的になる(いじめ加害者になる)ということも報告されています。

■「いじめ」加害者になる子の特徴
中学生におけるいじめ加害の要因を検討した結果、男女共にいじめ加害の経験をした子は、いじめ加害を経験していない子に比べて、有意に親への愛着得点が低く、学校全体への不満感と抑うつ傾向が高いことが報告されています。
いじめの中でも、ネットいじめの加害を行う子は、そうでない子に比べて、「親が自分の携帯電話、インターネットなどの利用状況に対する把握が低い」と考えている傾向が高く、ネットいじめと実際のいじめ両方を行う子どもでは、親への信頼感や親との情動的な繋がり度合いが有意に低いことが報告されています。
■愛着不形成がもたらす脳の異常
愛着がうまく形成できないことは、脳の発達にも影響することがわかっています。愛着が不安定で見捨てられ不安が高い人では、帯状回や側頭葉と呼ばれる場所の発達度合いが小さいと報告されています。また、幼少期に虐待などを経験した人でも、帯状回と海馬が小さくなっていることが報告されています。海馬や帯状回が小さくなっている状態は、戦争から帰還したPTSDを抱える兵士でも観測されています。
親子関係のあり方が、その後の人間関係や脳の発達まで含めた多岐に渡って影響をするということを、どこか心に留め日々子どもと向き合っていきたいものです。
----------
・Atzil S, Hendler T, Feldman R. Specifying the neurobiological basis of human attachment: brain, hormones, and behavior in synchronous and intrusive mothers. Neuropsychopharmacology. 36, 2603-15. 2011
・Bowlby, J. Attachment and Los Vol. 2 Separation. Basic Books, NY. 1973.
・Bretherton, I. Internal working models of attachment relationships as related to resilient coping. 1996.
・Chapple CL, Vaske J. Child neglect, social context, and educational outcomes: examining the moderating effects of school and neighborhood context. Violence Vict. 25, 470-485. 2010
・遠藤利彦 アタッチメント理論の現状と課題: 進化・発達・臨床の3つの視座から.子どもの虹情報研修センター紀要 No.8 23-38. 2010
・Fonagy P, and Luyten P.A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Dev Psychopathol. 21:1355-1381. 2009
・Benetti S et al, Attachment style, affective loss and gray matter volume: a voxel-based morphometry study. Hum Brain Mapp.(10):1482-9.2010
----------
----------
細田 千尋(ほそだ・ちひろ)
博士(医学)
東京大学大学院総合文化研究科研究員/科学技術振興機構さきがけ研究員/帝京大学医学部生理学講座助教。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科認知行動医学卒業後、英語学習による脳の可塑性研究を実施し、研究成果が多数のメディアに紹介。その研究をきっかけに、「目標達成できる人か?」を脳構造から判別するAIを作成し特許取得。現在は、プログラミング能力獲得と脳の関連性、 Virtual Realityを利用した学習法、恋愛と脳についても研究をしている。
----------
(博士(医学) 細田 千尋 写真=iStock.com)


















 、入浴によるヒートショックが大きな要因と指摘されています。
、入浴によるヒートショックが大きな要因と指摘されています。 画像:いらすとや
画像:いらすとや


 ※写真はイメージ
※写真はイメージ