先日(2021年7月18日)の大河ドラマ「青天を衝け」で大政奉還が描かれた。原市之進が暗殺された後、徳川慶喜が一人で悩んで大政奉還を決断したように描かれていた。薩摩の武力討幕をかわすための苦肉の策という筋書きであった。
「青天を衝け」の脚本はすばらしく、いつも感心して視聴しているが、これについては正しくない。渋沢栄一の編著『徳川慶喜公伝』(原著大正6年刊行)は、徳川慶喜が議会政治の開始を目指して大政奉還を行ったことを明らかにしている。同書によれば、慶喜が土佐藩の大政奉還建白書を受け入れた理由は、建白書に「上院に公卿・諸大名、下院に諸藩士を選補し、公論によりて事を行はば、王政復古の実を挙ぐるを得ん」とあるのを見て、それを大いに喜び、それが実現されるのであればと、腹心の板倉伊賀守と永井玄蕃頭と相談の上、決したとのことである(渋沢栄一『徳川慶喜公伝』4、平凡社東洋文庫、39~41頁) 。
渋沢栄一が『徳川慶喜公伝』を執筆するために慶喜本人に詳細に聞き取り調査を行った記録が『昔夢会筆記』であるが、それによれば慶喜本人は以下のように回想している。
「予が政権返上の意を決したるは早くよりの事なれど、さりとていかにして王政復古の実を挙ぐべきかということは成案なかりき。如何となれば、公卿・堂上の力にては事ゆかず、諸大名とても同様なり。さりとて諸藩士にてはまた治まるべしとも思われず、これ予が苦心のあるところなりしが、要するに、朝幕ともに有力者は下にありて上になければ、その下にある有力者の説によりて、百事公論に決せば可ならんと思いしかど、その方法に至りては、いまだ何等の定見なかりしなり。松平容堂の建白書出ずるに及び、そのうちに上院・下院の制を設くべしとあるを見て、これはいかにも良き考えなり、上院に公卿・諸大名、下院に諸藩士を選補し、公論によりて事を行わば、王政復古の実を挙ぐるを得べしと思い、これに勇気と自信とを得て、遂にこれを断行するに至りたり」 (『昔夢会筆記 ―徳川慶喜公回顧談』東洋文庫、270頁)。
すなわち、慶喜本人の談によれば、早くから大政奉還の意志を決めていたものの、公卿にも諸大名にも十分な人材はおらず、とても政権の受け皿にはなり得ないと躊躇していたと言うのだ。慶喜は、人材は上にはおらず下にいると考えていた。慶喜はまさに渋沢栄一の活躍などを見て、そう痛感していたのだろう。
そこに山内容堂の建白書が出て、上・下両院による議会政治が提言されているのを読み、はじめて「勇気と自信とを得て」、大政奉還を断行するに至ったというのである。もっとも慶喜の理解には若干の誤りがあり、土佐藩の大政奉還建白書には、下院議員の被選挙権は諸藩士のみではなく庶民にまで広げることが唱えられていた。慶喜は、下院は諸藩士のみに被選挙権が与えられると認識している。
いずれにしても慶喜は、議会政治の導入を前提として大政奉還に同意したのであった。その上で渋沢は、慶喜がこのように決断するに至った背景として、当時、徳川政権の側も含めて議会政治を開始する機運が高まっていたことを論証する。嘉永年間より議会政治を求める気運が次第に高まって、大政奉還に至ったのであった。渋沢は、土佐藩の大政奉還建白書の提出に先立つ公議政体論の系譜を、ペリー来航時の老中阿部正弘にまで始原を遡って紹介している。とりわけ、その系譜についての全体の記述の半分近くを赤松小三郎の議会政治論の紹介に充て、それを評価するのである。
すなわち、渋沢栄一は、赤松小三郎の議会政治建白書が、土佐の大政奉還建白書にまでつながっていると正しく認識していたのである。さて、なぜ渋沢栄一は赤松小三郎の建白書のことを知っていて、それを特筆したのか? はたして渋沢栄一と赤松小三郎に面識はあったのだろうか?
渋沢栄一が京都でパリ行きを命じられたのが、慶応2年11月、パリに旅立ったのは慶応3年1月。赤松小三郎が京都で開塾したのが慶応2年10月。わずかな1~2か月の短期間であるが、京都にいた時期が重なっている。
赤松小三郎は暗殺された原市之進や同じく慶喜側近の西周とは交友があり、慶喜とも面会している。このわずかの期間に渋沢とも会っていてもおかしくはない。あるいは、渋沢が直接小三郎と会っていなくとも、小三郎を知る慶喜家臣から、小三郎の建白書のことを聞かされていたのかも知れない。いずれにしても、幕末史の中に、小三郎の議会政治論を正しく位置づけようとしたのは、渋沢栄一の『徳川慶喜公伝』が初なのである。
「青天を衝け」の脚本はすばらしく、いつも感心して視聴しているが、これについては正しくない。渋沢栄一の編著『徳川慶喜公伝』(原著大正6年刊行)は、徳川慶喜が議会政治の開始を目指して大政奉還を行ったことを明らかにしている。同書によれば、慶喜が土佐藩の大政奉還建白書を受け入れた理由は、建白書に「上院に公卿・諸大名、下院に諸藩士を選補し、公論によりて事を行はば、王政復古の実を挙ぐるを得ん」とあるのを見て、それを大いに喜び、それが実現されるのであればと、腹心の板倉伊賀守と永井玄蕃頭と相談の上、決したとのことである(渋沢栄一『徳川慶喜公伝』4、平凡社東洋文庫、39~41頁) 。
渋沢栄一が『徳川慶喜公伝』を執筆するために慶喜本人に詳細に聞き取り調査を行った記録が『昔夢会筆記』であるが、それによれば慶喜本人は以下のように回想している。
「予が政権返上の意を決したるは早くよりの事なれど、さりとていかにして王政復古の実を挙ぐべきかということは成案なかりき。如何となれば、公卿・堂上の力にては事ゆかず、諸大名とても同様なり。さりとて諸藩士にてはまた治まるべしとも思われず、これ予が苦心のあるところなりしが、要するに、朝幕ともに有力者は下にありて上になければ、その下にある有力者の説によりて、百事公論に決せば可ならんと思いしかど、その方法に至りては、いまだ何等の定見なかりしなり。松平容堂の建白書出ずるに及び、そのうちに上院・下院の制を設くべしとあるを見て、これはいかにも良き考えなり、上院に公卿・諸大名、下院に諸藩士を選補し、公論によりて事を行わば、王政復古の実を挙ぐるを得べしと思い、これに勇気と自信とを得て、遂にこれを断行するに至りたり」 (『昔夢会筆記 ―徳川慶喜公回顧談』東洋文庫、270頁)。
すなわち、慶喜本人の談によれば、早くから大政奉還の意志を決めていたものの、公卿にも諸大名にも十分な人材はおらず、とても政権の受け皿にはなり得ないと躊躇していたと言うのだ。慶喜は、人材は上にはおらず下にいると考えていた。慶喜はまさに渋沢栄一の活躍などを見て、そう痛感していたのだろう。
そこに山内容堂の建白書が出て、上・下両院による議会政治が提言されているのを読み、はじめて「勇気と自信とを得て」、大政奉還を断行するに至ったというのである。もっとも慶喜の理解には若干の誤りがあり、土佐藩の大政奉還建白書には、下院議員の被選挙権は諸藩士のみではなく庶民にまで広げることが唱えられていた。慶喜は、下院は諸藩士のみに被選挙権が与えられると認識している。
いずれにしても慶喜は、議会政治の導入を前提として大政奉還に同意したのであった。その上で渋沢は、慶喜がこのように決断するに至った背景として、当時、徳川政権の側も含めて議会政治を開始する機運が高まっていたことを論証する。嘉永年間より議会政治を求める気運が次第に高まって、大政奉還に至ったのであった。渋沢は、土佐藩の大政奉還建白書の提出に先立つ公議政体論の系譜を、ペリー来航時の老中阿部正弘にまで始原を遡って紹介している。とりわけ、その系譜についての全体の記述の半分近くを赤松小三郎の議会政治論の紹介に充て、それを評価するのである。
すなわち、渋沢栄一は、赤松小三郎の議会政治建白書が、土佐の大政奉還建白書にまでつながっていると正しく認識していたのである。さて、なぜ渋沢栄一は赤松小三郎の建白書のことを知っていて、それを特筆したのか? はたして渋沢栄一と赤松小三郎に面識はあったのだろうか?
渋沢栄一が京都でパリ行きを命じられたのが、慶応2年11月、パリに旅立ったのは慶応3年1月。赤松小三郎が京都で開塾したのが慶応2年10月。わずかな1~2か月の短期間であるが、京都にいた時期が重なっている。
赤松小三郎は暗殺された原市之進や同じく慶喜側近の西周とは交友があり、慶喜とも面会している。このわずかの期間に渋沢とも会っていてもおかしくはない。あるいは、渋沢が直接小三郎と会っていなくとも、小三郎を知る慶喜家臣から、小三郎の建白書のことを聞かされていたのかも知れない。いずれにしても、幕末史の中に、小三郎の議会政治論を正しく位置づけようとしたのは、渋沢栄一の『徳川慶喜公伝』が初なのである。














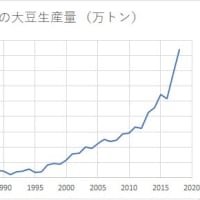

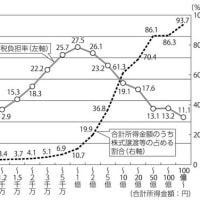



この間多忙でブログの更新もままならず、コメントへの反応もできずに失礼いたしました。
>経済という次元でのアプローチの可能性の話になるのだろうかと想像して
グローバル経済の見通しにもはや誰も楽観論は保持できず、政官財一体となった成長戦略としての石炭火力輸出も原発輸出も完全に生き詰まっています。さすがの日本経団連も白旗あげるしかなくなるだろうと拝察いたします。
文化思想の力でなかったとしても、環境危機と感染症でグローバル経済は路線転換を強いられています。あとは、その下部構造の変化を明るいものとするよう、そこにはやはり上部構造の役割が大きいだろうと思われます。
渋沢栄一の出自は一橋家臣であったそうですね。中村彰彦氏によれば渋沢栄一は慶喜の将軍就任に反対だったそうで、長州には心底で親和的だったと。どのような構想を抱いていたのでしょうか。持っていなかったのかもしれません。
https://keiei.proweb.jp/column/a037/86/1920/2698/
赤松小三郎建白と山内容堂建白の視野に対して徳川慶喜の視野は限られていたというご指摘はきわめて重要だと拝察します。渋沢栄一はこの相違を認識指摘しなかったわけですが、赤松小三郎は貧農と零細町人まで意識していたのではないかと期待します。
敗戦被占領期にいたるまで政治の構造変動は内外支配層のなかですすめられ、政党代議制と普通選挙による造り上げられた民意による現在までこれがつづいています。
変革するには選挙と政党によらなければならないわけしょうが、SNSまで含めてマスコミュニケーションに貫徹する支配と人心操作、投票集計の秘密主義を解くすべはないのでしょう。
がんばったアスリートの金メダルをカネメダルと読めば絶対的に市井で排撃されるように、文化思想アプローチは官民あげての媒体支配によってとうてい無理です。経済という次元でのアプローチの可能性の話になるのだろうかと想像して、上部構造下部構造論とどう異なるのか、首をひねっています。