.

・
・
・
・
★

★
・
・
・
・







 ・・・
・・・

 2012年、途中で投げ出したままだった「ソロモンの偽証」
2012年、途中で投げ出したままだった「ソロモンの偽証」 「ソロモンの偽証前篇」を見終えたあと、
「ソロモンの偽証前篇」を見終えたあと、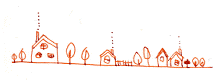




 ・・・
・・・

 「柘榴坂の仇討」は、この短編集「五郎治殿御始末」(浅田二郎著)の中の一篇が原作となっています。
「柘榴坂の仇討」は、この短編集「五郎治殿御始末」(浅田二郎著)の中の一篇が原作となっています。


 ・・
・・

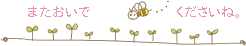
 2011年10月20日記。)へと続く、序章的な作品です。
2011年10月20日記。)へと続く、序章的な作品です。


 マスカレードイヴのサイト
マスカレードイヴのサイト 】
】 ・・
・・

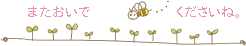
 本日(6月2日)九州北部、梅雨入りしました。
本日(6月2日)九州北部、梅雨入りしました。


 6月に入りました。今月もどうぞよろしくお願いします。
6月に入りました。今月もどうぞよろしくお願いします。 ・・
・・

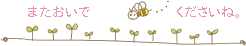





 ・・
・・

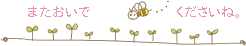


 ・・
・・

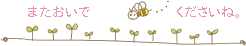

 七十二候の【桃始笑】ももはじめてさく(3月11日~15日)を、迎えています。
七十二候の【桃始笑】ももはじめてさく(3月11日~15日)を、迎えています。
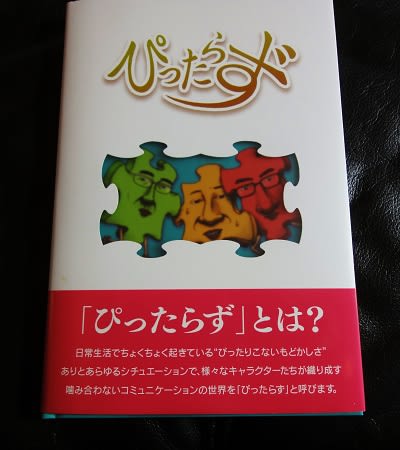
 ぴったらず公式HP
ぴったらず公式HP


 ✿✿
✿✿

 「銀貨三十枚でイエスを売った裏切り者はユダだが、ペテロも一度はイエスを裏切っている。役人たちと群衆に捕えられたイエスのもとに、一人最後まで留まった彼も、夜通しの激しい追及にとうとう負けて、自分はイエスの弟子ではないと誓う
「銀貨三十枚でイエスを売った裏切り者はユダだが、ペテロも一度はイエスを裏切っている。役人たちと群衆に捕えられたイエスのもとに、一人最後まで留まった彼も、夜通しの激しい追及にとうとう負けて、自分はイエスの弟子ではないと誓う 『聖ペテロの否認』(レンブランド作)ネット画像
『聖ペテロの否認』(レンブランド作)ネット画像
 「『誰か』『名もなき毒』に続く杉村三郎シリーズ、待望の第3弾。
「『誰か』『名もなき毒』に続く杉村三郎シリーズ、待望の第3弾。
 ネット画像
ネット画像 「滅びの山(Mount Doom)」は、J・R・R・トールキンの中つ国を舞台とした小説、『指輪物語』及び『シルマリルの物語』に登場する火山。
「滅びの山(Mount Doom)」は、J・R・R・トールキンの中つ国を舞台とした小説、『指輪物語』及び『シルマリルの物語』に登場する火山。
 今日はこの辺で
今日はこの辺で



 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 ネット画像
ネット画像 ネット画像
ネット画像

 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 ネット画像
ネット画像 ・・・城は大名や藩主の政治上の拠点であり、居住の場所であり、攻守の要であり、城下や近隣の人々の命や生活を左右する、まさに命運が決せられる場所であった。城を取り合う、すなわち領地を取り合う戦で勢力図は書き換わり、歴史の流れが決まってきた。城を中心に町が出来、政(まつりごと)が行われ、発展してきたのだ。江戸の太平の時代においても、城は様々な意味で藩の中心であった。現在の日本の県庁所在地、47のうち実に30あまりの都市が元々城下町であった都市であり、現在でも(戦後再建されたものも含めて)城が町の中心にある場所も多く、城は市民達の心の拠り所、シンボルとして、散策や集いの場として愛されている。
・・・城は大名や藩主の政治上の拠点であり、居住の場所であり、攻守の要であり、城下や近隣の人々の命や生活を左右する、まさに命運が決せられる場所であった。城を取り合う、すなわち領地を取り合う戦で勢力図は書き換わり、歴史の流れが決まってきた。城を中心に町が出来、政(まつりごと)が行われ、発展してきたのだ。江戸の太平の時代においても、城は様々な意味で藩の中心であった。現在の日本の県庁所在地、47のうち実に30あまりの都市が元々城下町であった都市であり、現在でも(戦後再建されたものも含めて)城が町の中心にある場所も多く、城は市民達の心の拠り所、シンボルとして、散策や集いの場として愛されている。 ・・・かつて日本には二万五千以上もの城が存在したと言われる。実際にはただ柵で囲われただけの砦のようなものもあり、文書に残っているのみでその存在が証されたのではないものも含まれるが、それでも相当数存在していたことは確かだ。しかし、数多くの戦や藩主の転封の度に廃城になったり破却されたりとその数は次第に減っていき、江戸後期にはその総数およそ200。さらにその後の明治維新の廃城令や戦争、火災、天災を免れて現在もその姿を残しているのは12城しかない。それ以外の現在見られる城は戦後新たに再建復興されたもの。古くに廃城になったものは、現在では打ち捨てさられ忘れられ、その城跡すらもただの野山と見分けがつかないようなものも多いのだ。天守や城郭が往時のまま現存しているのは丸岡城、犬山城、松本城、彦根城、松江城、高梁城(備中松山城)、丸亀城、姫路城、松山城、高知城、宇和島城、弘前城の12城のみだ。
・・・かつて日本には二万五千以上もの城が存在したと言われる。実際にはただ柵で囲われただけの砦のようなものもあり、文書に残っているのみでその存在が証されたのではないものも含まれるが、それでも相当数存在していたことは確かだ。しかし、数多くの戦や藩主の転封の度に廃城になったり破却されたりとその数は次第に減っていき、江戸後期にはその総数およそ200。さらにその後の明治維新の廃城令や戦争、火災、天災を免れて現在もその姿を残しているのは12城しかない。それ以外の現在見られる城は戦後新たに再建復興されたもの。古くに廃城になったものは、現在では打ち捨てさられ忘れられ、その城跡すらもただの野山と見分けがつかないようなものも多いのだ。天守や城郭が往時のまま現存しているのは丸岡城、犬山城、松本城、彦根城、松江城、高梁城(備中松山城)、丸亀城、姫路城、松山城、高知城、宇和島城、弘前城の12城のみだ。 ・・・城は大きく分けて竹田城や安土城に代表される山城と名古屋城などに代表される平城がある。戦乱の世であった時代、戦略的、防衛的な観点からその多くは地形を利用して山に建てられた。その後江戸時代になり、戦略的な意味合いが薄れるとその多くは平地に作られる平城となり、防衛的な特色より、立派な天守閣のある権力示威的な色合いが濃くなる。広大な縄張り内に数多くの櫓、豪壮絢爛な天守閣、そして城主が普段暮らす場所である本丸御殿など、技巧と贅を尽くした華美な建築物となってゆく。しかし、その建設の為の費用や労働力を捻出するために過度な年貢や労役を藩内の民に課したために時に一揆などが起こったのもまた事実だ。
・・・城は大きく分けて竹田城や安土城に代表される山城と名古屋城などに代表される平城がある。戦乱の世であった時代、戦略的、防衛的な観点からその多くは地形を利用して山に建てられた。その後江戸時代になり、戦略的な意味合いが薄れるとその多くは平地に作られる平城となり、防衛的な特色より、立派な天守閣のある権力示威的な色合いが濃くなる。広大な縄張り内に数多くの櫓、豪壮絢爛な天守閣、そして城主が普段暮らす場所である本丸御殿など、技巧と贅を尽くした華美な建築物となってゆく。しかし、その建設の為の費用や労働力を捻出するために過度な年貢や労役を藩内の民に課したために時に一揆などが起こったのもまた事実だ。 ・・・「土偏」に「成る」と書く「城」という漢字には元々「都市の周囲に防御の為に築いた壁」という意味のほかに「都市・町・国」そのものを表す意味がある。まさに「城」を中心として、「土」=地面が「国」や「町」に「成る」のだ。戦国時代は防衛防御を重んじたため、戦をする上で重要な、戦いに有意義な設備が各所に作られ、沢山の井戸も掘られた。設備とは例えば物見櫓や狭間(さま)と呼ばれる鉄砲(矢)穴で、外部からの攻撃に備え、守りを固めるためのもの。井戸は水確保のためだ。籠城の際、外部から引いている水にのみ頼ることは、その水に毒物などを入れられた場合に城内が混乱に陥る危険性がある。それを考慮して、外部とつながりのない水源を確保したのだ。
・・・「土偏」に「成る」と書く「城」という漢字には元々「都市の周囲に防御の為に築いた壁」という意味のほかに「都市・町・国」そのものを表す意味がある。まさに「城」を中心として、「土」=地面が「国」や「町」に「成る」のだ。戦国時代は防衛防御を重んじたため、戦をする上で重要な、戦いに有意義な設備が各所に作られ、沢山の井戸も掘られた。設備とは例えば物見櫓や狭間(さま)と呼ばれる鉄砲(矢)穴で、外部からの攻撃に備え、守りを固めるためのもの。井戸は水確保のためだ。籠城の際、外部から引いている水にのみ頼ることは、その水に毒物などを入れられた場合に城内が混乱に陥る危険性がある。それを考慮して、外部とつながりのない水源を確保したのだ。 ・・・「城」は戦略上の重要な拠点であり、防衛の上でも要であった。城を守ることは国を守ることと同義であり、それはすなわち、戦国時代には藩内の各人の命が城の存続と共にあったということを意味するのである。そのようなわけで有事の際には武将はおろか、一兵卒、農民や町民に至るまで、城内に暮らし、敵の襲来に備えたのだ。例えば北条氏の小田原城籠城であり、例えば吉川氏の鳥取城籠城である。
・・・「城」は戦略上の重要な拠点であり、防衛の上でも要であった。城を守ることは国を守ることと同義であり、それはすなわち、戦国時代には藩内の各人の命が城の存続と共にあったということを意味するのである。そのようなわけで有事の際には武将はおろか、一兵卒、農民や町民に至るまで、城内に暮らし、敵の襲来に備えたのだ。例えば北条氏の小田原城籠城であり、例えば吉川氏の鳥取城籠城である。 ・・・ところが天下統一の後、戦略的な目的を失った城は、今度はそこに封ぜられた大名のその藩の民に対する権力誇示の意味合いを持つようになり、また城下町内を統治する上での拠点、政所としての役割を担うようになった。例えば太田道灌が作った江戸城に入城した家康とその後の将軍達は、江戸城を政治の中心本拠地として位置づけた。それはすなわち、江戸「城」が江戸という町の中心と「成った」ことを意味し、それと同時に名実共に日本の中心と「成った」ことも意味したのだ。
・・・ところが天下統一の後、戦略的な目的を失った城は、今度はそこに封ぜられた大名のその藩の民に対する権力誇示の意味合いを持つようになり、また城下町内を統治する上での拠点、政所としての役割を担うようになった。例えば太田道灌が作った江戸城に入城した家康とその後の将軍達は、江戸城を政治の中心本拠地として位置づけた。それはすなわち、江戸「城」が江戸という町の中心と「成った」ことを意味し、それと同時に名実共に日本の中心と「成った」ことも意味したのだ。 ・・・各藩にあった各城もまたしかりである。それぞれの藩の中心、地方の中心としての役割を城は担うようになり、城を中心として町も整備されていく。もはや戦争の上での拠点ではなく、各人の生活の上での拠点、政治上の中心、象徴となっていったのだ。要塞、要害としての城から、政務の上での中心地としての城へと変化していったのである。しかし中央政権「徳川家」への遠慮や一国一城令のため、地方の大名達は城の新築増築改築をはばかる様になった。一国城令で、新築はおろか修理補修も無断では出来ないことになり、それによって城の数は減少の一途をたどっていくことになるのである。
・・・各藩にあった各城もまたしかりである。それぞれの藩の中心、地方の中心としての役割を城は担うようになり、城を中心として町も整備されていく。もはや戦争の上での拠点ではなく、各人の生活の上での拠点、政治上の中心、象徴となっていったのだ。要塞、要害としての城から、政務の上での中心地としての城へと変化していったのである。しかし中央政権「徳川家」への遠慮や一国一城令のため、地方の大名達は城の新築増築改築をはばかる様になった。一国城令で、新築はおろか修理補修も無断では出来ないことになり、それによって城の数は減少の一途をたどっていくことになるのである。 日本の城より。
日本の城より。 ネット画像
ネット画像
 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 ネット画像
ネット画像 お金があって客もはいるが、「パの巨人」呼ばわりは嫌だ
お金があって客もはいるが、「パの巨人」呼ばわりは嫌だ 今でもライオンズだけには負けたくないと思う
今でもライオンズだけには負けたくないと思う プレーオフなんて大嫌いだ
プレーオフなんて大嫌いだ ムネリンがいつかホークスに帰ってくると信じている
ムネリンがいつかホークスに帰ってくると信じている ハリーくんが突然バック転できるようになって驚いた
ハリーくんが突然バック転できるようになって驚いた 7回の守りが長いとジェット風船を持つがしびれる
7回の守りが長いとジェット風船を持つがしびれる ひそかに千葉ロッテの応援にあこがれている
ひそかに千葉ロッテの応援にあこがれている 博多の年輩者は「ダイエー」といいがち
博多の年輩者は「ダイエー」といいがち 「森福の11球」は美しすぎるドラマだ
「森福の11球」は美しすぎるドラマだ 打席登場曲のアカペライントロが終わらないうちに打つ本多
打席登場曲のアカペライントロが終わらないうちに打つ本多 「あらがき」じゃなくて「あらかき」、「たかだ」じゃなくて「たかた」
「あらがき」じゃなくて「あらかき」、「たかだ」じゃなくて「たかた」 毎年斬新なスローガンに度肝を抜かれる
毎年斬新なスローガンに度肝を抜かれる ネット画像
ネット画像 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 ネット画像
ネット画像 ・・独り暮らしをしていた老人・秋山周治が何者かに殺された。遺体の第一発見者は孫娘の梨乃。梨乃は祖父の死後、庭から消えた黄色い花のことが気にかかり、ブログにアップする。ブログを見て近づいてきたのが、警察庁に勤務する蒲生要介。その弟・蒼太と知り合った梨乃は、蒼太とともに、事件の真相と黄色い花の謎解明に向けて動き出す。西荻窪署の刑事・早瀬らも、事件を追うが、そこには別の思いもあった。
・・独り暮らしをしていた老人・秋山周治が何者かに殺された。遺体の第一発見者は孫娘の梨乃。梨乃は祖父の死後、庭から消えた黄色い花のことが気にかかり、ブログにアップする。ブログを見て近づいてきたのが、警察庁に勤務する蒲生要介。その弟・蒼太と知り合った梨乃は、蒼太とともに、事件の真相と黄色い花の謎解明に向けて動き出す。西荻窪署の刑事・早瀬らも、事件を追うが、そこには別の思いもあった。
 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 ・・・・しってるよ キミがいつもいっしょうけんめいなコト しってるよ キミがずっとガマンしてたコト そしてちゃんとしってる キミはホントは だれよりもやさしくて つよいココロをもっているコト・・・・
・・・・しってるよ キミがいつもいっしょうけんめいなコト しってるよ キミがずっとガマンしてたコト そしてちゃんとしってる キミはホントは だれよりもやさしくて つよいココロをもっているコト・・・・ ネット画像
ネット画像 ・・・・まっくらになってはじめて みえる光もあるんだよ
・・・・まっくらになってはじめて みえる光もあるんだよ ネット画像
ネット画像
 ・・・・だいじょうぶ いったりきたりもするけれど キミはちゃんとすすんでる
・・・・だいじょうぶ いったりきたりもするけれど キミはちゃんとすすんでる 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 はなこころ
はなこころ です。
です。