■ 「マグロ経済」 ■
本日のテーマは「マグロ経済」。
「マクロ経済」ではありません。
最近の市場動向に?という感覚を覚える方は多いはず。
トランプラリー以降、市場は〇〇危機が意識されると少し下げ、危機が回避される直前・直後にスルリと戻す事を繰り返しています。
過剰流動性を抱えた市場は、最初のうちこそは「少し触れられる」だけで過剰に反応していましたが、だんだんと「不感症」になり、最近はちょっとやそっとでは動じない「マグロ」になってしまいました。
■ 「市場との対話」という名の「予言の自己実現」 ■
日本のバブル崩壊や、リーマンショックを経験した事で、世界は「一本調子のバブル」をなかなか作る事が出来ませんが、一方で「マグロ化」した市場は「下がり難い」。その状況の中でリスクは拡大し続けています。
既に債権市場は金利上昇局面で危険度が高まっているので、逃げ出した資金が株式市場に流入しています。これがトランプラリー以降の株高の原因ですが、人々はポジティブな原因をこじつけて株価上昇を正当化し、自己暗示に掛けている。
この「変な均衡」を崩すのはやはりFRBの利上げですが、ここにも「市場との対話」という自己暗示が働いています。市場は極端な危機が顕在化するまでは「予言の自己実現」によってある程度の平成を保つ事が出来、FRBは市場をある程度コントロール出来る。
■ 「予言の自己実現」とは何か? ■
「予言の自己実現(自己成就)」は社会学者のマートンが提唱した考え方です。
「自己成就的予言(self-fulfiling prophecy)とは、最初の誤った状況の規定が新しい行動を呼び起こし、その行動が当初の誤った考えを真実なものとすることである。」
マートンは銀行の破たんを例に挙げています。
1) 銀行が破たんするという噂が立つ
2) 実際には銀行の経営は健全である
3) 人々は銀行が破たんすると思い込み預金を引き出しに殺到する
4) 結果、健全だった銀行が破たんする
5) 「銀行が破たんする」といった人々お誤った「予言」が現実の銀行を破たんさせた
実は「予言の自己実現」は悪い結果ばかりを招く訳ではありません。
1) 銀行が破たんする訳が無いと人々は考えている
2) 実際には信用創造によって成り立つ現在の金融システムは初めから破たんしている
3) 人々は「金融システムが最初から破たんしている」などとは考えるた事も無い
4) 結果、人々は預金を引き出してタンスに仕舞込む事は無い
5) 経済は継続する
■ FRBが用いる「予言の自己実現」のテクニック=「市場との対話」 ■
1) FRBは利上げに対するポジティブとネガティブな発信をバランス良くばら撒く
2) 利上げ前に利上げにポジティブな発言を増やす
3) 市場が利上げを予測してリスクの調整に入る
4) FRBは利上げ直前にネガティブとも取れる発言を流す
5) 市場は利上げが無い場合を警戒して、過剰なリスクヘッジを避ける
6) 結果として市場は全体的にはニュートラルな状態を保つ
「市場との対話」などとカッコイイ呼び名が着いていますが、実際は「利上げしちゃうぞー」「いや止めようかな」の繰り返しで、利上げ当日まで市場が極端なポジションを取らない様に揺さぶりを掛けているだけなのです。
個々の投資家レベルではリスクを取っているケースも多いのですが、全体としては相殺されてイーブンになる所がミソです。
■ 「ネガティブ・フィードバック」による「予言の自己実現」 ■
市場の調整原理はネガティブ・フィードバック(NFB)回路に似ています。NFB回路とはオーディオアンプの歪率改善に利用される技術です。
1) アンプの回路は入力信号を正確に増幅出来ない(歪の存在)
2) アンプの出力信号の少しの量を反転して入力に戻す(負帰還)
3) アンプが生じるであろう歪みを打ち消す信号が負帰還
5) 入力信号は負帰還によって今後生じるであろう歪みを予め補完される
市場でNFBの働きをしているのが「リスクヘッジ」です。将来の変動に対して「逆張り」で変動を抑え込む働きを持ちます。
NFBはあまり大きなゲインで掛けるとアンプの出力が低下します。逆位相の信号が本来の入力信号を相殺してしまうからです。同様に過剰なリスクヘッジは利益を相殺してしまいます。
現在の市場はまさにNFBの掛かり過ぎたアンプの様な状態で、ブレグジットやトランプの登場と言ったネガティブ要因(歪)に耐性があると同時に、利益(ゲイン)が得にくい状況にあるのでは無いかと思います。
■ 調整を誤ると自己崩壊(発振)するNFB回廊 ■
NFB回路は単純で非常に効果的な歪低減回路です。
しかし、時としてNFB回路はアンプを破壊する事があります。
1) NFB回路からの信号は通常入力信号と逆相
2) 回路の設計によっては一部周波数で位相の回転が起こる
3) NFB回路の信号に正相の信号が混入する
4) 正相信号はNFB回路によって増幅を繰り返す
5) ついには回路を破壊する
発振はカラオケでも度々発生します。「ハウリング」です。
1) マイク(入力信号)がスピーカーの音を拾う
2) マイクが拾った音がアンプで増幅されてスピーカーから音として出力される
3) マイクが増幅された音を拾う・・・
4) この繰り返しが起きる事により、ある音が増幅されし続けてハウリングが起きる
市場における「発振」や「ハウリング」は、「市場のパニック」や「売りが売りを呼び」などという状況に相当します。
現在の市場は「ヘッジ疲れ」しているとも言われ、大きな危機が発生するかも知れない状況で本来積みあがるはずのポジションが減少しているとの分析もあります。市場参加者が最近感じている「違和感」の原因は、リスクヘッジの弱まりを反映させたものかも知れません。あまりにリスクヘッジを効かせると儲からないからヘッジが弱まって来たのです。
この様な市場の「回路乗数」の変化が、ある時、悪いポジティブフィードバックを起こすと、市場は「発振」を起こし、それを切っ掛けに「パニック」が発生し、市場は崩壊を迎えます。
「マグロ経済」は市場が不感症になる事で、市場の安全装置を知らず知らずの内に弱めてしまうのでしょう。
本日のテーマは「マグロ経済」。
「マクロ経済」ではありません。
最近の市場動向に?という感覚を覚える方は多いはず。
トランプラリー以降、市場は〇〇危機が意識されると少し下げ、危機が回避される直前・直後にスルリと戻す事を繰り返しています。
過剰流動性を抱えた市場は、最初のうちこそは「少し触れられる」だけで過剰に反応していましたが、だんだんと「不感症」になり、最近はちょっとやそっとでは動じない「マグロ」になってしまいました。
■ 「市場との対話」という名の「予言の自己実現」 ■
日本のバブル崩壊や、リーマンショックを経験した事で、世界は「一本調子のバブル」をなかなか作る事が出来ませんが、一方で「マグロ化」した市場は「下がり難い」。その状況の中でリスクは拡大し続けています。
既に債権市場は金利上昇局面で危険度が高まっているので、逃げ出した資金が株式市場に流入しています。これがトランプラリー以降の株高の原因ですが、人々はポジティブな原因をこじつけて株価上昇を正当化し、自己暗示に掛けている。
この「変な均衡」を崩すのはやはりFRBの利上げですが、ここにも「市場との対話」という自己暗示が働いています。市場は極端な危機が顕在化するまでは「予言の自己実現」によってある程度の平成を保つ事が出来、FRBは市場をある程度コントロール出来る。
■ 「予言の自己実現」とは何か? ■
「予言の自己実現(自己成就)」は社会学者のマートンが提唱した考え方です。
「自己成就的予言(self-fulfiling prophecy)とは、最初の誤った状況の規定が新しい行動を呼び起こし、その行動が当初の誤った考えを真実なものとすることである。」
マートンは銀行の破たんを例に挙げています。
1) 銀行が破たんするという噂が立つ
2) 実際には銀行の経営は健全である
3) 人々は銀行が破たんすると思い込み預金を引き出しに殺到する
4) 結果、健全だった銀行が破たんする
5) 「銀行が破たんする」といった人々お誤った「予言」が現実の銀行を破たんさせた
実は「予言の自己実現」は悪い結果ばかりを招く訳ではありません。
1) 銀行が破たんする訳が無いと人々は考えている
2) 実際には信用創造によって成り立つ現在の金融システムは初めから破たんしている
3) 人々は「金融システムが最初から破たんしている」などとは考えるた事も無い
4) 結果、人々は預金を引き出してタンスに仕舞込む事は無い
5) 経済は継続する
■ FRBが用いる「予言の自己実現」のテクニック=「市場との対話」 ■
1) FRBは利上げに対するポジティブとネガティブな発信をバランス良くばら撒く
2) 利上げ前に利上げにポジティブな発言を増やす
3) 市場が利上げを予測してリスクの調整に入る
4) FRBは利上げ直前にネガティブとも取れる発言を流す
5) 市場は利上げが無い場合を警戒して、過剰なリスクヘッジを避ける
6) 結果として市場は全体的にはニュートラルな状態を保つ
「市場との対話」などとカッコイイ呼び名が着いていますが、実際は「利上げしちゃうぞー」「いや止めようかな」の繰り返しで、利上げ当日まで市場が極端なポジションを取らない様に揺さぶりを掛けているだけなのです。
個々の投資家レベルではリスクを取っているケースも多いのですが、全体としては相殺されてイーブンになる所がミソです。
■ 「ネガティブ・フィードバック」による「予言の自己実現」 ■
市場の調整原理はネガティブ・フィードバック(NFB)回路に似ています。NFB回路とはオーディオアンプの歪率改善に利用される技術です。
1) アンプの回路は入力信号を正確に増幅出来ない(歪の存在)
2) アンプの出力信号の少しの量を反転して入力に戻す(負帰還)
3) アンプが生じるであろう歪みを打ち消す信号が負帰還
5) 入力信号は負帰還によって今後生じるであろう歪みを予め補完される
市場でNFBの働きをしているのが「リスクヘッジ」です。将来の変動に対して「逆張り」で変動を抑え込む働きを持ちます。
NFBはあまり大きなゲインで掛けるとアンプの出力が低下します。逆位相の信号が本来の入力信号を相殺してしまうからです。同様に過剰なリスクヘッジは利益を相殺してしまいます。
現在の市場はまさにNFBの掛かり過ぎたアンプの様な状態で、ブレグジットやトランプの登場と言ったネガティブ要因(歪)に耐性があると同時に、利益(ゲイン)が得にくい状況にあるのでは無いかと思います。
■ 調整を誤ると自己崩壊(発振)するNFB回廊 ■
NFB回路は単純で非常に効果的な歪低減回路です。
しかし、時としてNFB回路はアンプを破壊する事があります。
1) NFB回路からの信号は通常入力信号と逆相
2) 回路の設計によっては一部周波数で位相の回転が起こる
3) NFB回路の信号に正相の信号が混入する
4) 正相信号はNFB回路によって増幅を繰り返す
5) ついには回路を破壊する
発振はカラオケでも度々発生します。「ハウリング」です。
1) マイク(入力信号)がスピーカーの音を拾う
2) マイクが拾った音がアンプで増幅されてスピーカーから音として出力される
3) マイクが増幅された音を拾う・・・
4) この繰り返しが起きる事により、ある音が増幅されし続けてハウリングが起きる
市場における「発振」や「ハウリング」は、「市場のパニック」や「売りが売りを呼び」などという状況に相当します。
現在の市場は「ヘッジ疲れ」しているとも言われ、大きな危機が発生するかも知れない状況で本来積みあがるはずのポジションが減少しているとの分析もあります。市場参加者が最近感じている「違和感」の原因は、リスクヘッジの弱まりを反映させたものかも知れません。あまりにリスクヘッジを効かせると儲からないからヘッジが弱まって来たのです。
この様な市場の「回路乗数」の変化が、ある時、悪いポジティブフィードバックを起こすと、市場は「発振」を起こし、それを切っ掛けに「パニック」が発生し、市場は崩壊を迎えます。
「マグロ経済」は市場が不感症になる事で、市場の安全装置を知らず知らずの内に弱めてしまうのでしょう。











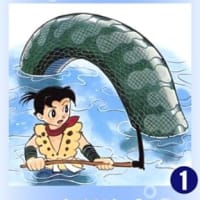
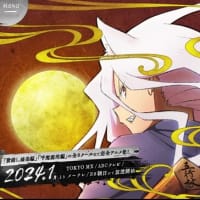







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます