■ 緊迫の現場 ■
東電の福島原発事故直後のTV会議の追加映像が公開されました。
事故当時の、現場と東電の緊迫したやり取りが記録されています。
不眠不休で事故処理に当たられた吉田所長を初め現場のスタッフの危機感が良く伝わります。
■ 長大な時間をダイジェストに編集している ■
以前、公開された東電の映像は、音声の無い部分が多く、
明らかに東電が事故当時の情報を隠蔽したものでした。
一方、今回の映像は、事故時の重大な局面でのダイジェスト版で、
音声もきちんと再生できるので、当時の状況が良く分かります。
しかし、都合の良い所だけを編集している様にも思え、
この映像だけから、当時の対応の状況を憶測するのは危険と思われます。
■ 官邸と現場の電話が繋がらないのは当然だ ■
映像冒頭は、現場の吉田所長が、
「官邸と電話が繋がらない」とぼやくシーンからスタートします。
このシーンを見て、多くの方が、事故当時、
官邸と現場のコミニュケーションが取れていなかったと推測するはずです。
「官邸は何をしていたんだ」と追求する方も出てくるでしょう。
しかし、良く考えて見てください。
東電本社と福島原発は、きっと専用回線で繋がれているはずです。
一方、福島原発と官邸の間は、一般回線ではないでしょうか?
地震直後、福島の通信インフラはダウンしていますから、
福島原発と官邸の電話が繋がり難い状況であった事は容易に想像出来ます。
さらには、官邸には被災地を初め、全国から様々な電話が殺到していたはずで、
官邸の電話回線の容量を超えていた事態も想定されます。
実際の所は知る由もありませんが、
当時、福島原発の現場からのみならず、全国から官邸への電話が繋がり難かった可能性があります。
ここら辺の事実が確認出来ない状態で、
「官邸に繋がらない」という映像だけで、
「官邸の怠慢」と決め付ける事は危険です。
いえ、むしろ、この音声を冒頭に持ってくる事で、
東電は明らかに責任を官邸に押し付ける情報操作をしていると考えられます。
■ ドライウェル・ベントできるなら直ぐやれ、こっちで全部責任は取るから ■
東電の映像では、3号機のドライベントは15日未明に実行されています。
映像で、「ドライウェル・ベントできるならすぐやれ。こっちで全部責任取るから」
とのやり取りがなされています。
この映像だけ見ていると、東電はドライベントを自主的に、かつ積極的に実施した様に見えます。
■ 福島原発事故を重大化させたのはウェット・ベントの遅れ? ■
東電がこのVTRの公表で、世間に印象付けたかったのは、
「東電はベントに積極的であった」というイメージでしょう。
原発事故直後も、「菅総理の現場視察によってウェット・ベントが遅れて水素爆発に繋がった」
との情報がさかんに飛び交っていました。
TVの報道も、ベントの遅れは「菅総理の視察と、政府の指示の遅れ」と指摘しています。
1)枝野官房長官の発言では12日の3時頃には、政府は東電にウェットベントの指示を出しています。
2)ベントしようとした所、電動バルブが開かなかった
3)東電は現場作業員が決死の覚悟で、手動でバルブを開放。
4) 現場の線量が高いので、一人数十秒のリレー作業でバルブ開放を試みる。
5) 東電が一号機のウェット・ベント用のバルブを手動で開放したのは12日午後
参考までに当時の読売新聞の記事です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110315-OYT1T00701.htm
官邸側は枝野発言にもある様に、菅首相が福島を視察するまでには
ウェットベントは完了しているものと考えていた。
しかし、実際には電磁バルブが作動せず、
高い線量に阻まれて、ベントの実行は12日午後まで実現しなかった。
これが事実なのでしょう。
東電は、この様な不手際を誤魔化す為に、
今回の追加映像をワザワザ編集して、
「官邸=悪者」
「東電=ベントに積極的」
という情報操作をしている様に思えます。
悪い事は全部、菅元総理に押し付けてしまえ作戦を実行しているのでしょう。
■ 1号機の圧力容器の損傷は12日午前1時50分には始まっていた ■
世間ではウェット・ベンチの遅れから炉心溶融が発生した様に思われています。
それで、菅総理の現場視察が事故を重大化させた様に情報操作がされています。
しかし、実際には1号機の圧力容器の破損は、
11日午前1時50分頃から起きていたと推測されています。
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120312-OYT1T01043.htm
■ 福島事故の最大の原因は、緊急炉心冷却装置の、『蒸気凝縮系機能』が外されていた事 ■
福島原発事故の押し問答で、どうしてベントのタイミングがこれ程重要視されるのでしょうか?
その原因は、福島第一原発の緊急炉心冷却装置から、
『蒸気凝縮系機能』と呼ばれる冷却系が外されていた事に起因します。
http://www.asyura2.com/12/genpatu26/msg/104.html
本来、緊急炉心冷却装置は、2段構えで事故時の炉心を冷却します。
1) 非常用電源を用いて圧力容器内の水を循環する
2) 圧力容器内の蒸気の圧力で、圧力容器内の水を循環する・・・『蒸気凝縮系機能』
福島原発事故では、津波で非常電源も失っています。
非常用バッテリーの容量内では、電源を用いる緊急炉心冷却装置が作動します。
しかし、全電源喪失後は、『蒸気凝縮系機能』だけが最後の望みとなります。
その『蒸気凝縮系機能』が福島原発では、事故の8年前に何と外されていました。
これには理由があります。
2001年に、静岡県の中部電力浜岡原発で原子炉停止事故が発生した際、
『蒸気凝縮系機能』の配管内に溜まった水素が爆発したのです。
そこで、東電は同型の福島原発の原子炉から、『蒸気凝縮系機能』を
2003年に政府に申請して、撤去していたのです。
『蒸気凝縮系機能』が存在しなくてもベントでその代替が利くというのが理由でした。
ところが、そのベントのタイミングが遅れ、
結局福島原発は1号機、2号機。3号機ともに水素爆発で破損してしまいました。
■ 『蒸気凝縮系機能』が生きていても、結局は同様の結果に至ったのでは ■
結果論になりますが、福島原発事故で炉心溶融を防ぐ唯一の方法は、
非常用バッテリーによる緊急炉心冷却装置が停止した段階で、
ウェット・ベンチを即時実行して、圧力容器内の圧力を下げ、
同時に圧力容器に、消防車ポンプ車などを用いて海水を注入しるしか無かった。
それも12日の未明までに、その対策が出来なければ、
結局、燃料棒は崩壊して、圧力容器底部に穴が開く事は防げませんでした。
燃料棒崩壊は12日未明よりも早期に発生していたでしょうから、
実際には、地震直後から、ウェットベンチの実行に移らなければ、
福島原発事故の圧力容器の破壊は防げませんでした。
しかし、停止直後の圧力容器内には、
半減期の短い、危険な核種が多数存在しますから、
結局は、周辺住民を退避させずにウェット・ベントを実行する事は不可能です。
さらには、電動のバルブも電源喪失で動作しなかった為、
手動でバルブを開放せざるを得ず、
この手動開放は、現場の放射線レベルが高い間は実行出来ません。
素人目には、水素爆発による原子炉建屋の損壊が重大危機の様に写りますが、
実際には圧力容器の底が損傷した時点で、原子炉は使用不能となります。
燃料棒が崩壊した時点で、ウェットベンチを実行しても遅すぎるのです。
官邸と東電の間に情報の齟齬が無くとも、
事故発生直後に10Km圏内の避難を実行し、
同時にウェットベントと、圧力容器への注水を実行しなければ、
福島原発事故は、結局は現在の状況に至る事は不可避だったと言えます。
■ 原発を再稼動する前にやるべき事 ■
政府と関電は、夏場の大規模停電を回避する為に
住民の反対を押し切って、大飯発電所の原子炉を稼動させました。
しかし、その前に政府と電力会社は事故が再発した場合の対策を見直したのでしょうか?
福島原発事故の教訓を生かすならば、全電源喪失を想定した次の様な対策が必要でしょう。
1) シリアス事故発生と同時に10Km圏内の強制避難を即時実行
2) 電源喪失の有無に関わらず、ウェットベンチと強制注水の準備開始
4) 非常用発電機の燃料残量が少なくなった時点で、風下方向の住民を広範囲に避難させる
5) 非常用発電機の電源が喪失し、非常用バッテリーも容量が無くなったら、即時ウェットベンチを実行し、炉心にポンプ車などで強制注水する。
6) 復水器は電源喪失で機能しないので、緊急のプールに炉心冷却排水をプールする
7) 上記作業と平行して電源の回復に努める
■ 再循環系の配管が破断していれば、電源が回復しても冷却されない ■
ここで問題になるのが、圧力容器と復水器を繋ぐ配管が、
地震によって破断されているかどうかです。
ここが破断していれば、電源が回復しても炉心の冷却は復旧しません。
■ 炉心停止直後の強制ベンチと、廃炉覚悟でしばらく封じ込めを持続するのでどちらが安全か? ■
原子炉停止直後の危険な核種が大量に存在する圧力容器内のガスを
ウェット・ベンチで外部に排出するリスクと、
圧力容器を犠牲にしても、危険な核種が減少する時間を稼ぐリスクの科学的比較です。
もし、早期ベントの方が危険であるとするならば、
福島第一原発は、後手後手に回ったとは言え、
結果的には東電以外の地元被害を最小化したとも言えます。
■ 軽水炉で容易に再臨界が発生しない事は、今後の事故対策の方向性を換える可能性がある ■
福島原発事故は私達に様々な事を教えてくれました。
万全を期していると言われた原子炉の事故対策の脆弱性に多くの人が注目しています。
一方で専門家達は、軽水炉が制御不能に陥っても、
意外なまでに、大規模な再臨界が発生しない事に注目している事でしょう。
軽水炉では、事故時に予期していなかったフェールセーフ機能が働き、
再臨界が未然に防がれる事は、今後の原子炉開発や事故対策に大きな変換をもたらすかもしれません。
例えば、再臨界の可能性が低いのであれば、
事故時に圧力容器から水を抜いて、格納容器を水で満たし、
水蒸気の発生を抑えながら、燃料溶融物を徐々に冷却する方法も有効かも知れません。
尤も圧力容器底部に制御棒の貫通穴があるマーク1型では不可能な方法かも知れませんが・・。
■ 人間は失敗から学ぶ ■
人間は失敗から多くの事を学びます。
原子力発電所の事故は、制御不能に陥る可能性がある事。
危機に際して、政府も行政も電力会社も、あまり役立たない事。
ここら辺が今回の事故が残した「負の教訓」です
一方、今後研究が進めば、こんな「正の教訓」も生まれるかも知れません。
軽水炉ではちょっとやそっとでは再臨界が発生しない事。
低線量率被曝では、顕著な健康被害が発生しない事。
私達は、科学の失敗から何を学び、どんな選択をするのでしょうか?
その選択次第によっては、さらに新たな教訓を学ぶ事となるのかも知れません。
それは・・・
いずれにしても、ベントのタイミングに問題が矮小化されがちな福島原発事故ですが、
GEのマーク1の構造的欠陥も含め、もう一度、冷静に事故を振り返るべきでは無いでしょうか?











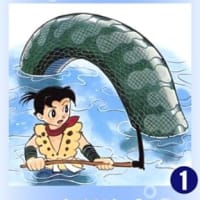
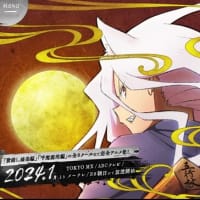







では”生”を垂れ流す事が良い事なのかどうなのか・・・。
他言伝聞を疑って、自分が見たものだけを信じて世界を狭くする
のも一計ですが、それもまたかなりシンドイでしょうね。
真実は闇の中ですが、どうも、菅さんを悪者にして、丸く収めようとしている様な気がします・・。
既に原発は私企業である電力会社が運用するには、事故時の賠償リスクが大きすぎる存在になっています。枝野氏が発表した様に、全ての原発を国有化し、賠償は国家が責任を持って行う必要があります。これは、事故直後から、池田信夫氏が指摘していた事です。
このまま、稼動しない原発を保有しているだけで、大幅な電力料金の値上げが無ければ、電力各社は3年後には債務超過になると言われています。
スケープゴートは必要ですもんね。是だけ言われて、自意識過剰な
彼の人が何も言わない(何言ってるか分からんですが^^;)のは、
それなりに裏で飴を貰ってるんでしょうね。
人力さんは菅さんをえらい持ち上げておられますが〝最高責任者”
として常識的な判断で常識的な指令をしたまでで、むしろそれら
指令を実行させれなかったた統率力無かった事が、問題に
なら無いでしょうか?。
私も何らかの手打ちがあったと思っています。
菅さんは、予備自衛官の投入など、防衛省も二の足を踏む対応を、迅速に決めており、同じ社会党出身の村山首相の阪神淡路大震災の対応に比べれば、雲泥の差があります。(自衛隊に対する意識も大きく変化しましたが)
本来、国民一丸となって、危機に立ち向かうべき時に、新聞やメディアが政府や首相の揚げ足ばかりを取る・・・。
この異常性に気付かずに、それを正義と勘違いしているメディアに携わる人々は、人間としての大切な何かを無くしている様に私には思えます。
豊田商事の事件の時もそうですが、目の前で人殺害されるのを阻止せずに、カメラを回し続けるのが彼らの習性です。他社に遅れを取るまいという競争意識が、結局、叩きやすい者を各社で一斉に叩くという、日本らしいイジメの構造として現われるのでしょう。
逆に言えば、当時の菅氏は「叩いて良い」という、お墨付きがあったとも言えます。