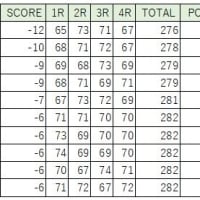現代の歌舞伎や日本舞踊の始まりは慶長年間(1596年~1615年)に、出雲阿国(いずものおくに)が始めた「歌舞伎踊り」が源流だといわれる。そしてそのもとになったのは1500年代中頃より始まった大衆芸能の「ややこ踊り」だという。「ややこ踊り」が古い文献に登場するのは「御湯殿上日記」という御所に仕える女官達によって書き継がれた日記が最初で、天正9年(1581)の条に初めて「ややこおとり」という言葉が登場する。そして奈良興福寺の塔頭多聞院の僧侶らによって書き継がれた「多聞院日記」の天正10年(1582)の条に「加賀国八歳十一歳の童ヤヤコヲトリ」と具体的な記載が出てくる。その「国」という11歳の少女が幼い頃の出雲阿国だとされている。その後もいくつかの文献にその名が登場し、出雲阿国が慶長8年(1603年)春に北野天満宮で勧進興行を行って一躍スターになると「かぶき踊り」と呼ばれるようになるのである。
「ややこ踊り」というのはその名のとおり「ややこ」すなわち稚児による踊りだったのだが、次第に年齢にかかわらず踊りの様式を指すようになっていったようだ。「ややこ踊り」は出雲阿国の出自が出雲大社の巫女だったと伝えられるように、もともと宗教的な意味を持つ舞、つまり神楽に近いものだったようだ。今日も日本各地にその名残りの稚児舞が伝統芸能として受け継がれている。
熊本の女流邦楽家で日本舞踊の指導者でもある中村花誠さんが、平成12年に立ち上げた舞踊団「わらべ」は、基本的に江戸後期以降の文化を受け継いだものであるから、安土桃山時代に生まれた「ややこ踊り」とは趣を異にするのは当然だが、中村花誠さんの発想は400年前に出雲阿国らが大衆の喝采を浴びた「ややこ踊り」の再現にほかならないと思うのである。
「ややこ踊り」というのはその名のとおり「ややこ」すなわち稚児による踊りだったのだが、次第に年齢にかかわらず踊りの様式を指すようになっていったようだ。「ややこ踊り」は出雲阿国の出自が出雲大社の巫女だったと伝えられるように、もともと宗教的な意味を持つ舞、つまり神楽に近いものだったようだ。今日も日本各地にその名残りの稚児舞が伝統芸能として受け継がれている。
熊本の女流邦楽家で日本舞踊の指導者でもある中村花誠さんが、平成12年に立ち上げた舞踊団「わらべ」は、基本的に江戸後期以降の文化を受け継いだものであるから、安土桃山時代に生まれた「ややこ踊り」とは趣を異にするのは当然だが、中村花誠さんの発想は400年前に出雲阿国らが大衆の喝采を浴びた「ややこ踊り」の再現にほかならないと思うのである。