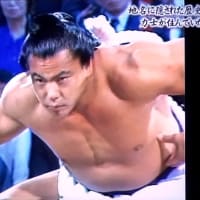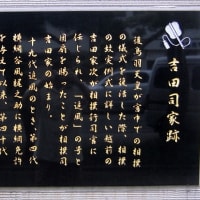今日はちょうど50年前に天草五橋が開通した日。当日だったかどうかは憶えていないが、学生だった僕は、東京の親戚の子を案内して初めて渡った。まだ、車も持ってなかったので、バスと徒歩で松島あたりまで行ったが、かなり疲れたことだけは憶えている。
天草五橋が開通してからの天草の発展は目を見張るものがあるが、それまでの天草がどういう地域だったかについて、父が備忘録の中に書き遺している。昭和10年に大矢野島の上村小学校への転勤が決まり、祖母はまるで父が島流しにでもなったかのように嘆き悲しんだという。熊本市に最も近い大矢野島でさえ、行き来するのは船しかない時代。今では阿蘇と並び熊本観光の代名詞となった天草も、当時はほとんどの地域が貧しい寒村だったのである。
同じ昭和10年に熊本市で開催された「新興熊本大博覧会」の公式ガイドブック「くまもと」には、天草について次のような解説が記されている。
切支丹殉教の歴史に色どられる天草は、熊本県の西南部に散在する、数十の群島と、大矢野島、上島、下島の三島から成っている。
この島は、上古天草国造を置かれたところで、早くから史上に見え、中世時代には、瀬戸、上津浦、大矢野、栖本、志岐の豪族が夫々領有していた。豊臣秀吉九州を平定した後も、各地に反旗を翻えす者があったので、小西、加藤の両氏これを征服し両氏の領有となった。
寛永14年の天草一揆、すなわち切支丹殉教の騒乱起るや、当時の領主、寺澤氏は、本島を没収せられ天領として、幕府直轄の下に、代官制度を布くことになった。明治維新、廃藩置県の後、一時長崎に属したことがあった。間もなく八代県に編入され、さらに明治6年熊本県に属し、爾来今日に及んでいる。現在熊本県の支庁を設け郡治を統括されている。
天草は、風光美を以てなり、肥後松島と称すべきところ、気候温和で、魚族が多く、保養地としても理想の地である。
総面積57方里37で、4町58ヶ村を有し、戸数35,200、人口195,400を擁している。
▼世界遺産「三角西港」の向こうに見える天草一号橋

▼天草の俗謡「牛深三下り」
「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」とハイヤ節で唄われるように、寄港する廻船の船乗りたちにとって絶海の楽園として知られた牛深湊の妓楼などで、ハイヤ節の前唄として唄われた。
唄:本條秀美 三味線:本條秀美社中 鳴物:中村花誠と花と誠の会 踊り:ザ・わらべ
天草五橋が開通してからの天草の発展は目を見張るものがあるが、それまでの天草がどういう地域だったかについて、父が備忘録の中に書き遺している。昭和10年に大矢野島の上村小学校への転勤が決まり、祖母はまるで父が島流しにでもなったかのように嘆き悲しんだという。熊本市に最も近い大矢野島でさえ、行き来するのは船しかない時代。今では阿蘇と並び熊本観光の代名詞となった天草も、当時はほとんどの地域が貧しい寒村だったのである。
同じ昭和10年に熊本市で開催された「新興熊本大博覧会」の公式ガイドブック「くまもと」には、天草について次のような解説が記されている。
切支丹殉教の歴史に色どられる天草は、熊本県の西南部に散在する、数十の群島と、大矢野島、上島、下島の三島から成っている。
この島は、上古天草国造を置かれたところで、早くから史上に見え、中世時代には、瀬戸、上津浦、大矢野、栖本、志岐の豪族が夫々領有していた。豊臣秀吉九州を平定した後も、各地に反旗を翻えす者があったので、小西、加藤の両氏これを征服し両氏の領有となった。
寛永14年の天草一揆、すなわち切支丹殉教の騒乱起るや、当時の領主、寺澤氏は、本島を没収せられ天領として、幕府直轄の下に、代官制度を布くことになった。明治維新、廃藩置県の後、一時長崎に属したことがあった。間もなく八代県に編入され、さらに明治6年熊本県に属し、爾来今日に及んでいる。現在熊本県の支庁を設け郡治を統括されている。
天草は、風光美を以てなり、肥後松島と称すべきところ、気候温和で、魚族が多く、保養地としても理想の地である。
総面積57方里37で、4町58ヶ村を有し、戸数35,200、人口195,400を擁している。
▼世界遺産「三角西港」の向こうに見える天草一号橋

▼天草の俗謡「牛深三下り」
「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」とハイヤ節で唄われるように、寄港する廻船の船乗りたちにとって絶海の楽園として知られた牛深湊の妓楼などで、ハイヤ節の前唄として唄われた。
唄:本條秀美 三味線:本條秀美社中 鳴物:中村花誠と花と誠の会 踊り:ザ・わらべ