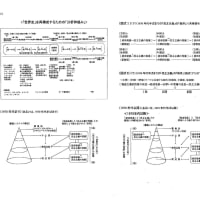№56私の語る「システム」論から、改めて「敗戦(終戦)記念日」前後における「あの戦争」の記憶を辿る日本人の集団的・自己欺瞞?の「演出」について再考するとき(続)
(最初に一言)
前回記事も、またまた以前に述べた話の焼き直しであったが、それでも私自身のボケ防止において、少しは役に立っているのは間違いない。今回記事も、その予防を兼ねて、前回記事の内容を再度、確認してみたい。
前回記事の強調点を、箇条書きでまとめると以下のようになる。
①私たちの「不戦の誓い」で祈念される「平和」は、自由や民主主義人権といった普遍的価値を構成するものである。
②そうした普遍的価値が提唱されたのはいわゆるフランス革命に代表される市民革命においてである。
③普遍的価値は、ただいくらその価値や価値観が素晴らしいと礼賛しても、それが現実に実現されないのならば、まさに絵に描いた餅でしかない。
④普遍的価値を現実に実現する歩みである普遍主義を考察するとき、それは大きく二つに分類されていた、と私はみている。
⑤その一つは、いわゆる「正常な発展」を辿ったとされる諸国であるが、これは先の市民革命を経験した英・米・仏・蘭に代表される。
⑥これに対して、「不正常な発展」を辿ったとされる諸国がある。そこには、戦前の独・伊・日が含まれている。
⑦前回記事でも少し触れたのだが、どうして⑤⑥のように、正常と不正常の違いが生じるのか。これまでの知見に従えば、その違いは、普遍的価値を前提として、あるいはそれを尊重・重視して、共同体が、その際それは主権国家を前提とした国民国家とされるのだが、国家の舵取りを担ったことが大きな要因とされる。
⑧これに対して、不正常な発展を辿った共同体は、その普遍的価値を軽視あるいは否定して、国家の舵取りを担ったから、とされている。
⑨ここで、私が再度、問いかけている問題は、そもそもそれでは、その普遍的価値を重視して国家の舵取りができたのは、なぜなのかとの問いである。換言すれば、そうした普遍的価値の実現に成功した共同体は、どのようにして、その実現に成功したのか、という問いである。
⑩その際、普遍的価値を実現できた共同体は、その主権国家や国民国家をどのようにして実現できたのだろうか。この問いかけにもこたえなければならないはずだ。と言うのも、共同体を前提として初めて普遍的価値の実現が可能となったから、可能となるような歴史を辿れたからだ。
⑪その関連で言えば、植民地や従属地に甘んじた共同体は、市民革命を実現したとされる共同体によって、主権を奪われたり、否定された歴史を辿ったということであるから、そもそも⑤の諸国は、これらの共同体に対して、彼らが重視した普遍的価値を許さなかったということになるのだが、それはどうしてなのか。この問いにもこたえなければならない。
⑫私が考えるには、⑤の共同体が掲げる普遍的価値は、最初から差別と排除の関係をその裡(うち)に含むものではなかったのか、ということである。⑤の共同体がその絶対王政期につくり出した植民地や従属地との差別と排除の関係は、市民革命時も、その後も維持・継続したことを鑑みるとき、それは現実には、普遍化を許さない価値であり、それゆえその実現の歩みである普遍主義においても、差別と排除の関係は存続するのは当然なことであったのではなかろうか。
⑬それゆえ、普遍的価値の一つを構成する平和をいくら祈念したとしても、差別と排除の関係はなくなることはなく、結局のところ、私の語る〈「システム」とその関係の歩み〉が発展することになり、それゆえ、「システム」内での共同体間と、その構成員間の対立と衝突、そして戦争を引き起こすこととなるのだ。
⑭これらに付言して再度述べるとき、丸山眞男氏は、民権と国権の両者が「幸福な結婚」を経験した⑤と、そうではなかった⑥の例を紹介しているのだが、そこでもやはり同じように、どうして⑤の諸国は、幸福な、つまりは正常な発展ができたのかについては、その理由を論述していないのだ。それは⑥の諸国は、どうして不幸な、不正常な発展を経験したのかについても、同じである。
(最後に一言)
本当におかしなことなのだが、肝心な問いに関して、これまであまりにも「スルー」し続けてきたのはなぜなのか、それを私たちは考えた方がいいのだが、私のこんな問いかけなど、多くの人たちには決して共有されないのも承知しているので、これくらいにしておく。
それにしてもだが、英・米・仏・蘭に代表される普遍的価値を世界に向かって高らかに宣言したはずの共同体が、どうして世界中の多くの共同体を侵略したのか。そうした侵略を経験したはずの共同体の中から、どうしてまた同じような侵略が繰り返されるのだろうか。私たちは、こうした問いかけを踏まえながら、自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の歩み(歴史)の中に見いだされる「混然たる一体的関係」(司馬遼太郎)について、どうしても掘り下げて論じ直すことが必要ではなかろうか。
何度も言うようで恐縮だが、私の語る「システム」論で描かれるモデルの〈「システム」とその関係の歩み〉は、司馬が問いかけた先の関係を、私なりに描いたものであることを、ここで指摘しておきたい。なお、これについては、拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」-「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」世界・セカイとそこでの戦争・センソウ』(晃洋書房、2014年)を参照されたい。
(付記)
前回拙著の刊行から、もうかれこれ10年を迎えるのだが、次の作品を未だ完成できない我が身の能力のなさに、恥じ入るばかりの今日この頃でもある。もう、このまま終わってしまうのか、それでいいのか、当然ながら、よくはないのだが、もう今さら何を主張しても、「糠に釘」のような「システム」の中で、との思いが強まるばかり。まあ、それはそれで、たとえ同じことの繰り返しでも、書きたいと思う間は、書き続けたい。それも正直な思いである。
*(付記)の(付記)
今日は8月21日の早朝だが、昨日の昼頃から、丸山氏の名前をまた間違えたのではないかと、少し頭の中では思っていたが、先ほど確認してみると、案の定そうであったので、訂正しておいた。
また、司馬遼太郎氏の「混然たる一体的関係」の私的は、その通りだ、と私も道灌なのだが、誤解のないように述べておくと、いわゆる「司馬史観」と揶揄された彼の歴史の見方には、私も納得はしていない。それはそうなのだが、この一体的関係という観点から、自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の歴史を、それこそ一体的関係として描き直す必要性の私的は、『昭和史』(岩波新書、青版)の中で、「あの戦争」の「三つの性格」として提示した個々バラバラの歴史観と比べても、はるかに優れている、と私はみている。なお、これについては、拙著『「日本人」と「民主主義」』(御茶の水書房 2009年)を参照されたい。
(最初に一言)
前回記事も、またまた以前に述べた話の焼き直しであったが、それでも私自身のボケ防止において、少しは役に立っているのは間違いない。今回記事も、その予防を兼ねて、前回記事の内容を再度、確認してみたい。
前回記事の強調点を、箇条書きでまとめると以下のようになる。
①私たちの「不戦の誓い」で祈念される「平和」は、自由や民主主義人権といった普遍的価値を構成するものである。
②そうした普遍的価値が提唱されたのはいわゆるフランス革命に代表される市民革命においてである。
③普遍的価値は、ただいくらその価値や価値観が素晴らしいと礼賛しても、それが現実に実現されないのならば、まさに絵に描いた餅でしかない。
④普遍的価値を現実に実現する歩みである普遍主義を考察するとき、それは大きく二つに分類されていた、と私はみている。
⑤その一つは、いわゆる「正常な発展」を辿ったとされる諸国であるが、これは先の市民革命を経験した英・米・仏・蘭に代表される。
⑥これに対して、「不正常な発展」を辿ったとされる諸国がある。そこには、戦前の独・伊・日が含まれている。
⑦前回記事でも少し触れたのだが、どうして⑤⑥のように、正常と不正常の違いが生じるのか。これまでの知見に従えば、その違いは、普遍的価値を前提として、あるいはそれを尊重・重視して、共同体が、その際それは主権国家を前提とした国民国家とされるのだが、国家の舵取りを担ったことが大きな要因とされる。
⑧これに対して、不正常な発展を辿った共同体は、その普遍的価値を軽視あるいは否定して、国家の舵取りを担ったから、とされている。
⑨ここで、私が再度、問いかけている問題は、そもそもそれでは、その普遍的価値を重視して国家の舵取りができたのは、なぜなのかとの問いである。換言すれば、そうした普遍的価値の実現に成功した共同体は、どのようにして、その実現に成功したのか、という問いである。
⑩その際、普遍的価値を実現できた共同体は、その主権国家や国民国家をどのようにして実現できたのだろうか。この問いかけにもこたえなければならないはずだ。と言うのも、共同体を前提として初めて普遍的価値の実現が可能となったから、可能となるような歴史を辿れたからだ。
⑪その関連で言えば、植民地や従属地に甘んじた共同体は、市民革命を実現したとされる共同体によって、主権を奪われたり、否定された歴史を辿ったということであるから、そもそも⑤の諸国は、これらの共同体に対して、彼らが重視した普遍的価値を許さなかったということになるのだが、それはどうしてなのか。この問いにもこたえなければならない。
⑫私が考えるには、⑤の共同体が掲げる普遍的価値は、最初から差別と排除の関係をその裡(うち)に含むものではなかったのか、ということである。⑤の共同体がその絶対王政期につくり出した植民地や従属地との差別と排除の関係は、市民革命時も、その後も維持・継続したことを鑑みるとき、それは現実には、普遍化を許さない価値であり、それゆえその実現の歩みである普遍主義においても、差別と排除の関係は存続するのは当然なことであったのではなかろうか。
⑬それゆえ、普遍的価値の一つを構成する平和をいくら祈念したとしても、差別と排除の関係はなくなることはなく、結局のところ、私の語る〈「システム」とその関係の歩み〉が発展することになり、それゆえ、「システム」内での共同体間と、その構成員間の対立と衝突、そして戦争を引き起こすこととなるのだ。
⑭これらに付言して再度述べるとき、丸山眞男氏は、民権と国権の両者が「幸福な結婚」を経験した⑤と、そうではなかった⑥の例を紹介しているのだが、そこでもやはり同じように、どうして⑤の諸国は、幸福な、つまりは正常な発展ができたのかについては、その理由を論述していないのだ。それは⑥の諸国は、どうして不幸な、不正常な発展を経験したのかについても、同じである。
(最後に一言)
本当におかしなことなのだが、肝心な問いに関して、これまであまりにも「スルー」し続けてきたのはなぜなのか、それを私たちは考えた方がいいのだが、私のこんな問いかけなど、多くの人たちには決して共有されないのも承知しているので、これくらいにしておく。
それにしてもだが、英・米・仏・蘭に代表される普遍的価値を世界に向かって高らかに宣言したはずの共同体が、どうして世界中の多くの共同体を侵略したのか。そうした侵略を経験したはずの共同体の中から、どうしてまた同じような侵略が繰り返されるのだろうか。私たちは、こうした問いかけを踏まえながら、自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の歩み(歴史)の中に見いだされる「混然たる一体的関係」(司馬遼太郎)について、どうしても掘り下げて論じ直すことが必要ではなかろうか。
何度も言うようで恐縮だが、私の語る「システム」論で描かれるモデルの〈「システム」とその関係の歩み〉は、司馬が問いかけた先の関係を、私なりに描いたものであることを、ここで指摘しておきたい。なお、これについては、拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」-「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」世界・セカイとそこでの戦争・センソウ』(晃洋書房、2014年)を参照されたい。
(付記)
前回拙著の刊行から、もうかれこれ10年を迎えるのだが、次の作品を未だ完成できない我が身の能力のなさに、恥じ入るばかりの今日この頃でもある。もう、このまま終わってしまうのか、それでいいのか、当然ながら、よくはないのだが、もう今さら何を主張しても、「糠に釘」のような「システム」の中で、との思いが強まるばかり。まあ、それはそれで、たとえ同じことの繰り返しでも、書きたいと思う間は、書き続けたい。それも正直な思いである。
*(付記)の(付記)
今日は8月21日の早朝だが、昨日の昼頃から、丸山氏の名前をまた間違えたのではないかと、少し頭の中では思っていたが、先ほど確認してみると、案の定そうであったので、訂正しておいた。
また、司馬遼太郎氏の「混然たる一体的関係」の私的は、その通りだ、と私も道灌なのだが、誤解のないように述べておくと、いわゆる「司馬史観」と揶揄された彼の歴史の見方には、私も納得はしていない。それはそうなのだが、この一体的関係という観点から、自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の歴史を、それこそ一体的関係として描き直す必要性の私的は、『昭和史』(岩波新書、青版)の中で、「あの戦争」の「三つの性格」として提示した個々バラバラの歴史観と比べても、はるかに優れている、と私はみている。なお、これについては、拙著『「日本人」と「民主主義」』(御茶の水書房 2009年)を参照されたい。