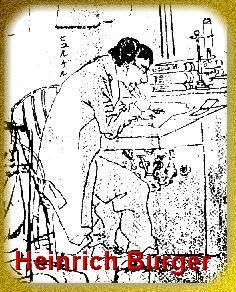長崎出島時代、オランダからきたケンペル、ツェンベリー、シーボルトが出島三学者と呼ばれている。

ケンペル(kennperu Engelbert Kaempfer, 1651~1716)は、ドイツ北部レムゴー出身の医師、博物学者。元禄3(1690)年、オランダ商館医として、約2年間出島に滞在した。1691年と1692年に連続して、江戸参府を経験し徳川綱吉にも謁見した。在日中、オランダ語通訳今村源右衛門の協力を得て精力的に資料を収集した。1692年、離日してオランダのライデン大学で学んだ後、故郷に戻ると著述活動に取り組んだ。死後の1727年、ロンドンで出版された『日本誌』は、フランス語、オランダ語、ドイツ語にも訳され、ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテスキューらも愛読した。
著書の中で、日本には、聖職的皇帝(=天皇)と世俗的皇帝(=将軍)の「二人の支配者」がいると紹介した。 その『日本誌』の中に付録として収録された「鎖国論」は、日本の鎖国政策を肯定したもので、当時のヨーロッパのみならず、日本にも影響を与えた。また、「鎖国」という言葉は、この「鎖国論」を志筑忠雄が訳した際にできた言葉である(ウィキペディアより)。

ツェンベリー(Carl Peter Thunberg, 1743~1828)は、スウェーデンの植物学者、医学者。日本植物学の基礎を作る。ウプサラ大学のカール・リンネに師事して植物学、医学を修めた。フランス留学を経て、1771年オランダ東インド会社に入社。安永4(1775)年、オランダ商館医として出島に赴任。翌1776年4月、商館長に従って江戸参府、徳川家治に謁見した。わずかな江戸滞在期間中に、吉雄耕牛、桂川甫周、中川淳庵らの蘭学者を指導した。1776年、在日1年で帰国し、1781年、ウプサラ大学長に就任した。在日中に採集した植物800余種の標本はいまもウプサラ大学に保存されている。著書に『日本植物誌』、『ヨーロッパ、アフリカ、アジア紀行』、『ツンベルクの日本紀行』、『喜望峰植物誌』がある(ウィキペディアより)。

シーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796~1866)は、ドイツの医師、博物学者。東洋研究を志し、1822年にオランダのハーグへ赴き、国王のヴィレル1世の侍医から斡旋を受け、1823年6月に来日。出島内において開業、1824年には鳴滝塾を開設し、医学教育を行う。高野長英・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介らを育て上げた。
1823年4月には162回目にあたるオランダ商館長の江戸参府に随行、商館長の一行に加わる。道中を利用して地理や植生、気候や天文などを調査する。江戸においても学者らと交友し、蝦夷や樺太など北方探査を行った最上徳内や高橋景保(作左衛門)らと交友、徳内からは北方の地図を贈られる。
景保には、クルーゼンシュテルンによる最新の世界地図を与える見返りとして、最新の日本地図を与えられた。

楠本滝との間に、娘、楠本イネをもうける。
紫陽花は学名Hydrangea otakusaと滝の名前をつけている。1828年に帰国する際、収集品の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、国外追放処分となる(シーボルト事件)。
帰国後は日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本(日本、日本とその隣国及び保護国蝦夷南千島樺太、朝鮮琉球諸島記述記録集)』を随時刊行する。
一方で日本の開国を促すために運動し、1844年にはオランダ国王ヴィレル2世の親書を起草し、1853年には米国東インド艦隊を率いて来日するマシュー・ペリーに日本資料を提供する。1857年にはロシア皇帝ニコライ1世に招かれ、書簡を起草するが、クリミア戦争により日露交渉は中断する。
1845年にはドイツ貴族のヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚、3男2女をもうける。1854年に日本は開国し、1858年には日蘭通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。
1859年、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。1862年に官職を辞して帰国。1866年10月18日、ミュンヘンで死去、70歳。シーボルトの息子アレクサンダー・フォン・シーボルトは、安政6(1859)年以来、日本に滞在、英国公使館の通弁官を勤め、慶応3(1867)年、徳川昭武らのフランス派遣(パリ万博のため)に同行している。また、従兄弟の子供に当たるアガーテ・フォン・ジーボルト(1835-1909)は、ブラームスの婚約者だったことで知られる(ウィキペディアより)。
彼ら「出島の三学者」のいずれも、本草学に造詣が深かった。本草学というのは、薬草などの植物学、薬物学、博物学といった、薬と関連するいろいろな分野を総合する学問である。江戸時代の日本の本草学の水準の高さは、すでに世界レベルであった。当時、蘭学者になろうとして蘭学塾に入門するには、本草学の知識をもっていることが条件になっていたほどである。