パソコンをRAID0構成にしました。
Dimension 9200は購入時にRAID構成を選べますが、ハードディスクを後から追加した方が安くなりそうなので、あえて購入時にはしませんでした。
でも実際には……
安いと思っていたのですが、新品のHDDの場合は計算するとほとんど変わりません。
これから買う場合はRAIDは選択せずハードディスクの2台構成にして後からRAIDに変更する事をおすすめします。
もしくは、ジャンク品のHDDなんていう選択もありますが、RAID0にするのはちょっと怖いです。
RAIDとは
複数のハードディスクを組み合わせ仮想的に1台のドライブとして利用する技術です。
RAIDにはレベルにより目的が異なってきます。
Dimension 9200では以下の2種類のRAIDレベルを選択可能です。RAID0(ストライピング) ハードディスクの高速化
複数のディスクにデータを分割して保存/読み出す方式でディスクアクセスが高速になり、総ディスクサイズは導入したディスクの総サイズとなります。
デメリットは1台でもディスク故障が発生すると、RAID構成内のデータは全て失われる事となります。RAID1(ミラーリング) ディスク故障時でもデータを損失する事が無い
複数のディスクに同じデータを書き込み、片方のディスクが壊れてもデータは別のディスクで維持されるので、ディスク故障に備えたものです。
デメリットは、使用可能なディスク容量はRAIDを構成する最小のディスクサイズとなる事です。
ハードディスクはBUFFALOのHD-H250FBS2/3Gという250GByteのSerialATAⅡ 3Gbps転送のもので、既に取り付けているディスクと同等レベルのものです。 SATAケーブルは1.5GbpsのものとSATAⅡの3Gbpsに対応したものがあります。
SATAケーブルは1.5GbpsのものとSATAⅡの3Gbpsに対応したものがあります。
違いは良くわかりませんが、SATAⅡに対応したものを選択。
また、コネクタ形状は片側がL型のものが良さそうです。
ここで、失敗が...
パソコン本体の筐体を開け新しいハードディスクを取り付けると、SATAのケーブルが付いていない事に気がつきました。
てっきり付属しているものだと思ってました。
長さは70cmを購入しましたが、ちょっと短いかなという感じです。
ケーブルも揃いようやくセットアップです。
RAID化にはIntel Matrix Storage Consoleという標準でついてくるソフトを利用します。
手順としてはざっと以下の通りです。
(1)ハードディスクを取り付け電源を入れます
(2)BIOSの設定で追加したハードディスクのSATAポートとRAIDを有効にします
(3)PCを起動しIntel Matrix Storage Consoleを管理者モードで起動します。
後は、既存のハードドライブからのRAIDボリュームを作成を選んで、ウィザードを選択していけば良いだけです。
設定でわからなければ、全てデフォルトでOKです。
完了するまでは、2.5時間位かかりました。
パーティション変更
上記方法でRAID設定しただけでは、新規に追加したディスク容量はまだ利用出来ません。
Windowsのディスクの管理ツールで、”ベーシック ボリュームを拡張する”を実行すると、Cドライブに追加分を割り当てる事が出来ます。
結合せずに、そのままフォーマットすれば、別パーティションとなります。
Windows XP標準では出来なかったパーティションの変更が、Vistaでは標準搭載されています。
既存のパーティションに追加する場合は”ベーシックボリュームを拡張”、
既存のパーティションを分割して新しいパーティションにするには”ボリュームの圧縮”
で自由にパーティションサイズ、分割、結合が可能です。
また、最近は内蔵HDDを買うと大抵パーティション操作のソフトが付いてくるので、こちらを使えば同じようにディスク割り当てを好きなように変更出来ます。(ソフトがまだvistaに対応していなかったりしますが…)
 ストライピング後のスコアを確認すると、ディスク関連のスコアは以前は5.4でしたが5.9になりました。
ストライピング後のスコアを確認すると、ディスク関連のスコアは以前は5.4でしたが5.9になりました。
現在のWindowsエクスペリエンスインデックスの上限値は5.9?なので満点です。
だから何って感じもしますが…
ただ、新しいHDDのせいなのかRAIDなのか良くわかりませんが、ちょっと音がうるさくなった様な気がします。













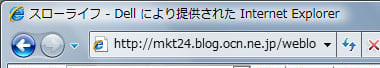 ダサすぎです…
ダサすぎです…
