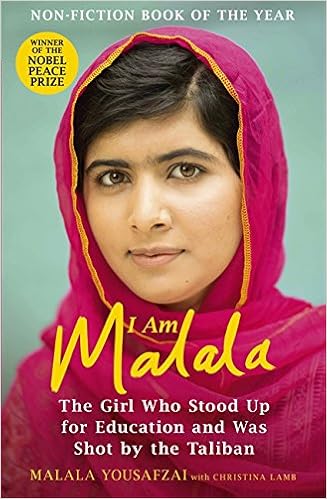大多数の同年代の友人と同じく、小学生で「ベルばら」の再放送をTVかぶりつきで毎週見ていた私、大人になってこの本を見つけたときは、てっきり、同姓同名の別人かと思った。読めば、「オルフェウスの窓」「エロイカ」「女帝エカテリーナ」・・・誰でも知っているような人気作品の数々を世に送り出す漫画家のキャリアを47歳で捨て、東京音大に入学した池田理代子さんのバイタリティに驚愕。さらに、文章のうまさも並大抵ではない。
新しい環境を経験するのは、得られるものが大きい反面、体にも心にも非常にハードな負荷をかける。年齢がいけばなおさらだ。それが、猛勉強の末にドイツ語や楽典、ピアノなどを含む難関試験に合格し、専門過程がみっちり詰まった4年間を、「とにかく歌うことが大好き」で乗り越えたエッセイ。それも、「頑張ったら、あら、できた」みたいな優等生的なキレイゴトが一切ないところが大好き。
スキーで肋骨を折ったり結婚が週刊誌に大バッシングされたり、ピアノの試験中に緊張のあまり暗譜した曲が頭からすっ飛んで真っ青になったり、といった「普通に毎日が超大変」な中、安くて栄養満点な学生食堂が何よりの楽しみで、ダニに刺されて顔中が腫れあがったなんて書く身近さ、レッスンがうまくできなかった日は池袋からぽろぽろ泣いて帰るというような感受性の鋭さがもう、ほんとに好きで、何度も繰り返し読んでいる。何か新しいことに挑戦したいとき、背中を押してくれる一冊。