おはようございます。神奈川県足柄、松田の河津桜をみた翌日は、本場、河津の河津桜見物に行ってきやした。京都の東寺にもたくさんの河津桜の若木が植栽されているのを知ったとき驚いたが、現在、第二のソメイヨシノになるのではないかと思われるほど全国に拡散している。あの鮮やかなピンク色の桜が、まだ二月のうちから見られるのだもの、増えるわけだ。以前は、河津桜、見に行ったよ、といえば、伊豆の河津桜だと誰もが思ってくれたが、今は違う。どこの河津桜?と聞き返される。だから、この記事のタイトルもわざわざ”河津の河津桜”としたわけ。
2016年2月18日 河津の河津桜
やっぱり、本場の河津桜は一味、違いますね。わざわざ、2時間かけて行く価値はある。とくに、昨日のように最高の見頃を迎えたときは、目を通して入ったピンク色が心の中にまで進入して、からだ全体がピンクの大風船になったような、ふわふわした気持ちと言ったらよいだろうか(笑)。
それに、河津川沿いの桜並木というのが風情があっていい。それが、4キロも延々とつづく。そして、出店の数もはんぱでない。伊豆特産のものが中心だが、いろいろあり、眺めたり、試食をしたりと、花より団子派の人も十分楽しめる。ぼくは花+団子派かな。そして、何よりも、河津桜の原木を拝めるのがうれしい。拝めると言えば、来宮神社のご神木、大楠を見上げるのも楽しみのひとつ。では、一回では終わらないと思うが、4時間ほどの桜ウオークを再現してみよう。
踊り子号で河津駅に到着したのが、11時22分。満員の電車からほぼ全員が下り、ホームは満杯。駅を出て、川沿いへ向かう道も桜並木。この時点で、桜も菜の花も見頃になったことがわかる。


その小道はすぐ河津川に突きあたる。館橋の左が河口へ向かう道。その道が、結構、いい桜並木に育ってきていて、駅前ということもあり、多くの人は、まずこちらを見物するようになっている。ぼくも、今回ははじめて河口まで歩いてみた。
館橋付近 花に勢いがあり、最高の見頃になっている。かなりの人出。

川辺の桜はいい。

数百メートル歩くと、浜橋で、その先は河口と海。浜橋から館橋方面の桜並木を眺める。今、この桜道を歩いてきた。ここだけでも満足なのに、これは、河津のほんの一部。1/10といったとこ。

河口をみてみよう。

河口にひっそり咲く河津桜もいい。

この近くのホテルの前で、”正月桜”と称する河津桜の早咲き系の桜をみた。もう葉桜になっている。

その横に説明板があった。この”正月桜”は、この地に限って植栽し、拡散させないようにしようと書かれていたが、鎌倉宮や三浦海岸の一部の早咲き系と同じものではないだろうか。

この桜道の下の道路には出店が並んでいる。以前はそんなでもなかった。人だかりがあった。なんだろう。

お猿さんの芸だった。

ここで、楽しんで、お猿さんがひと休みしたとことで、ぼくもひと休み。鮎の塩焼きで熱燗一本(汗)。

この一画でいくつも面白いものをみた。一つ目はスカイツリー! 右下の人影と比べてみてください。結構、大きい。何のために建造したのか、不明。たぶん、みんなが面白がってくれるからと思って建てたのだろう。それが一番!見上げた男だ。女かもしれないが。
右下の人影と比べてみてください。結構、大きい。何のために建造したのか、不明。たぶん、みんなが面白がってくれるからと思って建てたのだろう。それが一番!見上げた男だ。女かもしれないが。

これもびっくり。見た目は勝海舟と坂本竜馬と思ったが・・・。

勝海舟は当たったが、龍馬ははずれた。その人は、地元出身で咸臨丸の乗船員となった鈴木長吉だった。帰ってから、調べると偉い方だった。大工頭として咸臨丸に乗船、その後、明治新政府に招かれ、横須賀造船所の技術畑の重鎮として活躍されたそうだ。
これは、駅前の案内で知ったのだが、お相撲の一手、かわづ掛けの考案者、河津三郎はこの地の領主だった。近くの八幡宮に三郎の力石があるそうだ。曽我兄弟の父親でもある。来年は、ぜひぜひ見に行こう。

いろいろ楽しんで、館橋に戻ってきた。

ようやく、河津桜見物の1/10の紹介がおわった。先を急がねば。この調子では、何日、かかるかわからない。
でも、ここでひと休み。今日もいい天気だし、これから、また、もう一つの河津桜を見に行かねば。




























 もにゃんにゃんにお願いしましょう。
もにゃんにゃんにお願いしましょう。




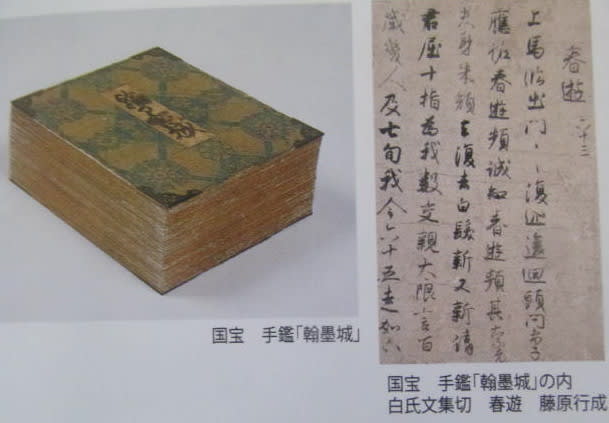






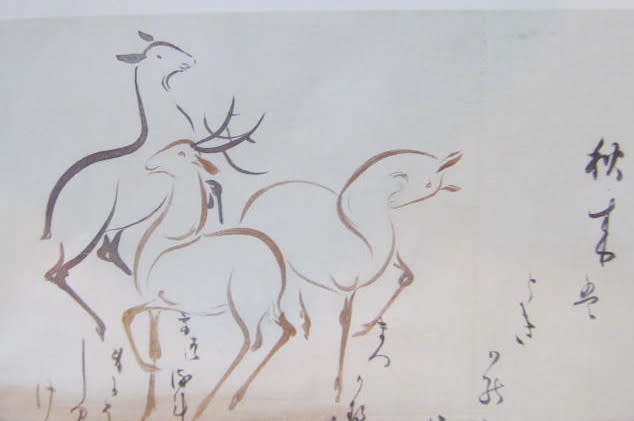

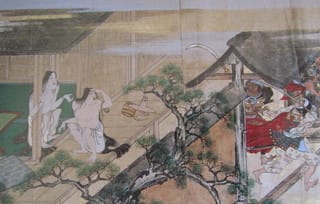
















































































 とういわけで、記念すべき、
とういわけで、記念すべき、

















































