2008.6.21(土)
先日、今季初のびわを食した。大粒の実で甘さも十分だった。
びわと言えば上関町の祝島が有名所である。数年前、祝島の知人から箱入りのびわを頂いたが、これには唸りましたね。特産品というだけのことはあり、その甘さたるや郡を抜いていた。みかんもそうだが、びわも島で獲れるものが良いのかなあ。おそらく、海風にあたるのと陽にあたるのが良いのだろう。年平均気温が15度以上、-5度以下にならないような所が良いと聞いたことがある。全国的には長崎、千葉、香川、和歌山あたりが有名産地だが、やはり温帯地域が良いようだ。
美味しいびわの見分け方は、へたがしっかりしていて、果皮に張りがあり、びわ独特の鮮やかさがあるもの、産毛と白い粉が残っているものが新鮮とのこと。そういえば、捥ぎたてのびわは薄い白い毛に覆われているなあ。逆にテカテカと光っているものは味が落ちているので避けた方が良いらしい。また冷蔵庫で冷やすのは3時間程度が限度で、冷やし続けると変色して味が落ちるらしい。
びわは屋敷の敷地内に植えるものではないと良く耳にする。その理由を調べてみると、中国4千年の歴史の何時頃のことか解らないが、全ての病気の治療をびわの葉に頼っていた時代があり、びわの木があると病人たちがその葉っぱを下さいと集まって来て、終いには長い行列ができたと言われる。そのために、びわの木があるとろくでもない病人たちが集まって来て縁起が悪いと心狭い人達が考え、びわの木を植えることを嫌い、縁起の悪い木となったのだそうだ。これとは反対に家を建てたなら屋敷の東南の地に必ずびわの木を植えるという地方もあるという。
そこでびわの効能を調べてみると、びわはあんずやみかんに次いでビタミンAを多く含み、またβカロテン、カリウム、サポニン、アミグダリン、タンニン、ビタミン17、クロロゲン酸、βクリプトキサンチンなどを含んでいるとのこと。高血圧予防、動脈硬化予防、脳梗塞予防、心筋梗塞予防、がん予防、老化防止、風邪予防、咳止め、胃腸病、去痰、皮膚炎などなど、びわは万病に効くと考えられるほど不思議な植物である。
葉っぱをお風呂に入れたり、湿布薬(出来るだけ古い葉っぱが良く、ぺたぺた貼るだけで良い)に使ったりもするらしい。
なるほど、これだけの効能があれば病人たちが集まってくる訳だ。そうなると、敷地内にびわの木を植えてはならないということはないのである。皆さん、医者要らずのびわの木を挙って植えましょう。
今日の暦
・夏至(24節気)
・乃東枯る(72候)
・正倉院宝物はじまりの日、756年(天平勝宝8)光明皇太后が亡き夫である聖武天皇の遺品を東大寺大仏に献納した日。
・冷蔵庫の日、日本電気工業会が1985年(S60)から夏至の日を冷蔵庫の日とした。
・スナックの日、全日本菓子協会が制定。
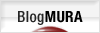
※お願い:下の広告を全部クリックして下さい。



先日、今季初のびわを食した。大粒の実で甘さも十分だった。
びわと言えば上関町の祝島が有名所である。数年前、祝島の知人から箱入りのびわを頂いたが、これには唸りましたね。特産品というだけのことはあり、その甘さたるや郡を抜いていた。みかんもそうだが、びわも島で獲れるものが良いのかなあ。おそらく、海風にあたるのと陽にあたるのが良いのだろう。年平均気温が15度以上、-5度以下にならないような所が良いと聞いたことがある。全国的には長崎、千葉、香川、和歌山あたりが有名産地だが、やはり温帯地域が良いようだ。
美味しいびわの見分け方は、へたがしっかりしていて、果皮に張りがあり、びわ独特の鮮やかさがあるもの、産毛と白い粉が残っているものが新鮮とのこと。そういえば、捥ぎたてのびわは薄い白い毛に覆われているなあ。逆にテカテカと光っているものは味が落ちているので避けた方が良いらしい。また冷蔵庫で冷やすのは3時間程度が限度で、冷やし続けると変色して味が落ちるらしい。
びわは屋敷の敷地内に植えるものではないと良く耳にする。その理由を調べてみると、中国4千年の歴史の何時頃のことか解らないが、全ての病気の治療をびわの葉に頼っていた時代があり、びわの木があると病人たちがその葉っぱを下さいと集まって来て、終いには長い行列ができたと言われる。そのために、びわの木があるとろくでもない病人たちが集まって来て縁起が悪いと心狭い人達が考え、びわの木を植えることを嫌い、縁起の悪い木となったのだそうだ。これとは反対に家を建てたなら屋敷の東南の地に必ずびわの木を植えるという地方もあるという。
そこでびわの効能を調べてみると、びわはあんずやみかんに次いでビタミンAを多く含み、またβカロテン、カリウム、サポニン、アミグダリン、タンニン、ビタミン17、クロロゲン酸、βクリプトキサンチンなどを含んでいるとのこと。高血圧予防、動脈硬化予防、脳梗塞予防、心筋梗塞予防、がん予防、老化防止、風邪予防、咳止め、胃腸病、去痰、皮膚炎などなど、びわは万病に効くと考えられるほど不思議な植物である。
葉っぱをお風呂に入れたり、湿布薬(出来るだけ古い葉っぱが良く、ぺたぺた貼るだけで良い)に使ったりもするらしい。
なるほど、これだけの効能があれば病人たちが集まってくる訳だ。そうなると、敷地内にびわの木を植えてはならないということはないのである。皆さん、医者要らずのびわの木を挙って植えましょう。
今日の暦
・夏至(24節気)
・乃東枯る(72候)
・正倉院宝物はじまりの日、756年(天平勝宝8)光明皇太后が亡き夫である聖武天皇の遺品を東大寺大仏に献納した日。
・冷蔵庫の日、日本電気工業会が1985年(S60)から夏至の日を冷蔵庫の日とした。
・スナックの日、全日本菓子協会が制定。
※お願い:下の広告を全部クリックして下さい。




























