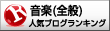何かが僕のなかで終わりつつあるようだ。横たわる死ではないけれど、まるで幻想に取り憑かれていたものが、すーっと消えつつような感覚。しかし、それを認めることができないのも仕方がないのかもしれない。正しかったものが正しいということよりも、正しいと信じていたかっただけで根拠なんてものは何処にもありはしなかった。
この世界がおかしいと感じていた頃から、何もかもが始まっているのだろう。このままでいいはずがない世界で、僕は何もできないどころか何もしなかった。ただおかしいということだけは僕のなかから消えることはなかった。おかしいということが僕にとって自然なことだったんだ、大きな渦のなかにあっても、変われない自分がいた。この世界では僕は全く役にたたないもの、まるで自分自身で虚無に引き摺りこんでいく。混沌とした世界で朽ち果てていくだけなのかもしれません。
何かギリギリのところで浮かんでくるものが、終わりを迎える前に僕自身が感じたおかしなことを理解したいと願うばかり。
生きたいと願うことよりも、存在したということを僕が認めることができるのか、それがいまはわからない。
この世界がおかしいと感じていた頃から、何もかもが始まっているのだろう。このままでいいはずがない世界で、僕は何もできないどころか何もしなかった。ただおかしいということだけは僕のなかから消えることはなかった。おかしいということが僕にとって自然なことだったんだ、大きな渦のなかにあっても、変われない自分がいた。この世界では僕は全く役にたたないもの、まるで自分自身で虚無に引き摺りこんでいく。混沌とした世界で朽ち果てていくだけなのかもしれません。
何かギリギリのところで浮かんでくるものが、終わりを迎える前に僕自身が感じたおかしなことを理解したいと願うばかり。
生きたいと願うことよりも、存在したということを僕が認めることができるのか、それがいまはわからない。