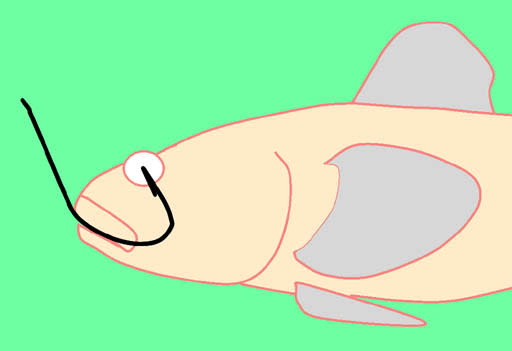
黒は釣針
「片目伝説」は、日本各地に散らばっている。
近辺で有名なのは、横手の厨川(くりやかわ)にすむ片目のカジカである。
後三年の役、鎌倉権五郎景政が、射られた目を洗った厨川のカジカが
片目になったという、全国各地に伝わる「鎌倉権五郎景政伝説」とよばれるもののひとつである。
なぜ、片目の魚が出現するかというと、その原因は釣針にちがいない。
口が大きく、目が前方にあるカジカ・ハゼ類は、
大きな針でもくわえるために、目を針先が貫通することが多い。
絵は魚体とマス類の釣針を同じ縮尺で描いた。
以前、イカの餌付けに使用するために、岸辺の岩の間に釣針を落として
ドロメ類を釣ったことがあるが、かなりの率(20%くらい)で釣針は目を貫いていた。
片目伝説にはフナが多いが、釣ろうと思っていない小さな魚が、
ある大きさの釣針に食いついてくると、やはり目を貫くことがある。
とくに私のような釣りの下手な人間がやれば確率は大きい。
そして、釣ろうとした目的の魚ではないために、再び放される。
以上、科学的思考もできることの自慢である。
実は男鹿半島にも、片目魚の伝説があるが、少し変わっている。
(1)無理に押しかけてくる八郎太郎を退治してほしいと、一ノ目潟の姫が竹内神主に頼んだ。
竹内神主が八郎太郎を弓で射ると八郎太郎の目に当たった。
それ以来、一ノ目潟のフナは片目になった。
(2)無理に押しかけてくる八郎太郎を退治してほしいと、一ノ目潟の姫が竹内神主に頼んだ。
竹内神主が八郎太郎を弓で射ると当たった。
しかし、八郎太郎は矢を抜き取り、「子孫七代まで片目にしてくれる」と叫びながら、
投げ返した矢は神主の目に当たった。
(1)は一般的な「秋田の民話」に載っている内容、
(2)は、男鹿市教育委員会で出版した「男鹿の昔話」である。
基本的内容を変えないように気をつけて、両方とも文章を要約変形している。
どちらが元の話なのだろうか。
わたしは(2)が最初の話に近いと思う。
(1)は主人公であるべき人間が片目になってしまって、
おかしいと、あとの人がつじつまを合わせたのである。
柳田 國男(やなぎた くにお)は「一目小僧(ひとつめこぞう)」で次のようなことを述べている。
ずっと昔の大昔には、祭りのたびごとに一人ずつの神主を殺す風習があった。
殺される神主は前の年の祭りの時から籤(くじ)か神の声である神託(しんたく)に
よって決められていた。
生け贄(にえ)となるこの神主をはっきり見分けることができるように、
片目をつぶし、逃げられないように片足を折った。
そしてその人を優遇し尊敬した。
やがて、その神主も死んだら神になれるという確信を持つようになり、
心も澄んで、神の心を伝える神託預言を始め、人々の中で力を持ってくる。
死にたくないという気持ちから、「この神主(自分)を殺す必要はない」と
神が言っているという託宣(たくせん)もしたかもしれない。
上の話から、幻想を進めると、日本書紀、垂仁天皇(すいにんてんのう)の
次の話を私は思いうかべる。
倭彦命(やまとひこのみこと)が亡くなったとき、いままで使えていた者を集めて、
陵の周りに生き埋めにした。泣きうめく声がいつまでも続き、やがで死んで腐り、
犬や鳥が食い始めた。
泣きうめく声を聞いて、天皇は「これからは殉死を中止するように」と命じた。
その後、皇后日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が亡くなられたとき、
野見宿禰(のみのすくね)は埴輪(はにわ)を考案して、人を生き埋めにはしなかった。
昔、殉死があり、やがてそれがなくなったように、神主の片目をつぶし殺すかわりに、
神社の池で泳ぐ魚の片目をつぶすようになったのかもしれない。
わたしは片目が壊れている。わたし自身、神と人間との間の存在で、
話す言葉は神の声ということになる。そういわれればそんな気もしてくる。^^;
参考:
・一目小僧 柳田國男全集7 筑摩書房
・目一つ五郎考 柳田國男全集7 筑摩書房
・片目の魚 柳田國男定本30 筑摩書房
・青銅の神の足跡 谷川健一著作集5 三一書房
・一つ目小僧と瓢箪 飯島吉晴 新曜社
・日本書紀 宇治谷孟 講談社学術文庫















断捨離されながらでしょうか、
暮らしの引っ越しと一緒でブログの引っ越しも大変そうですね。
がんばってください。
コメント欄を設けてくださったのすね。
これで質問がしやすいです。
コメント欄は作らないつもりでしたが、いつの間にか表示させていました。これも何かの縁でしょうから、このまま開いておくことにします。
山里さんとお話が弾みそうな記事ですね
四神のところで
高松塚古墳と薬師寺の薬師三尊の台座と
どっちが古いかな?などと思いました
私が子供時代四神のことを知ったのは
修学旅行で
あの台座の玄武に興味を持ったからでした
ところで
鉾をそちらではやりと読むの?
鉾とやりを調べたら結構近い存在なのですね?
この手の記事もわたしはとても面白いです
前よんだと思うけれど
又面白いです