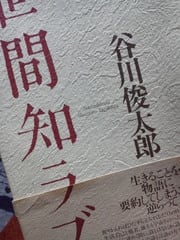好天続く。
出かけたり客が来たり。知らぬ間に一日過ぎる。
市役所行って帰りに駐車場から出てきたら、隣の会館の前にバスやらタクシーやらがいっぱいで、さらに大勢の人で動きがとれない。たくさんいる人間たちがみんな老人で、ウソみたいにゆっくり移動して行く。ウソみたいにみんながノロノロと道路を横切ったりしているから、こちらも全然動けない。
ソロソロと車転がしながら会館の入り口見たら、戦没者慰霊遺族会総会みたいなことでありました。
ついでに久しぶりに新刊本屋に寄る。最近は殆ど入らなくなった。
岩波現代文庫の新刊で富岡多恵子『湖の南 大津事件異聞』を買おうか買うまいかさんざ迷って結局買う。買ってから、やっぱり読まないような気がしてくる。いつものパターン。
で、ついでに文庫の棚をサッと眺める。これもずいぶん久しぶり。いちおう北杜夫を探してみるが全部で5冊ぐらいしか並んでない。これはちょっと驚き。というわけで新潮文庫の棚だけでも眺めてみると、当然ながら昔とはだいぶ様変わり。全然知らない人ばかり。
ワシが毎日のように眺めていた頃(もう30年以上前ですけどね)の新潮文庫だったら、例えば石川達三とか井上靖とか遠藤周作とか、そんなの全くない。山口瞳とか吉行淳之介とか、それだけで一列あったようなのがほぼ無い。まあ当たり前か。変わらないのは司馬遼太郎と、それからアッパレ太宰治とかか。
そう見てみると、古典といわれるようなものにもだいぶ消長があるなあ。その昔、昭和の古典、青春の三種の神器とか三羽烏とかいわれてたのが、太宰治、中島敦、梶井基次郎で、(ワシの記憶では)そのうちのどれかはたいがいの本棚にはあったものだけれど、さて今はどうなんだろう。なんだか前二者は今でも健在だけれど、梶井はこのところトンと聞かない気がする。(最近の状況については全くわからないのですが。)ワシの記憶では当時はこの中ではむしろ梶井が一番人気で、主要文庫には必ず梶井基次郎一冊必ずラインナップされていた。(まあ一冊でほぼすべての作品が読めちゃうわけだけれど。)
というわけで、一応その証拠。

本棚ちょっと探しただけで、すぐに文庫で5冊でてきた。
『檸檬』(昭和50年5月 新潮文庫)
『檸檬・ある心の風景 他二十編』(昭和51年 旺文社文庫)
『城のある町にて』(昭和52年8月 角川文庫)
『檸檬・Kの昇天 ほか十四編』(昭和51年2月 講談社文庫)
『檸檬・冬の日 他九篇』(1977年10月 岩波文庫)
ついでに、文庫ということで、鈴木沙那美『転位する魂 梶井基次郎』(昭和52年5月 現代教養文庫)
収載作品はどれもほぼ同じ。このほかにも探せばまだあるかもしれない。作品以外にも評論や回想ならまだいろいろ出てくるだろう。(中谷孝雄なんか、梶井で食ってるような印象だったもんな。)
まあともかく、同じ作品をこれだけ買っちまうというだけでも当時のワシ自身の状況汗顔のイタリではありますが、世間的にもそんなもんだったろう。
というわけで、さてここから、ということですが、意外とハナシがふくらまない。どっちの方へ持ってくか、何にも考えてないから、このまま終わるか。