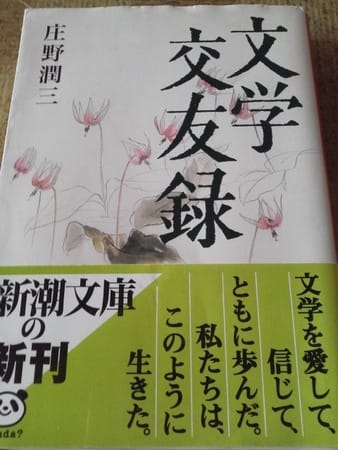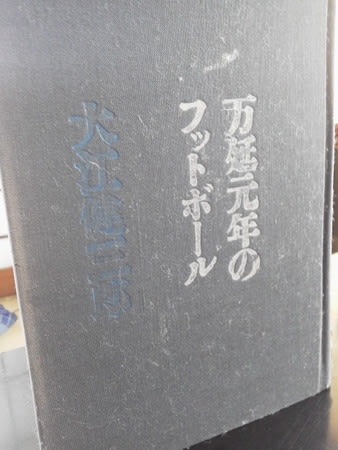オールナイトニッポン、名前も顔もわからないが二十代前半ぐらいと思われる女の子がパーソナリティでこれがまたよく笑う。その笑い声が特徴的で、なんというかキャーハハハ、みたいな脳天気というか屈託なさすぎというか、ともかく耳についてますます眠れない。

氏家セイ一郎 聞き書き塩野米松『昭和という時代を生きて』(2012 岩波書店)を本屋で見かけて2400円もしたのに買ってしまった。こういう衝動買いはやめようとそのたびに思っていまだにやめられない。
かつての特ダネ記者というか、ナベツネの盟友、というか日テレのとっても偉い人というか、なんか2年前くらいに急に亡くなった人の回想録であるわけだけれども。
真っ先にジブリの話から出てくる。親会社だから不思議はないわけだけれど、徳間康快から、「風の谷のナウシカ」を当時破格の4500万で買ったとか、そのあとの「ラピュタ」は9900万だったとかいう話。(いずれにしてもその後あれだけ放送してれば充分モトはとっただろうが。)
徳間(というか「コクリコ坂」の徳丸理事長ですな。)も氏家も読売で元共産党だから付き合いは古いんだろうが、ともかくついでに、以前買った佐高信『飲水思源 メディアの仕掛人、徳間康快』(2012 金曜日)も出してきたけど、こっちは著者の思い入れだけみたいなとこがあって、もっと事実だけを叙述してもらえばよかったと思ったことでした。

急死したせいか後半は駈足みたいになって、その分若い頃、ことに共産党員だった時代の事がけっこう詳しくて面白かったな。戦後すぐくらい東大経済学部全体900人のうち200人以上が共産党細胞だったというのは今からでは想像しがたいかもしれない。そういえば東大生の過半数が自民党支持になったといって驚いてたのは80年代くらいか。これだって今からではよく理解されないかもしれない。
なかで網野善彦との付き合いについて、意外と厚い付き合いだったらしいことに驚いた。網野がかつて共産党員時代の論文について後年全否定したことについて、(この辺はちょっと評価が難しいのだろうが)彼がどのような転向を果たしたのか、それが自身の人生の最大関心事だとまで言っている。
で、あとはやっぱりジブリ(というか宮崎、高畑両監督)との関係だな。
今度の宮崎の作品の堀越二郎に憧れた少年というのは氏家のことらしい。
それ以上に高畑勲への思い入れの強さである。氏家が最も評価していたのは「となりの山田くん」らしいし、二年前急死する以前に「かぐや姫」のコンテはだいぶできていたらしくて、「これは儲からない。だが損をしてもいいからいい作品をつくってもらう」旨社内に大号令出してるらしい。
にしてもなんで高畑勲なのか。(たしか徳間康快もそうだったよな。)鈴木敏夫の巻末の解説によれば、鈴木が氏家にしたその質問に対して、「おれはあいつに惚れてる」「あの男にはマルキストの香りが残っている」と答えたという。なんかちょっと考えさせられる。
(高畑との最初の邂逅のとき、「世界はこれからどうなるのか」という氏家の質問に、高畑が「地球の資源は有限。みんなでそれを争って無駄遣いしていたら、人類そのものが駄目になる。名前は違うだろうが、共産主義的なものでやっていくしかない。」と答え、それに対して氏家が一言「同感です」と応じたという。)
巻末にはもう一本、辻井喬の解説がついている。期待して読んだけど、なんだかよくわからない文章だった。