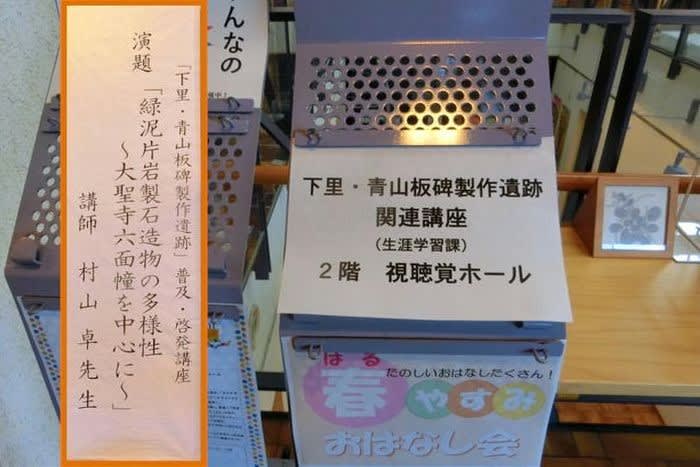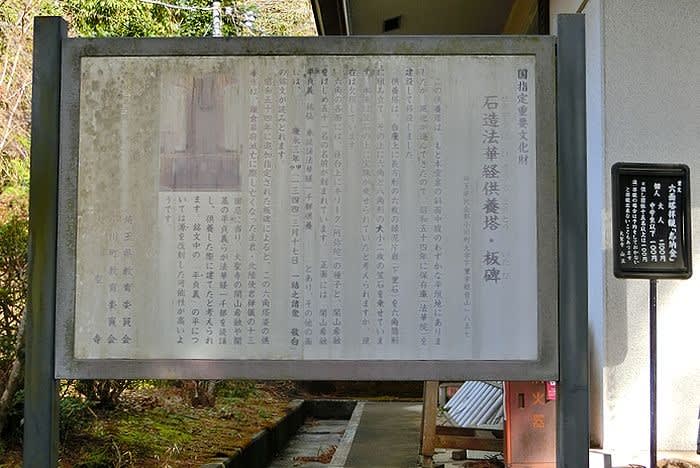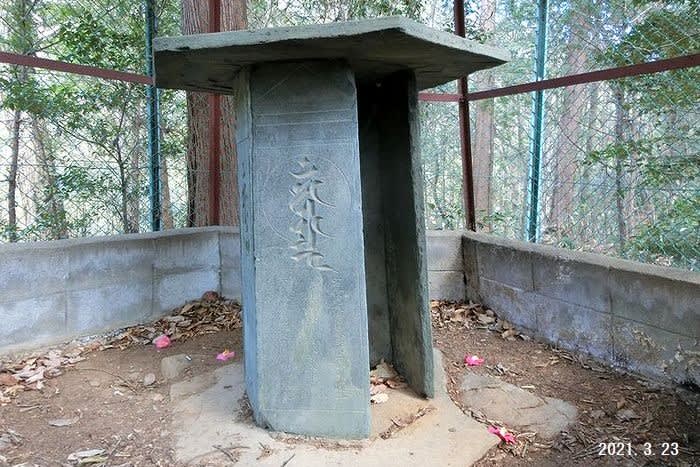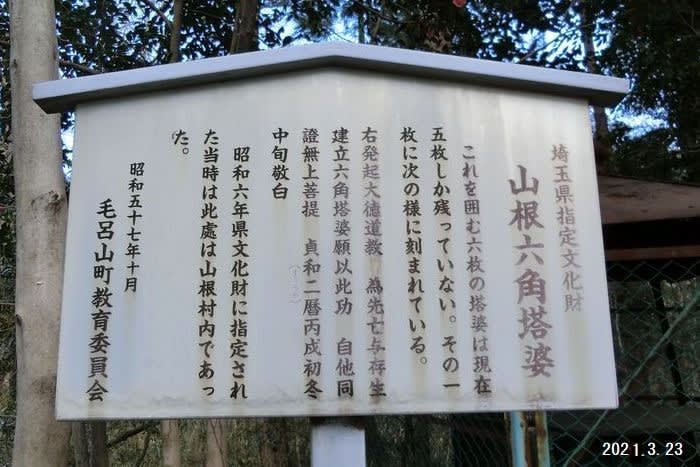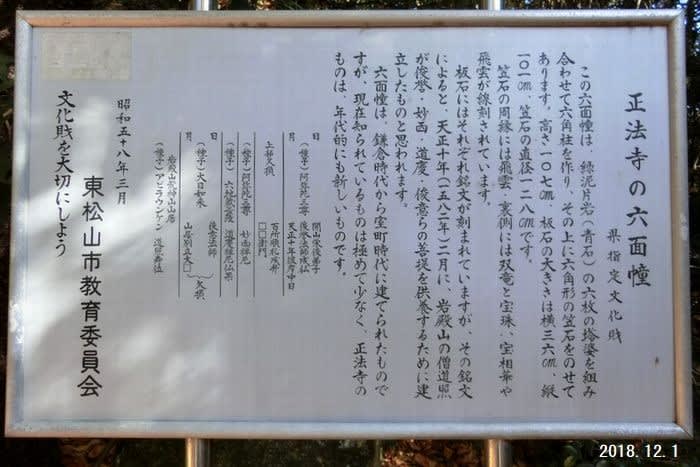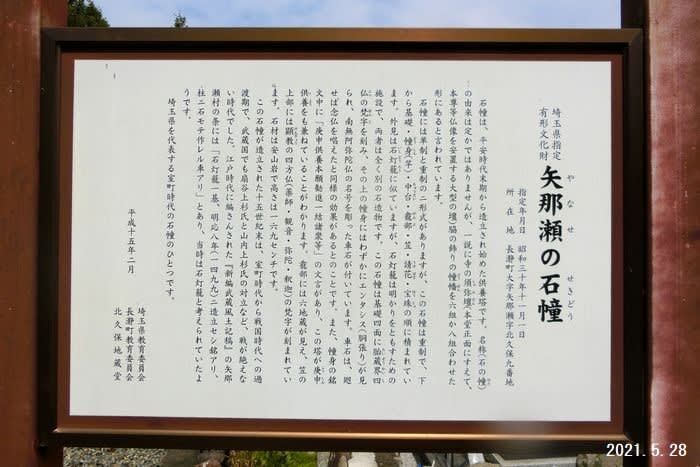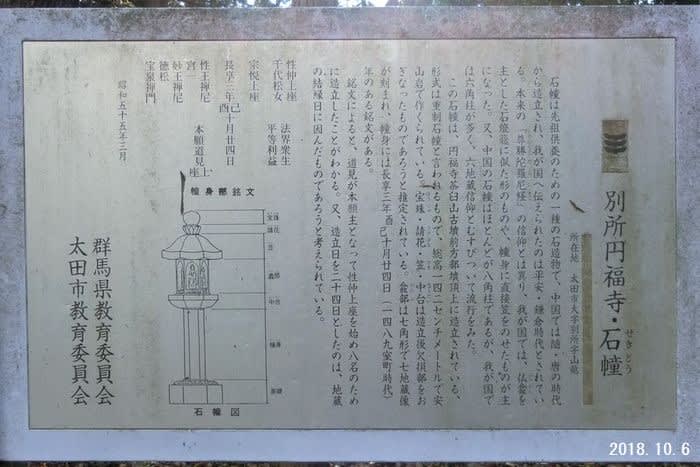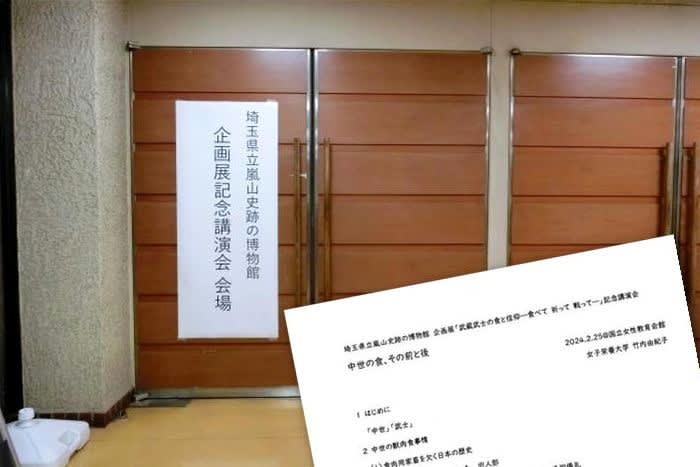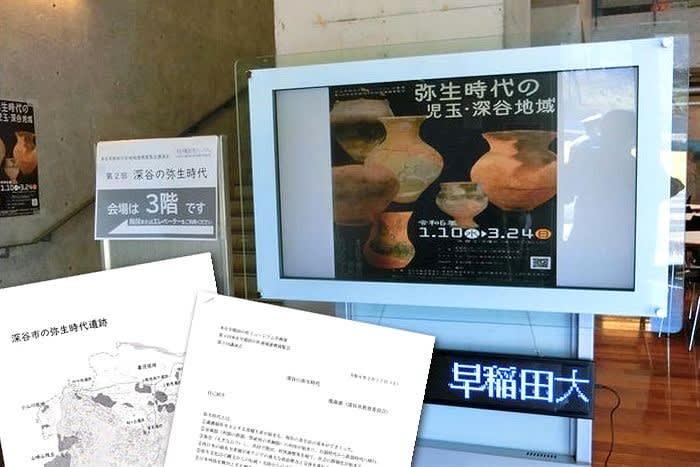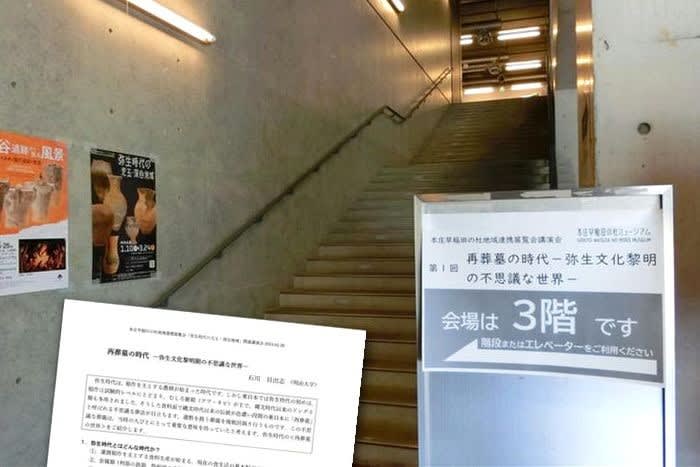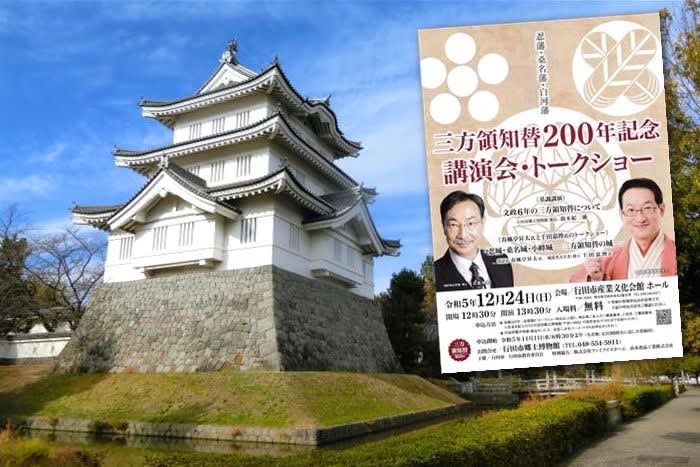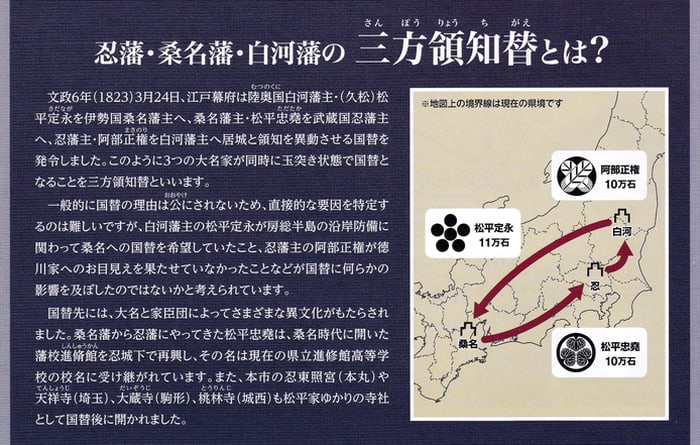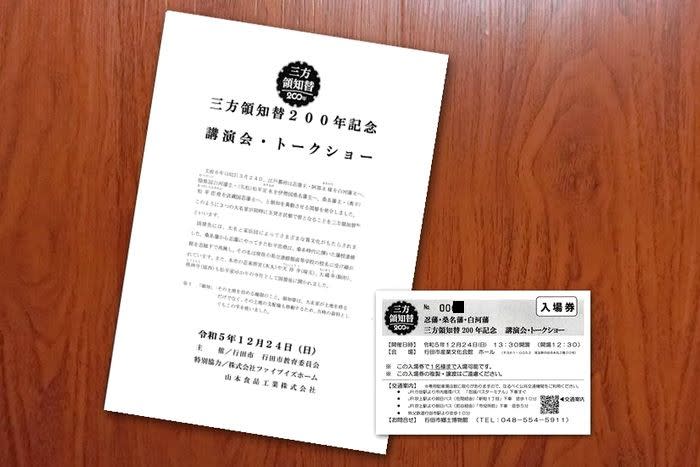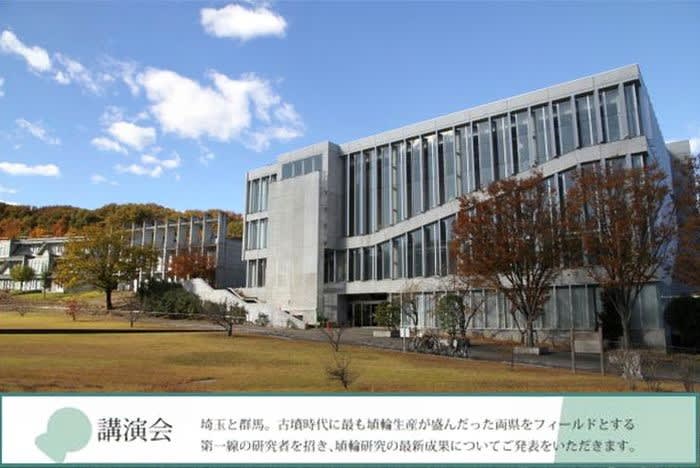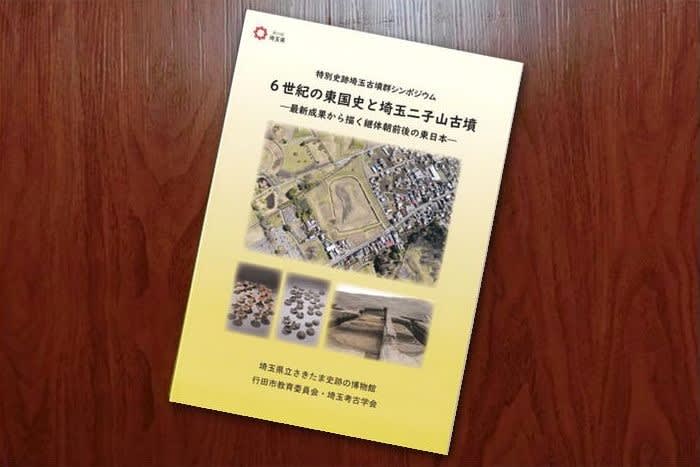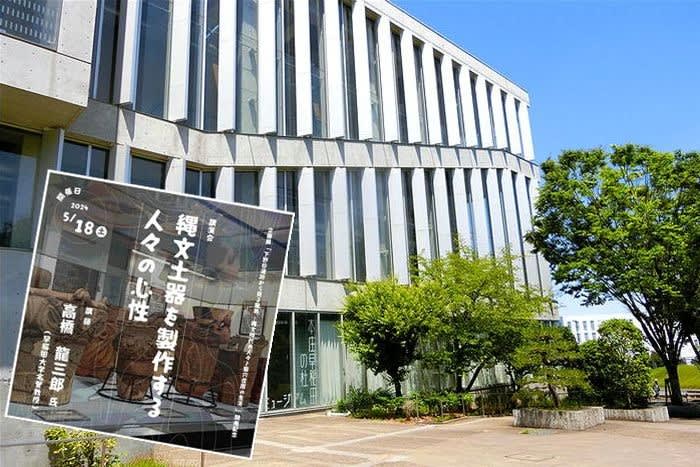
本庄早稲田の杜ミュージアム ミュージアムデー
講演会「縄文土器を製作する人々の心性」
日 時:令和6年5月18日(土) 13:00~14:30
会 場:早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター3階レクチャールーム1(本庄市西富田)
講 師:高 橋 龍 三 郎 氏(早稲田大学名誉教授)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
縄文時代の土器製作者は、一体どのような心性に基づいて土器を製作したのでしょうか。土器型式研究
では余り問われない課題ですが、民族誌を繙くと意外な側面が見えてきます。実際に土器を製作する際
に交錯する心性とはどのようなものなのか、お伝えします。
《本庄早稲田の杜ミュージアム ミュージアムデー》のチラシから
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
を聴講してきました。
毎年5月18日は「国際博物館の日」とのことで、世界中博物館で、5月18日を中心に様々な行事が行われ
ており、本庄早稲田の杜ミュージアム においてもこの 5月18日をミュージアムデーとして、本庄市民俗
芸能上演、ミュージアムコンサートと共にこの講演会が実施されたものです。


講演会資料
聴講日:令和6年(2024)5月18日(土)