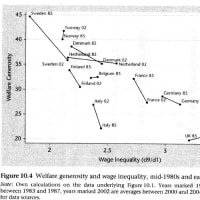Amazon.Frで、アルチュセールの新刊を購入したので、その報告を。購入したのは、Politique et Histoire, de Machiavel à Marx : Cours à l'Ecole normale supérieure de 1955 à 1972 。『政治と歴史、マキャベリからマルクスまで:高等師範学校講義 1955-1972』といった具合のタイトルだろうか。アルチュセールが勤めたエコール・ノルマル・シュープリウールにおける講義録の公刊。講義の録音と、受講生のノートをもとに編集されたもののようである。
。『政治と歴史、マキャベリからマルクスまで:高等師範学校講義 1955-1972』といった具合のタイトルだろうか。アルチュセールが勤めたエコール・ノルマル・シュープリウールにおける講義録の公刊。講義の録音と、受講生のノートをもとに編集されたもののようである。
「講義」と言っても、その中心は、仏において有名なアグレガシオンという教授資格試験のための準備講座の講義のため、彼自身が自らの理論を展開しているというのでは必ずしもないであろう(まだ詳しく読んでいないので)。ただし、無論、そこからも彼自身の主張を引き出すことは当然可能だが。
内容は、17から19世紀の哲学史に関する数章(ヘーゲルとマルクスはここに含まれる)、それからルソー、ホッブス、ロックなどを扱った数章が続く。
教授資格試験のための講座であるがゆえに、主題はその年毎に変わる(指定される)のだが、やはりこれを見ると、アルチュセールは哲学者なのだということを改めて感じる。
アルチュセールは、一方において社会科学的な言説を生産すると同時に、他方においては哲学者然とした言説も残している。アルチュセールにおける、あるいは彼に限らず、より全般的に哲学と社会科学との関係を再考してみる必要があるかもしれない。
ただし、バデュは、アルチュセールは最終的に哲学の中にとどまる内在的な哲学者であると論じているし(「哲学の介入」というアルチュセールのテーゼも、哲学そのものを捨てるわけではない、というのがバデュの考えであろう)、西川長夫先生も、アルチュセールは結局、研究室に閉じこもるタイプの研究者・哲学者ではなかったのか? と考えている。
この西川先生の考えには私も同意見だが、アルチュセールの翻訳に関わったメンバーの間では、意見の違いがある。山家さんは、アルチュセールに関して「細かいところで、チョコチョコやっている」感じがすると述べていたし(フーコーを主に追っている故の考えであろうが)、方や伊吹さんは、もっと活動的な側面を見ようとする。編集でお世話になった保科さんは、「たとえアルチュセールが閉じこもるタイプの研究者であったとしても、それについて我々があれこれ考える必要はまったくない」といったことを言っていた。
いわゆる、「アルチュセーリアン」と呼ばれていた人々は、この点についてどう考えているのだろうか?(ただし、その多くが、こう呼ばれることに嫌悪感を持っていたようだが) これについては、別の機会ででも触れたいと思う。
「講義」と言っても、その中心は、仏において有名なアグレガシオンという教授資格試験のための準備講座の講義のため、彼自身が自らの理論を展開しているというのでは必ずしもないであろう(まだ詳しく読んでいないので)。ただし、無論、そこからも彼自身の主張を引き出すことは当然可能だが。
内容は、17から19世紀の哲学史に関する数章(ヘーゲルとマルクスはここに含まれる)、それからルソー、ホッブス、ロックなどを扱った数章が続く。
教授資格試験のための講座であるがゆえに、主題はその年毎に変わる(指定される)のだが、やはりこれを見ると、アルチュセールは哲学者なのだということを改めて感じる。
アルチュセールは、一方において社会科学的な言説を生産すると同時に、他方においては哲学者然とした言説も残している。アルチュセールにおける、あるいは彼に限らず、より全般的に哲学と社会科学との関係を再考してみる必要があるかもしれない。
ただし、バデュは、アルチュセールは最終的に哲学の中にとどまる内在的な哲学者であると論じているし(「哲学の介入」というアルチュセールのテーゼも、哲学そのものを捨てるわけではない、というのがバデュの考えであろう)、西川長夫先生も、アルチュセールは結局、研究室に閉じこもるタイプの研究者・哲学者ではなかったのか? と考えている。
この西川先生の考えには私も同意見だが、アルチュセールの翻訳に関わったメンバーの間では、意見の違いがある。山家さんは、アルチュセールに関して「細かいところで、チョコチョコやっている」感じがすると述べていたし(フーコーを主に追っている故の考えであろうが)、方や伊吹さんは、もっと活動的な側面を見ようとする。編集でお世話になった保科さんは、「たとえアルチュセールが閉じこもるタイプの研究者であったとしても、それについて我々があれこれ考える必要はまったくない」といったことを言っていた。
いわゆる、「アルチュセーリアン」と呼ばれていた人々は、この点についてどう考えているのだろうか?(ただし、その多くが、こう呼ばれることに嫌悪感を持っていたようだが) これについては、別の機会ででも触れたいと思う。