
それとも柳の鞭でぶちましょか、いえいえそれは・・
今朝の京都新聞のコラム天眼に、哲学者・鷲田清一先生の「金糸雀記」というのがあった。西条八十作詞の童謡「かなりや」(金絲雀記)が紹介されていた。ある程度の年配者には、子供の頃の懐かしい純粋な思いが俄かに込み上げてくる。書かれているように、音楽には、他人の苦しみを自分の苦しみのように抱擁する力がある。この象徴派の詩人は、家族の扶養に懸命の詩業を断念、生計の維持との錯綜の胸の内をこの唄に求めたというのだ。先生には、いちど日本HIS研究センターから講演をお願いした経緯もあり、神妙になって読んだ。
問題は、年配者には響くこの感情豊かな曲の味わいが、今の若い人たちには受け継がれていないことだ。時代は変わるもの。変わるから時代という理屈は当然ではあるが、では、人間がIT機器のように簡単にバージョンアップしてしまえるのか、ということ。それで万事いいのかという素朴ともいえる疑問がここに浮かび上がっている。しかし、それはITやAIといった技術の変革・革新といった従来の変化やニュースの中身ではない。日常の若者とのコミュニケーションの中で、それこそヨヨーッ!としてしまうことが多いのだが。
だが、ここには童謡「金糸雀(かなりや)」の中には、日本人の優しい精神が謳われているのに、真剣な伝承ができていないのではという問題提起がある。講師が最後の授業として考え抜いた講義であったにも関わらず、出席者である若者が「金糸雀(かなりや)」という歌の存在を誰も知らなかったというのだ。目の前の効率優先の結果だとはいえないが、何年かの間に、社会は人間的な配慮を蔑ろにしてきた事例の一つではないだろうか。形式やDATAの比較としてだけが、あたかも唯一正しい評価として処理されてきているきらいがある。
そのズレには、人の心につながる夢や可能性の入る余地・機会が意図されてないのだ。この近年の傾向は、組織間の協働やビジネスのうえでも平気であらわれているように思う。特に会議や連絡といった仕事のコミュニケーションにおいて、いつも亡霊のようにスーッと立ち上がる。発信側も受信側も「見えているだけ」のやりとりで深いところを見ていない。情報があったら文字列(記号)として記号どおりの理解に終わる。もちろん全てがそうであるとは言えないのだが、相互に心からの遣り甲斐に繋がったという確認はできないものだろうか。mitameya20190414
第200回記念・病院広報プランナー(PL)認定実践講座
開講:6月29日(午後)横浜みなとみらい クイーンズタワーA棟 会議室
講師:ジェリイ・フォリ(イメジャス代表)
石田 章一(日本HIS研究センター代表)ほか
詳細・申し込みは、http://www.j-his.jp/
今朝の京都新聞のコラム天眼に、哲学者・鷲田清一先生の「金糸雀記」というのがあった。西条八十作詞の童謡「かなりや」(金絲雀記)が紹介されていた。ある程度の年配者には、子供の頃の懐かしい純粋な思いが俄かに込み上げてくる。書かれているように、音楽には、他人の苦しみを自分の苦しみのように抱擁する力がある。この象徴派の詩人は、家族の扶養に懸命の詩業を断念、生計の維持との錯綜の胸の内をこの唄に求めたというのだ。先生には、いちど日本HIS研究センターから講演をお願いした経緯もあり、神妙になって読んだ。
問題は、年配者には響くこの感情豊かな曲の味わいが、今の若い人たちには受け継がれていないことだ。時代は変わるもの。変わるから時代という理屈は当然ではあるが、では、人間がIT機器のように簡単にバージョンアップしてしまえるのか、ということ。それで万事いいのかという素朴ともいえる疑問がここに浮かび上がっている。しかし、それはITやAIといった技術の変革・革新といった従来の変化やニュースの中身ではない。日常の若者とのコミュニケーションの中で、それこそヨヨーッ!としてしまうことが多いのだが。
だが、ここには童謡「金糸雀(かなりや)」の中には、日本人の優しい精神が謳われているのに、真剣な伝承ができていないのではという問題提起がある。講師が最後の授業として考え抜いた講義であったにも関わらず、出席者である若者が「金糸雀(かなりや)」という歌の存在を誰も知らなかったというのだ。目の前の効率優先の結果だとはいえないが、何年かの間に、社会は人間的な配慮を蔑ろにしてきた事例の一つではないだろうか。形式やDATAの比較としてだけが、あたかも唯一正しい評価として処理されてきているきらいがある。
そのズレには、人の心につながる夢や可能性の入る余地・機会が意図されてないのだ。この近年の傾向は、組織間の協働やビジネスのうえでも平気であらわれているように思う。特に会議や連絡といった仕事のコミュニケーションにおいて、いつも亡霊のようにスーッと立ち上がる。発信側も受信側も「見えているだけ」のやりとりで深いところを見ていない。情報があったら文字列(記号)として記号どおりの理解に終わる。もちろん全てがそうであるとは言えないのだが、相互に心からの遣り甲斐に繋がったという確認はできないものだろうか。mitameya20190414
第200回記念・病院広報プランナー(PL)認定実践講座
開講:6月29日(午後)横浜みなとみらい クイーンズタワーA棟 会議室
講師:ジェリイ・フォリ(イメジャス代表)
石田 章一(日本HIS研究センター代表)ほか
詳細・申し込みは、http://www.j-his.jp/


















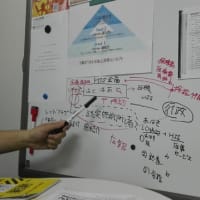

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます