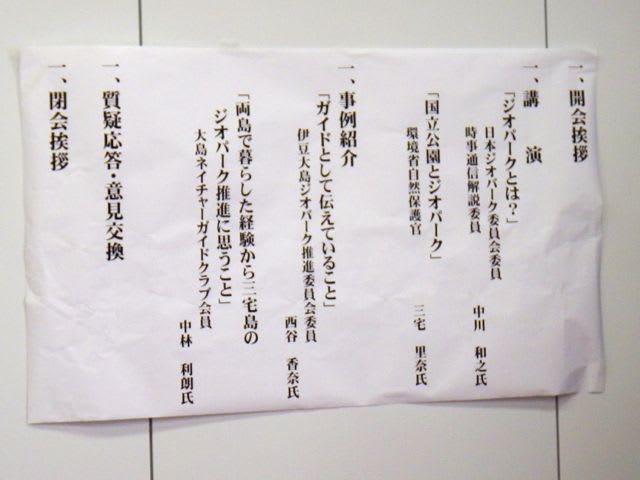昨日の夜、磐梯山ジオパークと洞爺湖有珠山ジオパークから講師を呼んでの講座が開催されました。講師は、磐梯山エコツールズム協会会長の伊藤さんと洞爺ガイドセンター代表の小川さん。
お2人とも、雪国に暮らすアウトドアガイドです。
昨日の船到着後の2時間と、今日1日(船が出るまで)一緒に大島を歩きました。
有珠山は2000年に、磐梯山は明治時代に噴火した活火山で、大島よりも粘りのある溶岩を噴き出します。なので同じ火山でも見られるものは、ずいぶん違います。
「普段見られないものを見てもらおう」と考えました。
まずは赤い溶岩の丘へ。

小川さん、何を撮っているのでしょう?
こんな感じ?

いや、きっともっと素敵に撮っているに違いありません。(見たい…)
何しろ、とても素敵な写真を撮る方なのです。
(小川さんのHPのギャラリーはこちら。http://www.toya-guide.com/gallery/)
巨大バームクーヘン。

初めて見る構え方!
どんな構図の写真なんでしょう~(気になる)
黒い砂浜。

昨日はかなりな引き潮で、砂浜に丸い石が出て来ていました。
石が太陽に照らされて輝いて見えました。(キレイでした~)
そして…
お2人を歓迎するかのような、面白い夕日。

まるで舌をだして笑っている人の顔みたいでした。
そして、今日。
総勢8名で山を目指しました。
道中、寄り道して椿鑑賞。

磐梯山も洞爺湖も大島よりずっと寒いので、常緑の椿を見てもらおうと思ったのです。
華やかに花がついている木もありましたが…
雪の重みで折れたと思われる木も、何本もありました。

“大雪”の影響は,ここでも…。
三原山もすっかり「雪の山」になっていました。

この間、雪だるまを作った時より、雪が厚かったです。
お2人は、雪かきをしていた町役場の方達のスコップを借りて“雪かき”のコツを伝授したり…

雪山(?)の登り方を伝授したりと、本領を発揮されていました!

せっかく遠くから来てもらったので、ジオパーク展にある三原山の写真の前で記念撮影。

なんだか寒そうなんですけど…(?)
一般のお客様に混ざって、バーチャルジオツアーも見ていただきました。
ケンボーダイビングの佐藤さんの語りに、みなさん聞き入っていました。

10数人のガイドでジオを語っているこの“山頂ジオパーク展”も、今年で4年目に入りました。
ガイドがそれぞれ、自分の持っているジオ素材(溶岩や映像など)を持ちよって、行くたびに少しずつ変わっているのがとても楽しいです。
今日は“ハート形のマグマ”を見つけました!

室内に溶けたマグマ!?
はたしてこのハート型の正体は?
これです。

一緒にいたジオ研のメンバーが「これを見て『ハートに見える』というお客様が多いので、敷物を作ってみたんです。」と教えてくれました。なんてナイスなアイデアでしょう!
こんな手作り感あふれる空間をみんなで作れるなんて、やっぱりジオパークって楽しいです。
誰かにやらされるのではなく、みんなの持ち寄りアイデアや"気持ち”が少しずつ、形をつくっていきます。
雪の三原山を下りた後は、島の南部へ。

みんなで語りながら楽しく歩きました。
伊藤さん、小川さん,ありがとうございました
今度は雪のない大島を、ぜひまた歩きにいらしてください~。
(講習の様子は近日中に報告します)
(カナ)
お2人とも、雪国に暮らすアウトドアガイドです。
昨日の船到着後の2時間と、今日1日(船が出るまで)一緒に大島を歩きました。
有珠山は2000年に、磐梯山は明治時代に噴火した活火山で、大島よりも粘りのある溶岩を噴き出します。なので同じ火山でも見られるものは、ずいぶん違います。
「普段見られないものを見てもらおう」と考えました。
まずは赤い溶岩の丘へ。

小川さん、何を撮っているのでしょう?
こんな感じ?

いや、きっともっと素敵に撮っているに違いありません。(見たい…)
何しろ、とても素敵な写真を撮る方なのです。
(小川さんのHPのギャラリーはこちら。http://www.toya-guide.com/gallery/)
巨大バームクーヘン。

初めて見る構え方!
どんな構図の写真なんでしょう~(気になる)
黒い砂浜。

昨日はかなりな引き潮で、砂浜に丸い石が出て来ていました。
石が太陽に照らされて輝いて見えました。(キレイでした~)
そして…
お2人を歓迎するかのような、面白い夕日。

まるで舌をだして笑っている人の顔みたいでした。
そして、今日。
総勢8名で山を目指しました。
道中、寄り道して椿鑑賞。

磐梯山も洞爺湖も大島よりずっと寒いので、常緑の椿を見てもらおうと思ったのです。
華やかに花がついている木もありましたが…
雪の重みで折れたと思われる木も、何本もありました。

“大雪”の影響は,ここでも…。
三原山もすっかり「雪の山」になっていました。

この間、雪だるまを作った時より、雪が厚かったです。
お2人は、雪かきをしていた町役場の方達のスコップを借りて“雪かき”のコツを伝授したり…

雪山(?)の登り方を伝授したりと、本領を発揮されていました!

せっかく遠くから来てもらったので、ジオパーク展にある三原山の写真の前で記念撮影。

なんだか寒そうなんですけど…(?)
一般のお客様に混ざって、バーチャルジオツアーも見ていただきました。
ケンボーダイビングの佐藤さんの語りに、みなさん聞き入っていました。

10数人のガイドでジオを語っているこの“山頂ジオパーク展”も、今年で4年目に入りました。
ガイドがそれぞれ、自分の持っているジオ素材(溶岩や映像など)を持ちよって、行くたびに少しずつ変わっているのがとても楽しいです。
今日は“ハート形のマグマ”を見つけました!

室内に溶けたマグマ!?
はたしてこのハート型の正体は?
これです。

一緒にいたジオ研のメンバーが「これを見て『ハートに見える』というお客様が多いので、敷物を作ってみたんです。」と教えてくれました。なんてナイスなアイデアでしょう!
こんな手作り感あふれる空間をみんなで作れるなんて、やっぱりジオパークって楽しいです。
誰かにやらされるのではなく、みんなの持ち寄りアイデアや"気持ち”が少しずつ、形をつくっていきます。
雪の三原山を下りた後は、島の南部へ。

みんなで語りながら楽しく歩きました。
伊藤さん、小川さん,ありがとうございました
今度は雪のない大島を、ぜひまた歩きにいらしてください~。
(講習の様子は近日中に報告します)
(カナ)