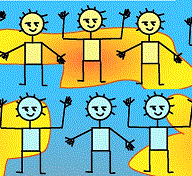今日(10月18日)の朝日新聞《オピニオン&フォーラム》、『「失敗」を直視せよ 原発事故の真相が解明されないまま「安全神話」は続く』は、突っ込みが弱い。インタビュー記者の大牟田徹が悪いのか、元政府事故調委員長・東京大学名誉教授の畑村洋太郎が逃げているのかわからない。しかし、一般論から言うと、人は自分に都合が悪い事実をごまかしがちで、ジャーナリストはそれに切り込むべきである。
2011年の福島第一原発事故の後、高校の同窓会の連絡で、原発廃止を書き込んだら、日立に務めた同窓生から、文句がとんできた。技術には失敗がつきもので、失敗から学んで問題を克服すればよいのであって、原発廃止とはけしからんと、いうものだ。
畑村洋太郎は、「失敗を直視せよ」で何の失敗を解明し、何をしたかったのだろうか。なぜ、彼は、「再現実験」にこだわったり、「自分が原子力の門外漢である」ことに悔いたりするのか。失敗は、技術の進歩のためのコストだという考えにとらわれていたのではないか。
原子力発電は日本の技術ではない。単にアメリカから買ってきた技術である。それに原子力発電も大した技術ではない。畑村洋太郎は「自分が原子力の門外漢」と言うが、原子力発電は色々な技術の寄せ集めであって、原子核分裂連鎖反応の知識だけでできているのではない。
原子力発電とは、要は、大規模プロジェクトを組み、いろいろな技術の専門家を集めて、発電装置を設計し、製造し、運用するというものである。ジェット旅客機の設計、製造、運用をちょっと複雑化したものだが、日本政府や国際機関の安全に対する監視・規制が、原発は旅客機ほど機能しなかったということである。
だから、政府事故調の目標が、原発事故の技術的解明よりも、事故の実態を記録し、保存し、公開することを第1の目標に置くべきで、「失敗学」が技術革新に有効であることを立証するためではない。
事故関係者は、自分にとって不都合な事実を隠蔽しようするから、その意味では、関係者に率直に打ち明けてもらうことで再発防止の鍵を探る「失敗学」も有効そうに見える。しかし、じっさいには、嘘がつけないように、傍証を固めていく手法が必要だったのではないか。司法取引のようなことで、会社に忠実な職員や役員から本当のことが聞けると思えない。
たとえば、原発を知る私の友人たちは、福島第1原発の所長、吉田昌郎が原発に無知で、事故処理に落ち度があったため、重大事故に発展した、と疑っている。しかし、いまや彼は死人で、会社の秘密をもって墓場に行ってしまった。
原発事故は、ジェット旅客機の事故より、影響の空間的時間的範囲が大きい。それにもかかわらず、原発を推進してきた経済産業省が、原発の認可、監視を担当している。経済産業省は原発の推進を行うということ自体が誤りで、特定の産業育成に政府が加担していることなる。推進は原子力メーカに任せるべきである。経済産業省は、認可・監視業務だけでなく、原発事故調査を常設し、小さな事故でも、普段から自分の力で調査すべきである。
原発を推進するというような誤りを経済産業省が起こすのは、日本が原子爆弾の保有国になる潜在的技術力を確保しようという たわけたことを自民党が思っているからだ。原発事故直後に、原発維持の理由として、じっさい、ある自民党議員がテレビでそう語っていた。
日本が原発を買ってきただけで、設計にかかわっていないことは、原発の位置からしてわかる。海面から高い位置に原発を設置すれば、防潮堤を作らなくても、津波の被害から免れる。一本のポンプで水を引き上げられる高さは限界があるが、途中に貯水池を置けば、いくらでも引き上げられる。日本全国の原発は、わざわざ、岩盤を削って、一本のポンプで水が引き上げられる位置にしている。また、配電盤など水に弱い設備の防水が甘い。設置場所の比較的自由なディーゼル非常電源を高台に置かない。
日本は原発の設計にかかわらなかったが、製造では部分的に下請けしている。その意味で、本当に設計基準を満たしていたか、を調査しなければならない。事故では、冷却水を失っていた原子炉から放射性物質を含むガスがぷかぷか吹き出ていた。これは、設計が容認していた範囲なのか、製造技術の問題なのか、わかっていない。
畑村は、「福島第一原発の事故では1号機の非常用復水器が作動しなかったことが悲劇を招きました」と言う。じつは、事故直後に、私の友人も同じこと言っていた。原発技術者には常識のことらしい。作動しなかったことは、無知のゆえなのか、それとも、別の事情があってできなかったのか、をも解明する必要がある。原子炉の鋼鉄は、古くなるともろくなる。それに、非常用復水器を作動させ、急冷させたとき、原子炉の鋼鉄にひびがはいることはなかったのだろうか。
現在、福島第1原発の原子炉は、放射線レベルが高くて、近づいて詳しい調査ができない。それでも、同じタイプの原子炉は日本のいろいろな場所にある。ジェット旅客機の重大事故があると、いっせいに、同じタイプの旅客機が検査される。日本の原発では、これがない。日本政府は電力会社の自己申告書を受け取るだけである。日本政府は、安全を点検せず、世界で一番厳しい安全規制を行っていると平気でウソを言う。
「安全神話」とかいう問題ではない。単に自分利益のために他の人の不幸に無関心であるだけである。原発の安全性も必要性も疑わしい。
そして、関西電力の原子力本部長が地元の助役や調達企業からお金をもらっていて、平然としている。
日本政府と電力会社と原子力メーカが一体となって腐りきっている。技術以前の問題から解決しないとだめだろう。
朝日新聞の『「失敗」を直視せよ』は、「18日からNHKで始まるドラマ『ミス・ジコチョー』」の宣伝にすぎないように思えてくる。