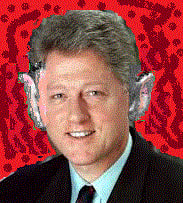岩波文庫の『完訳 アンデルセン童話集 1』の最初の物語は『火打箱』である。
私がこれを最初に読んだのは、カバヤ児童文庫である。5つ上の兄がカバヤ児童文庫をそろえていた。1952年から1954年にかけて、岡山市のカバヤ食品(株)がキャラメルのおまけように児童文学の本を出していた。カバヤのキャラメルを買ってその箱にはいっている文庫券をいくつか ためて送ると、本が送られてくるのだ。
カバヤ児童文庫は、いまはデジタル化され、ネット上で『火うちばこ』も読むことができる。
ところで、きのう、たまたま、『火打ち箱』が「悪人がハッピエンドとなる童話」という読者感想文をネット上でみた。私が小学校低学年で読んだとき、主人公の兵隊さんが、悪人だとは思わなかった。当時の私のイメージでは、戦争から帰って身も心もボロボロになった可哀そうな兵隊さんが、やっとつかんだ幸運の物語であった。
アンデルセンの童話には「勧善懲悪」のところがまったくない。リアリストなのである。貧しい人は貧しいままに死ぬのである。神は助けてくれない。デンマークの当時の現実をそのまま童話のなかに閉じこめているのだ。
そのアンデルセンの童話のなかで、珍しく、ハッピエンドなのが『火打箱』なのだ。
主人公の兵隊さんを悪人だと思う人がいるのは、醜い婆さんの頼みで木のほらの奥から「火打ち箱」をとってきたあと、その用途がなにかに答えない婆さんを兵隊さんが切り殺すからである。なんのためらいもなく切り殺すのである。すなわち、乱暴者なのである。
さて、戦争からの復員途中の兵隊さんが身も心もボロボロだと幼い私が思いこんだ根拠は、現在、読み返すと、『火打箱』にはほとんどない。数少ない記述をあげると つぎのようになる。
醜い婆さんを切り殺した後、近くの町の宿屋に泊まるが、その下男が、お金をたくさんもっているのに、靴がボロボロなのを いぶかしく思うとの記述がある。これは、主人公を凱旋した兵士ではないことを思わせる。
さらに、町の美しい姫様は「身分の卑しいただの兵士」と結婚するという予言のため、誰とも会うことのないよう、塔の奥深くに閉じこめられている。その話を聞いて「兵たいは、ちょっとぎくりとしました」とある。だから、主人公の兵隊さんは「身分の卑しいただの兵士」なのだ。
もう1つの記述は、その兵隊さんが、もともと貧乏だったので、お金のないことの苦しさがよくわかり、木のほら奥深くからとってきた金貨を惜しみなく貧しい人に与えたとある。
これらの記述から、私は、哀れな復員兵と思ったのだと思う。
絵本などでは、復員途中の兵士にもかかわらず、きれいな服を着ている。王様の近衛兵のように着飾っているが、これは アンデルセンが抱いていたイメージとは違うのではないか。
物語では、主人公の兵隊さんは、木のほら奥深くから持ち出した金貨をすべて使い果たして、屋根裏部屋に移動し、明かりもないので、火をともそうとして火打ち箱の石を打つと、3匹の大きい犬が現れる。
岩波文庫によれば、1番目の犬は紅茶カップの受け皿のような大きい目をして、2番目の犬は水車の輪のような大きな目を、3番目の犬は丸い塔のような大きい目をしている。カバヤ児童文庫では、2番目の犬はお盆のような大きい目をしており、3番目の犬はテーブルのような大きい目をしている、とあり、ここは違う。カバヤ児童文庫以外は、岩波文庫と同じ訳になっているので、岩波文庫の訳が正しいのだろう。
さて、兵隊さんは、3匹の犬に命令して、木のほら奥深くから金貨・銀貨・銅貨を持ち出す。
そのうちに、兵隊さんは、塔に閉じこめられた姫を犬に連れ出さす。それがバレてつかまり、絞首刑になる。死ぬ前にタバコを吸いたいと言って火打ち箱の石を打つと、3匹の犬が現れ、主人公を救うため、暴れる。兵士たちや王や妃に噛みついたり、宙に放り投げたりする。
岩波文庫では、このとき、恐れた兵士たちが、主人公に「王様になってください」と言う。カバヤ児童文庫だけが、王様が「王様になってください」ということになっている。
ここでも、私は岩波文庫が正しいと思う。王も妃も3匹の犬に殺されたのだ。
そして、町のみんなが、身分の卑しい兵隊さんが美しい姫様と結婚することに、喜んだという。
この童話は、珍しく、アンデルセンの本音がでていると思う。――権力者は犬にかみ殺されればよい。
[補注]アンデルセンの生きていた頃の最初の戦争は、デンマークが、ナポレオン側にたって、ドイツ・オーストリア連合と戦い、負けている。その後も、ドイツと2度戦っているが、2度とも負けている。アンデルセンは、敗戦で ひとり帰ってくる、兵士をイメージしていたと思う。しかも、戦争から解放されて、心ウキウキして、オイチニ、オイチニと手を振りながら歩く兵士である。
☆蛇足☆(眞子さまの結婚の日が決まったとのこと)