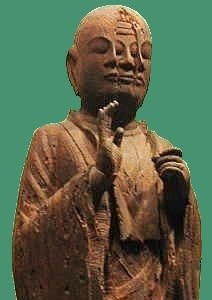森本あんりの『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)を何度も読み返すうちに、疑問が生じた。アメリカが「平等の国」ということと、「プロテスタントの建国した国」であることとが矛盾するのではないか、ということである。
森本あんりはカルヴァン派をプロテスタントの本流ととらえている。しかし、カルヴァン派は人間が不平等に作られているというドグマ、予定説をもつ。カルヴァンによれば、神の救済にあずかる者と滅びに至る者が、あらかじめ決められているとする。人間は神の前で平等でないのだ。
マックス・ウェーバーは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(岩波書店)で、金持ちがますます金持ちになることが正しいと主張している。彼の言うプロテスタンティズムはカルヴァン派のことである。カルヴァン派は、欲望のための際限のない欲望を肯定するブルジョアジーのためのキリスト教の1セクトではないか。
私の疑問は、宇野重規が『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ)で主張する、平等の国アメリカと矛盾するのではないか、ということである。
森本あんりは、『反知性主義』の第3章に、つぎのように書く。
《実のところ、植民地時代のアメリカは、何とかして「神の前での平等」が「社会的な現実における平等」という現実に直結しないようにと、必死の努力を続けていたのである。もし万人が社会的平等を主張したなら、上に立つ者の権威はどうなってしまうのか。政府や王や教会を敬う人はいなくなり、体制転覆の革命が起き、アナーキー(無政府状態)が生じるのではないか。これが彼らの恐れていたことだった。》
このアナーキーを恐れていた「彼ら」は、アメリカで支配者の立場にたった裕福なプロテスタント、カルヴァン派ではないか。彼らは、「神の前での平等」さえ、否定していたのではないか、という疑念である。
裕福なプロテスタントに搾取されたプロレタリアートこそが「平等」を求めたのではないか。字が読めず、英語も話せない、無学の貧しい移民が「平等」を求めたのではないか。
キリスト教はもともと字も読めない無産階級(プロレタリアート)のものだった。新約聖書は金持ちへの怒りに満ち満ちている。しかし、彼らは、金持ちの施しによってしか生きていけない弱みを抱え、金持ちたちを皆殺しにできなかった。
歴史的には、キリスト教徒は財産の共有を求める叛乱を何度も何度も起こしている。『使徒行伝(Πράξεις τῶν Ἀποστόλων)』の5章1節から11節は、キリスト教徒の共同体に自分の財産を正直にすべて捧げなかった金持ちアナニアとその妻を使徒ペテロが殺したという話しである。
カルヴァン派だけがプロテスタントではない。カルヴァン派から急進派と忌み嫌われたアナバプテストやクエーカーやメソジストがいる。彼らが「平等」を求めたのではないか。
新約聖書には「神の前の平等」なんて書いてない。『マルコ福音書』『マタイ福音書』『ルカ福音書』『ヨハネ福音書』には、単に、あなたがたは偉そうにするな、人々に仕えよ、とイエスが使徒たちに言ったと書いてある。すなわち、キリスト教徒の間に上下関係があってはならない。これが、ヨーロッパからアメリカに逃げてきた人々の求めた「平等」ではないか。
それを裕福な人々は抑え込もうとして、カルヴァンの「予定説」を利用しただけではないか。「神の前での平等」が「社会的な現実における平等」という現実に直結しないようにと、必死の努力を続けているのは、森本あんり自身ではないか、という疑念を私はもつ。
同じように、「機会平等」は現実の「不平等」を肯定するためにウソではないか。
森本あんりはカトリックをバカにしてつぎのように書く。
《プロテスタント教会には、カトリックのような修道院も存在しない。修道士として出発したルターは、あえて元修道女と結婚し、世俗社会に暮らす者にも修道者と同じように神に仕える道があることを示した。》
修道院は、貧富の差がある現実の社会を否定し、自分で自分の食べるものを作り、搾取を否定する者たちの集まりである。カウツキーによれば、修道院も土地があるから自活できるのであり、豊かな収穫が得られるようになると、共有と平等を否定する「組織としての教会」が動き出し、上下関係を否定する修道士を抑圧し、蓄えた富を奪い取る事態となる。「カトリックのような修道院」に、悪意に満ちた森本あんりの偏見を感じる。修道院自体は何も悪くない。
反知性主義とは、難解な知識で飾り立てた権威に反発する直観である。それを「熱病」と断定するのではなく、反知性主義の背後にある真実「不平等の存在」を弾劾しないといけない。アナーキーは何も悪くない。