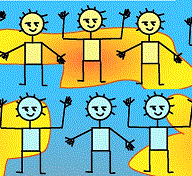経済協力開発機構(OECD)が11月3日に発表した学習到達度調査(PISA)の結果で、日本は「読解力」が15位となり、前回調査の8位から後退したことが、なにか、トンデモナイことかのように、メディアで報道されている。
冷静になって、OECDとは何か、PISAとは何か、「読解力」と何か、そんなに悪い結果だったのかを考えないと、経済産業省の「脱ゆとり教育」「PCを使いこなす教育」にだまされてしまう。
NHKは、このニュースの報道に次のようなコメントをつけている。
〈日本の教育政策はこの国際学力調査に大きく影響を受けてきました。2003年には、順位が下がったことがPISAショックといわれ、それまでの「ゆとり教育」から「脱ゆとり教育」へと転換し、授業時間や教える内容の増加、さらに、全国学力テストの復活にもつながりました。〉
NHKが言っているように、日本政府は、16年前に すでに、「脱ゆとり教育」に舵を切っているのだ。そして、この間、「読解力」の順位はあがったり、さがったり、している。これは、「ゆとり教育」か「脱ゆとり教育」か、という問題とは関係ない ことを示している。
OECDとは、じつは、国連の組織ではない。1948年4月、冷戦時代に、共産主義国に経済発展で負けないために、西側諸国の経済復興を米国がリードするために、作った組織である。
PISAとは “Programme for International Student Assessment” の略称である。英語では、長期のプロジェクトのことをプログラムという。OECDが行うのは、経済発展を担う労働力の質の調査である。そこで、調査されているのは、実学の能力であり、一般的な学力や教養ではない。
簡単にそれを理解してもらうため、今回の調査でどこがトップグループになったかを見てもらえばわかる。「読解力」のトップは中国内陸部である。2位はシンガポール、3位はマカオ、4位は香港である。アメリカは13位、イギリスは14位、日本は15位、ドイツは20位、フランスは23位、オランダは26位である。別に差別しているわけではないか、なにか変だと思わないか。
それに、日本の「読解力」の得点504点はそんなに悪くない。偏差値になおすと57点である。偏差値とは、平均点を50点に、標準偏差を10点に変換したものである。
世界の人びとは異なる言語を話している。異なる言語を話している人々の言語能力に点数をつけて順位を出すことができるだろうか。不可能だし、比較することは失礼にあたる。
PISAの目的は経済発展を担う労働力の質の調査である。だから、「読解力」とは言語能力のことではない。「読解力」とは、「情報を探し出す能力」、「質問を理解する能力」、「情報を選択し評価する能力」で、特定の言語によらない情報リテラシーなのである。ちなみに、それぞれの日本の偏差値は、順に、54点、57点、55点である。すなわち、問われた質問の答えが書いてある場所を短時間で探しだす能力が54点であったというだけだ。こんなものがイノベーション生む能力と何の関係もない。
OECDのPISAは 先進国にとって もはや時代遅れで、後進国の実学を応援するものである。
こんなことで、「ゆとり教育」か「脱ゆとり教育」かを言い争うなんて馬鹿げている。
それよりも、だいじなのは、(1)簡単で明瞭な日本語を話し書くように教育すること、(2)記憶の無駄使いになる漢字の使用を厳しく制限すること、(3)古文、漢文を選択制にし、かわりに、韓国語、中国語、ドイツ語、フランス語、ロシア語を選択できるようにすること、(4)身分差別社会の遺物、敬語の教育をやめることである。
また、反共のOECDのPISAなんかに教育が かきまわされるのではなく、また、時代遅れの道徳教育なんか行うのではなく、国連が推奨しているLife Skill教育を実施すべきである。
Life Skill教育は、個人の権利を政府や多数派から如何にまもるかの生きる技術を教えるものである。いじめや不登校やうつの原因は対人関係のつまずきから起きることが多い。Life Skill教育は市民社会での対人関係を良好に保つ技術をも教える。