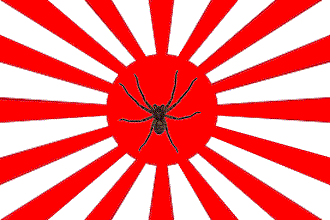
今年の12月8日は日米開戦から80年になる。この機会に、日本人がなぜ戦争に突入したのか、かえりみたい。
日本人がすべて戦争したかったわけではない。無教会派の矢内原忠雄が戦争に反対した。徴兵されたエホバの信徒が銃をもって人を殺すことに逆らった。小学校もでてない私の祖父(母の父)も戦争に反対した。彼はキリスト教徒ではなく、日蓮宗の門徒であった。
教養があってもなくても戦争に反対した人々がいるのである。
日清戦争、日露戦争、日中戦争、日米戦争と戦争に明け暮れた戦前の日本は、別に、国民に戦争をしましょうか、と尋ねたわけではない。国会が開戦に同意したわけでもない。天皇が戦争に同意すれば、政府が戦争できたわけである。
いっぽう、古代ギリシアでは、直接民主主義がとられており、参加の意思のある者が民会(エクレシア)に集まり、多数決で戦争するかどうかを決めた。そこに集まった市民は、農夫であったり、革職人であったり、船大工であったりして、多くは字の読み書きができなかった。
天皇制がなければ、戦争をすることがなかった、とまでは言えないが、国民の意思を尋ねない体制が、少なくとも、戦争の1つの要因であったことは間違いがないと思う。
私は、日本が戦争に突入した要因をつぎのように思う。
(1)暴力で一部の人間による明治維新が成功した。
(2)天皇ただひとりがすべての権力を握るとする大日本帝国憲法が定められた。
したがって、私は昭和にはいって軍人が暴走したというような考え方をとらない。明治維新ですべての誤りの種がまかれ、1890年(明治23年)に成立した大日本帝国憲法がそれを固定したのだと思う。
尊王攘夷運動の引き起こした明治維新は、「強い日本」「天皇のもとの一体化」と誤った教条を政治の中心に据えた。
本当は、日本が軍事大国になる必要はなかったのである。他国を侵略する必要はなかったのである。天皇制もいらなかったのである。権力をだれかに集中する必要もなかったのである。
現在の日本は、「法の下の平等」を掲げながら、例外としての皇族を認めている。そして、自民党政権は、憲法の解釈の変更を重ねながら、首相の権力を強めている。今年の8月、内閣はアフガニスタンに国会の承認なく自衛隊機を派遣した。これは、安倍政権が安保関連法の改正(2016年)の実施にあたる。
さらに防衛費(軍事費)を従来のGNP比1%から2%に引き上げることを、今回の衆院選で自民党の公約に掲げている。
明治以降の日本の過ちを、いま、繰り返していいはずはない。日本は「強い大国」ではなく「みんなが平等の民主主義の国」であればよいのだ。












