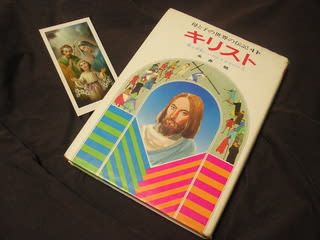ある晴れた日のカトリック八王子教会
(住所:東京都八王子市本町16-3)
(住所:東京都八王子市本町16-3)
稲川圭三神父が麻布教会へ異動されてから、約3ヶ月が経った。「キリストを信じるすべての者よ・・・」。八王子教会で「復活の続唱」を先唱された稲川神父の歌声が、今も私の耳に残っている。一昨年、私は精神的な苦しみから教会へ通うようになったが、八王子教会で初めての主日ミサに与って以来、稲川神父の説教に強く惹かれた。毎回の朗読箇所から、埋もれた宝のような「神さまが共にいてくださる神秘」に光を当て、福音を宣べ伝えられていた。
ある朝ミサの時であった。その頃、私は聖体拝領になると、自席に留まっていた。それは神の御前に立つという畏れ(注)と、未信者は席で待つべきものという幼少時の記憶によるものである。その日も私は席にいた。すると、聖体拝領を終えられた信徒の方から、「神父様が、どうぞ祝福をお受けくださいと仰っていますよ。せっかくお見えになったんだからって」との伝言をいただいた。 私は徴税人ザアカイのように歓喜すると共に、自分の頑なな態度を恥じた。
麻布教会へ異動される直前、稲川神父の説教集「神さまが共におられる神秘」に続き、「神さまのまなざしを生きる」が出版された。稲川神父の説教は「原稿なし」のため、信徒の方が録音を文字に起こすことを望み、それが書籍化されたもの。私は本書を読むたびに、稲川神父が説教を自ら手話で同時通訳されたり、土曜の主日ミサで子どもたちと一緒に歌われていた姿が甦る。「神さまは共におられます。わたしと共におられ、あなたと共におられます」。

<カトリック八王子教会聖堂>
(注):プロテスタント系の高校時代、神は私にとって厳父のような存在であり、聖書は絶対の戒律として読んだ。学校側の「やや偏った」宗教教育の影響だろう。先月、私は武蔵豊岡教会(日本基督教団)の主日礼拝に参列して、プロテスタントの敬虔な祈りを初めて知った。
◆主な参考文献など:
「神さまが共におられる神秘」 稲川圭三著(雑賀編集工房・2012年)四六判・178頁。説教17編を収録。
「神さまのまなざしを生きる」 稲川圭三著(雑賀編集工房・2012年)A5判・298頁。説教70編を収録。