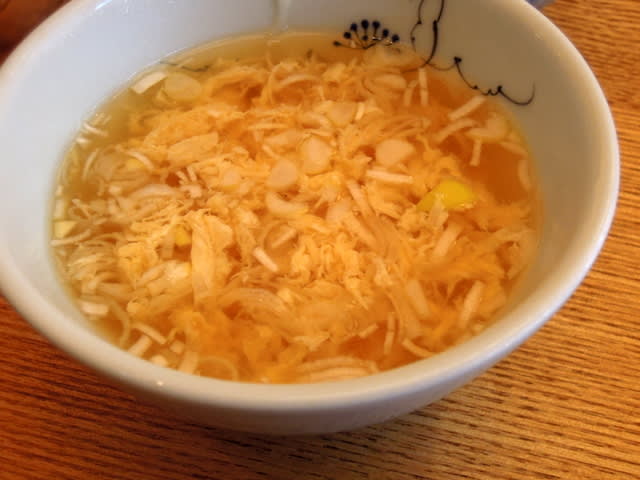イチゴが高価である。
イチゴ狩りに行って分かったのだが、温室栽培といえども最近は寒波襲来で低温状態が続いており、イチゴが色づいていないのである。

行ったのは、千葉県の山武成東(さんぶなるとう)地区のイチゴ街道である。
この街道一帯でも、イチゴ狩りを中止しているイチゴ園が多いのであった。
「本日終了」の看板が目立つのであった。
行ったイチゴ園では、花の摘み取りなどもあるようだけれど実際には花はやっていなかった。
花の摘み取りは、館山まで行かなければならないのである。
イチゴを食べ、花を摘み取るという至福の時間は経験出来なかった。
残念である。

確かに色づきは悪かった。
だがしかし、良く吟味して歩いていると前の方の取り残しが結構あってお腹一杯になったのであった。

休園しているイチゴ園が多いので、客は殺到するといった按配である。

いま客を入れているハウスは、一棟のうちの半分。
この写真で言えば、手前のエリアだけであった。
イチゴが無くなってしまう訳である。
写真を見て頂ければ分かるけれど、赤味が少ない。
ハウスに入って「わあ~っ!」と歓声が上がることは無い。

このイチゴ園は、10棟以上のハウスがあった。
ここはまだ客を入れていないけれど「高設」式のハウスである。
胸の高さ、腰の高さにイチゴがある。
車いすの方や、子どもに喜ばれるのであるけれど色づきが悪く、客を入れるのは3月中旬頃になると言う。
やはりハウス全体の色合いが悪いのである。
でも・・・このイチゴ園は気持ち良かった。
時間制ではあるけれど・・・30分食べ放題であるけれど、時間を気になさらないで「お腹がいっぱいになるまでどうぞ!」と言ってくれた。
確かに、30分などと言う必要は無いのである。
現実には30分も食べていられないのである。
「お腹がいっぱいになるまでどうぞ!」は嬉しい一言である。

ぼくは再来することを約してこのイチゴ園を辞したのであった。
お腹も心も満腹であった。
緑川いちご園 TEL 0475-82-4304 である。
山武成東インターで下車、一般道に出たら左折して「JA緑の風」を過ぎ、道なりに行けば右手にある。
 にほんブログ村
にほんブログ村
荒野人
イチゴ狩りに行って分かったのだが、温室栽培といえども最近は寒波襲来で低温状態が続いており、イチゴが色づいていないのである。

行ったのは、千葉県の山武成東(さんぶなるとう)地区のイチゴ街道である。
この街道一帯でも、イチゴ狩りを中止しているイチゴ園が多いのであった。
「本日終了」の看板が目立つのであった。
行ったイチゴ園では、花の摘み取りなどもあるようだけれど実際には花はやっていなかった。
花の摘み取りは、館山まで行かなければならないのである。
イチゴを食べ、花を摘み取るという至福の時間は経験出来なかった。
残念である。

確かに色づきは悪かった。
だがしかし、良く吟味して歩いていると前の方の取り残しが結構あってお腹一杯になったのであった。

休園しているイチゴ園が多いので、客は殺到するといった按配である。

いま客を入れているハウスは、一棟のうちの半分。
この写真で言えば、手前のエリアだけであった。
イチゴが無くなってしまう訳である。
写真を見て頂ければ分かるけれど、赤味が少ない。
ハウスに入って「わあ~っ!」と歓声が上がることは無い。

このイチゴ園は、10棟以上のハウスがあった。
ここはまだ客を入れていないけれど「高設」式のハウスである。
胸の高さ、腰の高さにイチゴがある。
車いすの方や、子どもに喜ばれるのであるけれど色づきが悪く、客を入れるのは3月中旬頃になると言う。
やはりハウス全体の色合いが悪いのである。
でも・・・このイチゴ園は気持ち良かった。
時間制ではあるけれど・・・30分食べ放題であるけれど、時間を気になさらないで「お腹がいっぱいになるまでどうぞ!」と言ってくれた。
確かに、30分などと言う必要は無いのである。
現実には30分も食べていられないのである。
「お腹がいっぱいになるまでどうぞ!」は嬉しい一言である。

ぼくは再来することを約してこのイチゴ園を辞したのであった。
お腹も心も満腹であった。
緑川いちご園 TEL 0475-82-4304 である。
山武成東インターで下車、一般道に出たら左折して「JA緑の風」を過ぎ、道なりに行けば右手にある。
荒野人