JSEPTICのホームページの右下にある、このブログのロゴには、
”医学雑誌鑑賞が趣味のDr内野が面白い文献を毎週紹介”
と書いてある。
そもそもこのブログは、JSEPTICのホームページがリニューアルするときにアクティブコンテンツを作ろうということで始まったもので、こんなちょっと恥ずかしめの宣伝文句にした記憶がある。
とは言え、趣味とは言わないまでも文献を読んでいる数は平均よりは多いと思っているのは事実。
で、実は、文献を書いている数も平均よりは多いと思っている。
しかも最近は若者が論文を書く手伝いをすることも多いので、英語で論文を書いて投稿して採用される困難についてはそれなりに経験があるとも思っている。
以前、こんな文献を紹介したけど、最近この話題を耳にするので、ちょっとそんな立場から思ったことを書いてみようかと。
英語を母国語としない我々にとって、国際雑誌に自分の論文を発表するときに英語で書かないといけないというのは大きなハンデ。なので、つい他人の書いた文献から文章をコピペしたくなってしまうのだが、それは剽窃ですからダメですよ、ということになっている。でも例えば、
A p value of less than 0.05 is considered statistically significant.
とどこかの文献に書いてあったのをコピペしたらダメと言われるかというと、もちろんそんなことは無い。
さて、そうなるとどこから剽窃でどこまでならOKか、ということになる。
決まり/定義は難しいと思われるかもしれないが、実は、現実問題としてはそんなことはなくて、比較的明確だよ、という話をしたい。
論文は、
・Introduction
・Methods
・Results
・Discussion
に分かれる。
まず、resultsは自分の数字だらけなのでコピペをする方が大変なくらい。数字が入らない文章も、例えば、
Results of multivariable regression analysis is shown in Table 3.
と書いて剽窃だと言う人は現実にはいない。
あ、これは不正確な表現だ。それを剽窃だと言って拒絶する編集者はマトモな雑誌にはいない、という意味。
Methodsの書き方は明らかな書式がある。この研究はいつどこで行われましたよー、倫理委員会は通しましたよー、から始まって、統計はこうやりましたよー、で終わる。だから定型的な文章のオンパレードになる。上記のP値についての文章が典型例。それを剽窃だと言う人は現実にはいない(これも編集者のことね)。
ここで勘違いしてはいけないのは、定型的文章のオンパレードにはなるけど、自分の研究に特異的な部分も必ずある、ということ。そりゃそうだ。そうでないとオリジナルじゃないもんね。こういう特異的な部分についての表現をそのまま他の文献から持ってくると、それはアウト。方法が似ている研究はあるので、やろうと思えばできたりするけど、これは定型的文章ではないので、明らかにこの文献のここからコピペしてきたと指摘できる。
Introductionとdiscussionにも書式がある。Disucssionについては、以前にちょっと書いた。
でも、当然ながら自分が言いたいことを書くところなので、他の人の文章をまるまるコピペすることはありえないはず。逆にそれをやったらそれは明らかな剽窃。
先日、若者が書いた論文が雑誌社から剽窃だとして突っ返されてきた。
手術中の放射線暴露についての研究で、放射線の人体に与える影響についての文章を若者が他の文献から数カ所まるまるコピペしていた。
そんな、日本語でもちゃんと説明する自信のないことを英語で書くのはとっても難しいので、コピペした気持ちはとっても分かるけど、これはアウト。表現を変えて再投稿。このときも、p値のことは指摘されなかった。
論文を書く目的は、自分が見つけた知見を公表して医学の進歩に貢献するため。そのためには新しい何かを見つけないといけない。でも、それを発表しないことには意味が無い。つまり、雑誌に採用されることが重要になる。だからルールは守る必要がある。
雑誌側は、送られてきた論文が医学の進歩に貢献するか、を評価する。その評価には、内容だけでなく、他の雑誌で発表されていないかとか、特許の侵害は無いかとか、盗作じゃないかとか、剽窃は含まれていないかとか、も含まれる。そのためのチェック方法の一つとして、少なくとも一部の雑誌ではコンピュータープログラムを使って過去の文献の文章からの剽窃を自動的にチェックする。とは言え、彼らも非英語圏からの論文を扱う事は多いし、そもそも雑誌の目的も医学の進歩への貢献なので、判断しながらやっているはず。文体が突然変わっていて明確なときもあるだろうし。
僕も英語は苦手。なんか良い表現は無いかなーと、文献をパラパラ見て探すなんていうことはよくやっている。母国語じゃないんだから、それは当然。そういう行為を、剽窃と読んで拒絶する編集者はいない。
結論。
・明らかに定型的な文章
・英語が苦手な人が表現を参考にしながら頑張って書いた文章
・難しい表現を他の文献からまるまるコピペした文章
何が剽窃で何が剽窃でないかは、少なくとも著者と編集者にとっては明確だと思う。
追伸。
STAP細胞の論文についても、剽窃についての学問的知識も、全然知りません。
ただ、こんな視点もあってもいいかと。
あ、なんでこんな話なのかと思われる方は、お気になさらずに。
”医学雑誌鑑賞が趣味のDr内野が面白い文献を毎週紹介”
と書いてある。
そもそもこのブログは、JSEPTICのホームページがリニューアルするときにアクティブコンテンツを作ろうということで始まったもので、こんなちょっと恥ずかしめの宣伝文句にした記憶がある。
とは言え、趣味とは言わないまでも文献を読んでいる数は平均よりは多いと思っているのは事実。
で、実は、文献を書いている数も平均よりは多いと思っている。
しかも最近は若者が論文を書く手伝いをすることも多いので、英語で論文を書いて投稿して採用される困難についてはそれなりに経験があるとも思っている。
以前、こんな文献を紹介したけど、最近この話題を耳にするので、ちょっとそんな立場から思ったことを書いてみようかと。
英語を母国語としない我々にとって、国際雑誌に自分の論文を発表するときに英語で書かないといけないというのは大きなハンデ。なので、つい他人の書いた文献から文章をコピペしたくなってしまうのだが、それは剽窃ですからダメですよ、ということになっている。でも例えば、
A p value of less than 0.05 is considered statistically significant.
とどこかの文献に書いてあったのをコピペしたらダメと言われるかというと、もちろんそんなことは無い。
さて、そうなるとどこから剽窃でどこまでならOKか、ということになる。
決まり/定義は難しいと思われるかもしれないが、実は、現実問題としてはそんなことはなくて、比較的明確だよ、という話をしたい。
論文は、
・Introduction
・Methods
・Results
・Discussion
に分かれる。
まず、resultsは自分の数字だらけなのでコピペをする方が大変なくらい。数字が入らない文章も、例えば、
Results of multivariable regression analysis is shown in Table 3.
と書いて剽窃だと言う人は現実にはいない。
あ、これは不正確な表現だ。それを剽窃だと言って拒絶する編集者はマトモな雑誌にはいない、という意味。
Methodsの書き方は明らかな書式がある。この研究はいつどこで行われましたよー、倫理委員会は通しましたよー、から始まって、統計はこうやりましたよー、で終わる。だから定型的な文章のオンパレードになる。上記のP値についての文章が典型例。それを剽窃だと言う人は現実にはいない(これも編集者のことね)。
ここで勘違いしてはいけないのは、定型的文章のオンパレードにはなるけど、自分の研究に特異的な部分も必ずある、ということ。そりゃそうだ。そうでないとオリジナルじゃないもんね。こういう特異的な部分についての表現をそのまま他の文献から持ってくると、それはアウト。方法が似ている研究はあるので、やろうと思えばできたりするけど、これは定型的文章ではないので、明らかにこの文献のここからコピペしてきたと指摘できる。
Introductionとdiscussionにも書式がある。Disucssionについては、以前にちょっと書いた。
でも、当然ながら自分が言いたいことを書くところなので、他の人の文章をまるまるコピペすることはありえないはず。逆にそれをやったらそれは明らかな剽窃。
先日、若者が書いた論文が雑誌社から剽窃だとして突っ返されてきた。
手術中の放射線暴露についての研究で、放射線の人体に与える影響についての文章を若者が他の文献から数カ所まるまるコピペしていた。
そんな、日本語でもちゃんと説明する自信のないことを英語で書くのはとっても難しいので、コピペした気持ちはとっても分かるけど、これはアウト。表現を変えて再投稿。このときも、p値のことは指摘されなかった。
論文を書く目的は、自分が見つけた知見を公表して医学の進歩に貢献するため。そのためには新しい何かを見つけないといけない。でも、それを発表しないことには意味が無い。つまり、雑誌に採用されることが重要になる。だからルールは守る必要がある。
雑誌側は、送られてきた論文が医学の進歩に貢献するか、を評価する。その評価には、内容だけでなく、他の雑誌で発表されていないかとか、特許の侵害は無いかとか、盗作じゃないかとか、剽窃は含まれていないかとか、も含まれる。そのためのチェック方法の一つとして、少なくとも一部の雑誌ではコンピュータープログラムを使って過去の文献の文章からの剽窃を自動的にチェックする。とは言え、彼らも非英語圏からの論文を扱う事は多いし、そもそも雑誌の目的も医学の進歩への貢献なので、判断しながらやっているはず。文体が突然変わっていて明確なときもあるだろうし。
僕も英語は苦手。なんか良い表現は無いかなーと、文献をパラパラ見て探すなんていうことはよくやっている。母国語じゃないんだから、それは当然。そういう行為を、剽窃と読んで拒絶する編集者はいない。
結論。
・明らかに定型的な文章
・英語が苦手な人が表現を参考にしながら頑張って書いた文章
・難しい表現を他の文献からまるまるコピペした文章
何が剽窃で何が剽窃でないかは、少なくとも著者と編集者にとっては明確だと思う。
追伸。
STAP細胞の論文についても、剽窃についての学問的知識も、全然知りません。
ただ、こんな視点もあってもいいかと。
あ、なんでこんな話なのかと思われる方は、お気になさらずに。











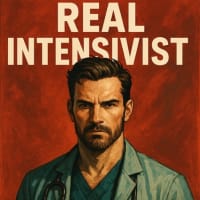












www.uni-edit.net
弊社の各学術分野専門の翻訳者たちは、国際ジャーナル誌によるアクセプトに不可欠な概念を
正確な英語に翻訳するための資格と経験を備えています。
日本語または英語でサービスをご提供いたします。
ご質問、見積もりのご注文は永山までご連絡ください。
uniedit.japan@gmail.com