年明け早々、たくさんあります。迷惑です。
Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al.
Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.
N Engl J Med. 2013 Jan 3;368(1):11-21. PMID: 23281973.
上部消化管出血患者921例。輸血するHbの閾値を7g/dlか9g/dlにするかでRCT。Hbの閾値を下げると輸血の必要性が減少(51% vs. 15%)、生存率が増加(95% vs. 91%)。ただし、生存率の改善度は原因疾患によって異なり、オッズ比は、潰瘍からの出血で0.70、Child AとBでは0.30、Child Cだと1.04。
(多分)偶然、同じ週のJAMAに輸血の閾値についてのメタアナリシスが載っている。Chocraneのアナリシスの結果紹介みたい。
Carson JL, Carless PA, Hebert PC.
Outcomes using lower vs higher hemoglobin thresholds for red blood cell transfusion.
JAMA. 2013 Jan 2;309(1):83-4. PMID: 23280228.
19のRCT、6000例。閾値が低い群の方が死亡率が低い(30日死亡率でrelative riskが0.85)。
基本、輸血は毒。気軽にしないように。
Helbok R, Kurtz P, Schmidt MJ, et al.
Effects of the neurological wake-up test on clinical examination, intracranial pressure, brain metabolism and brain tissue oxygenation in severely brain-injured patients.
Crit Care. 2012 Nov 27;16(6):R226. PMID: 23186037.
重症脳損傷患者にdaily interruptionは有意義か、についての観察研究。モニタリング(ICPとかPbtO2とか)がされている20例が対象。観察期間中(合計82件)、34%は鎮静剤を中止することは危険であると判断され、鎮静剤の投与が中止されたケースの三分の一でICPの増加や不穏や組織低酸素が起こり、新しい脳神経学的異常が発見できたのは1件のみだった。メリットよりもデメリットの方が多いのでは、という話。
Daily sedation interruptionについては、一度じっくりと考えた方がよさそう。ということで、ジャーナルクラブ候補。
Page RD, Asmat A, McShane J, et al.
Routine endoscopy to detect anastomotic leakage after esophagectomy.
Ann Thorac Surg. 2013Jan;95(1):292-8. PMID: 23200235.
食道癌の胃管再建後、1週間以内にルーチンで胃内視鏡を100例にやったら、15例に胃粘膜の虚血が見られ、2例はリークしており、4例はリークと虚血の両方が認められた。虚血の15例に1週間後にもう一度内視鏡をしたら、1例がリークしていた。それ以外の症例にリークは起こらず、内視鏡の診断精度は100%だった。
ちょっといつもと毛色の違う話だけど、へー、食道癌術後の胃カメラって、安全で診断価値があるのね、と思ったので。
Senbokuya N, Kinouchi H, Kanemaru K, et al.
Effects of cilostazol on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective, randomized, open-label blinded end point trial.
J Neurosurg. 2013 Jan;118(1):121-30. PMID: 23039152.
SAHのスパズム予防として、シロスタゾール(つまりプレタール)を投与するかどうかでRCT。109例が対象、シロスタゾール群で症候性バソスパズムが減少(13% vs. 40%)、脳梗塞も減少(11% vs. 29%)、6ヶ月後の神経学的予後も良かった。
日本の7施設からのRCT。Open labelで、症例数が100例程度なので、phase IIレベル。次の研究に進んでくれるといいけど。
今日のメインはこれで。
Muller L, Bobbia X, Toumi M, et al.; the AzuRea group.
Respiratory variations of inferior vena cava diameter to predict fluid responsiveness in spontaneously breathing patients with acute circulatory failure: need for a cautious use.
Crit Care. 2012 Oct 8;16(5):R188. PMID: 23043910.
自発呼吸をしている40例の循環不全(血圧低下、乏尿、頻脈、乳酸上昇など)症例に対し、HES 130/0.4(!)を500ml投与する前後で、心エコーで下大静脈径(cIVC)を測定。補液に対する反応性を大動脈の流速(subaortic velocity time index)の15%以上の増加で定義し、ReponderとNon-responderで比較。僧帽弁でのE/A比なども一緒に計測。
その結果、
#患者の内訳は、セプシス24例、出血11例、脱水5例。全体のちょうど半分の20例がResponder。
#cIVCのAUROCは0.77、E/A比は0.76。
#もっとも精度の高いcIVCのカットオフ値は40%。
#その値での精度は、感度80%、特異度70%、陽性予測値72%、陰性予測値83%
さて。
IVCの呼吸性変動、みんな好きだよねー。まあ、心エコーの基本的な測定の一つですし。
ここでは心機能や体液量の評価については割愛。呼吸性変動が大きいと、補液によって循環の改善は見られるか?
結論は、予想通りというか、そこそこの精度。無視するほどじゃないし、絶対的な信頼がおけるほどでもない。
とっても信頼している人もいそうなので、そうでもないよ、という話。
呼吸性変動を利用した補液の反応性の予測は、2000年前後からのブーム。だいたいどれも似たような研究で、数十例の患者に対し、補液をする前後で何かを測定、心拍出量かそれの代用が15%以上変化するかどうかで補液の反応を定義し、精度を検討。
違うのは、
・患者の呼吸状態が、調節呼吸か、それ以外の陽圧換気か、自発呼吸か
・反応性の評価方法が、ガンツか、PiCCOか、FloTracか、大動脈の流速か
・研究対象が、動脈圧波形か、SpO2波形か、SVC/IVCのエコーでの測定値か、PiCCOやFloTracの測定値か
くらい。
で、結果は、90%以上の感度特異度を報告しているものから、70%程度のものまで。
以前は、そっかー、CVPってほぼ無意味なんだな、呼吸性変動ってすごいな、と思って文献を読んでいたが、ここ10年、あまり話の内容に変化がなく、もう飽きた。
結局、調節呼吸だと正確、でもそれって麻酔中とかだけだし、自発呼吸だとイマイチ。どの測定値が一番良いか、とかはよく分からない。多分、どれもだいたい同じくらい。
そこに割って入ってきたのがpassive leg raising。確かに原理は異なるし、簡単にできるけど、精度は呼吸性変動と同じくらいだし、足を動かすと患者さんが覚醒して血圧が上がったりすることも珍しくなく、万能からはほど遠い。
なんか、こう、もう一声欲しいわね。
困ることの一つは、どれも数十例のsingle centerの研究で、ある測定値についての精度を報告しているだけなので、どんな病態にどの測定方法がいいかとか、病態によって精度は異なるのかとか、が分からない。
いろいろな施設で、いろいろな疾患を対象に数百例とかで、いろいろな測定方法をまとめて評価した、みたいな研究がそろそろ欲しいなー。
待ってないで、自分でやれって?
そーねー。。。
Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al.
Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.
N Engl J Med. 2013 Jan 3;368(1):11-21. PMID: 23281973.
上部消化管出血患者921例。輸血するHbの閾値を7g/dlか9g/dlにするかでRCT。Hbの閾値を下げると輸血の必要性が減少(51% vs. 15%)、生存率が増加(95% vs. 91%)。ただし、生存率の改善度は原因疾患によって異なり、オッズ比は、潰瘍からの出血で0.70、Child AとBでは0.30、Child Cだと1.04。
(多分)偶然、同じ週のJAMAに輸血の閾値についてのメタアナリシスが載っている。Chocraneのアナリシスの結果紹介みたい。
Carson JL, Carless PA, Hebert PC.
Outcomes using lower vs higher hemoglobin thresholds for red blood cell transfusion.
JAMA. 2013 Jan 2;309(1):83-4. PMID: 23280228.
19のRCT、6000例。閾値が低い群の方が死亡率が低い(30日死亡率でrelative riskが0.85)。
基本、輸血は毒。気軽にしないように。
Helbok R, Kurtz P, Schmidt MJ, et al.
Effects of the neurological wake-up test on clinical examination, intracranial pressure, brain metabolism and brain tissue oxygenation in severely brain-injured patients.
Crit Care. 2012 Nov 27;16(6):R226. PMID: 23186037.
重症脳損傷患者にdaily interruptionは有意義か、についての観察研究。モニタリング(ICPとかPbtO2とか)がされている20例が対象。観察期間中(合計82件)、34%は鎮静剤を中止することは危険であると判断され、鎮静剤の投与が中止されたケースの三分の一でICPの増加や不穏や組織低酸素が起こり、新しい脳神経学的異常が発見できたのは1件のみだった。メリットよりもデメリットの方が多いのでは、という話。
Daily sedation interruptionについては、一度じっくりと考えた方がよさそう。ということで、ジャーナルクラブ候補。
Page RD, Asmat A, McShane J, et al.
Routine endoscopy to detect anastomotic leakage after esophagectomy.
Ann Thorac Surg. 2013Jan;95(1):292-8. PMID: 23200235.
食道癌の胃管再建後、1週間以内にルーチンで胃内視鏡を100例にやったら、15例に胃粘膜の虚血が見られ、2例はリークしており、4例はリークと虚血の両方が認められた。虚血の15例に1週間後にもう一度内視鏡をしたら、1例がリークしていた。それ以外の症例にリークは起こらず、内視鏡の診断精度は100%だった。
ちょっといつもと毛色の違う話だけど、へー、食道癌術後の胃カメラって、安全で診断価値があるのね、と思ったので。
Senbokuya N, Kinouchi H, Kanemaru K, et al.
Effects of cilostazol on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective, randomized, open-label blinded end point trial.
J Neurosurg. 2013 Jan;118(1):121-30. PMID: 23039152.
SAHのスパズム予防として、シロスタゾール(つまりプレタール)を投与するかどうかでRCT。109例が対象、シロスタゾール群で症候性バソスパズムが減少(13% vs. 40%)、脳梗塞も減少(11% vs. 29%)、6ヶ月後の神経学的予後も良かった。
日本の7施設からのRCT。Open labelで、症例数が100例程度なので、phase IIレベル。次の研究に進んでくれるといいけど。
今日のメインはこれで。
Muller L, Bobbia X, Toumi M, et al.; the AzuRea group.
Respiratory variations of inferior vena cava diameter to predict fluid responsiveness in spontaneously breathing patients with acute circulatory failure: need for a cautious use.
Crit Care. 2012 Oct 8;16(5):R188. PMID: 23043910.
自発呼吸をしている40例の循環不全(血圧低下、乏尿、頻脈、乳酸上昇など)症例に対し、HES 130/0.4(!)を500ml投与する前後で、心エコーで下大静脈径(cIVC)を測定。補液に対する反応性を大動脈の流速(subaortic velocity time index)の15%以上の増加で定義し、ReponderとNon-responderで比較。僧帽弁でのE/A比なども一緒に計測。
その結果、
#患者の内訳は、セプシス24例、出血11例、脱水5例。全体のちょうど半分の20例がResponder。
#cIVCのAUROCは0.77、E/A比は0.76。
#もっとも精度の高いcIVCのカットオフ値は40%。
#その値での精度は、感度80%、特異度70%、陽性予測値72%、陰性予測値83%
さて。
IVCの呼吸性変動、みんな好きだよねー。まあ、心エコーの基本的な測定の一つですし。
ここでは心機能や体液量の評価については割愛。呼吸性変動が大きいと、補液によって循環の改善は見られるか?
結論は、予想通りというか、そこそこの精度。無視するほどじゃないし、絶対的な信頼がおけるほどでもない。
とっても信頼している人もいそうなので、そうでもないよ、という話。
呼吸性変動を利用した補液の反応性の予測は、2000年前後からのブーム。だいたいどれも似たような研究で、数十例の患者に対し、補液をする前後で何かを測定、心拍出量かそれの代用が15%以上変化するかどうかで補液の反応を定義し、精度を検討。
違うのは、
・患者の呼吸状態が、調節呼吸か、それ以外の陽圧換気か、自発呼吸か
・反応性の評価方法が、ガンツか、PiCCOか、FloTracか、大動脈の流速か
・研究対象が、動脈圧波形か、SpO2波形か、SVC/IVCのエコーでの測定値か、PiCCOやFloTracの測定値か
くらい。
で、結果は、90%以上の感度特異度を報告しているものから、70%程度のものまで。
以前は、そっかー、CVPってほぼ無意味なんだな、呼吸性変動ってすごいな、と思って文献を読んでいたが、ここ10年、あまり話の内容に変化がなく、もう飽きた。
結局、調節呼吸だと正確、でもそれって麻酔中とかだけだし、自発呼吸だとイマイチ。どの測定値が一番良いか、とかはよく分からない。多分、どれもだいたい同じくらい。
そこに割って入ってきたのがpassive leg raising。確かに原理は異なるし、簡単にできるけど、精度は呼吸性変動と同じくらいだし、足を動かすと患者さんが覚醒して血圧が上がったりすることも珍しくなく、万能からはほど遠い。
なんか、こう、もう一声欲しいわね。
困ることの一つは、どれも数十例のsingle centerの研究で、ある測定値についての精度を報告しているだけなので、どんな病態にどの測定方法がいいかとか、病態によって精度は異なるのかとか、が分からない。
いろいろな施設で、いろいろな疾患を対象に数百例とかで、いろいろな測定方法をまとめて評価した、みたいな研究がそろそろ欲しいなー。
待ってないで、自分でやれって?
そーねー。。。











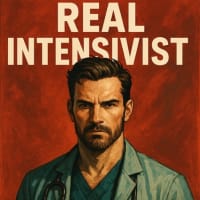












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます