最近よく聞く言葉。
少し危険を感じているので、これを紹介。
Hubbard RA, Gatsonis CA, Hogan JW, et al.
"Target Trial Emulation" for Observational Studies - Potential and Pitfalls.
N Engl J Med. 2024 Nov 28;391(21):1975-1977. PMID: 39588897.
最後の文章。
"When rigorously implemented, the target trial emulation framework provides a useful method for systematic specification of the design of observational studies, but is not a panacea."
(意味が分かりにくい部分があるのでChat先生に少しだけ意訳してもらった)
「厳密に実施される場合、target trial emulationのフレームワークは、観察研究の設計を体系的かつ一貫して定義するための有用な手法であるが、万能薬ではない。」
極端な例だし、Target traial emulationでもないけど、観察研究の限界をわかりやすく示している文献を紹介。
Teman NR, Strobel RJ, Bonnell LN, et al.
Operating Room Extubation for Patients Undergoing Cardiac Surgery: A National Society of Thoracic Surgeons Database Analysis.
Ann Thorac Surg. 2024 Sep;118(3):692-699. PMID: 38878949.
1000以上の病院の約67万例を使用した研究。CABGや弁手術患者をOP室で抜管したら死亡率が半分になった。
なるか!
どれだけ情報を集めたって、Nを増やしたって、患者背景の群間差をなくすことはできない。
「ビッグデータと洗練された統計手法とAIがあれば、将来的にはRCTは行われなくなっていくのでは?」と言う人もいるが、僕は真逆だと思っている。
多施設RCTを行うには、研究を立案して、IRBを通して、保険会社と相談して、参加施設を募って、患者家族からICを取得して、データを集めて、参加施設の意欲を維持して、正しくデータを解析して、執筆して投稿して、採用してくれる雑誌を探す必要がある。列挙してみると改めて大変さがわかるし、ビッグデータを後ろ向きに解析したらこの大変さの相当な部分が省略できるのは事実。でも、データが電子化されて、研究プロセスのあらゆるところにAIが関与するようになると、実はこの大変さのほとんどは劇的に減少する。sakana AIを見れば、それは容易に予想できる。
観察研究もRCTも両方とも進歩するから、ずっと車の両輪のままです。
少し危険を感じているので、これを紹介。
Hubbard RA, Gatsonis CA, Hogan JW, et al.
"Target Trial Emulation" for Observational Studies - Potential and Pitfalls.
N Engl J Med. 2024 Nov 28;391(21):1975-1977. PMID: 39588897.
最後の文章。
"When rigorously implemented, the target trial emulation framework provides a useful method for systematic specification of the design of observational studies, but is not a panacea."
(意味が分かりにくい部分があるのでChat先生に少しだけ意訳してもらった)
「厳密に実施される場合、target trial emulationのフレームワークは、観察研究の設計を体系的かつ一貫して定義するための有用な手法であるが、万能薬ではない。」
極端な例だし、Target traial emulationでもないけど、観察研究の限界をわかりやすく示している文献を紹介。
Teman NR, Strobel RJ, Bonnell LN, et al.
Operating Room Extubation for Patients Undergoing Cardiac Surgery: A National Society of Thoracic Surgeons Database Analysis.
Ann Thorac Surg. 2024 Sep;118(3):692-699. PMID: 38878949.
1000以上の病院の約67万例を使用した研究。CABGや弁手術患者をOP室で抜管したら死亡率が半分になった。
なるか!
どれだけ情報を集めたって、Nを増やしたって、患者背景の群間差をなくすことはできない。
「ビッグデータと洗練された統計手法とAIがあれば、将来的にはRCTは行われなくなっていくのでは?」と言う人もいるが、僕は真逆だと思っている。
多施設RCTを行うには、研究を立案して、IRBを通して、保険会社と相談して、参加施設を募って、患者家族からICを取得して、データを集めて、参加施設の意欲を維持して、正しくデータを解析して、執筆して投稿して、採用してくれる雑誌を探す必要がある。列挙してみると改めて大変さがわかるし、ビッグデータを後ろ向きに解析したらこの大変さの相当な部分が省略できるのは事実。でも、データが電子化されて、研究プロセスのあらゆるところにAIが関与するようになると、実はこの大変さのほとんどは劇的に減少する。sakana AIを見れば、それは容易に予想できる。
観察研究もRCTも両方とも進歩するから、ずっと車の両輪のままです。











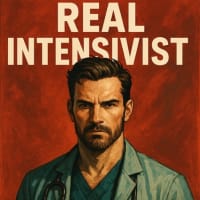












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます