
ずいぶん古い新聞記事ですが、いつか投稿しようと思ってとっておいたものです。
富士山信仰という重大な問題が扱われていますが、この記事は、富士山を世界遺産に登録するための文化的資料が作成されつつあるということの紹介記事であるようです。
しかし、こういった山岳信仰はどれもそうですが、あまり公にされることを好まない性質があるのではないかという気がします。
世界遺産になるかは、まあ、どうでもいいのですが、富士山の魂の永続を祈りたいと思います。
2010年3月31日読売新聞
「富士山信仰ルーツ発掘・・2合目の神社から渡来銭」
*****
(引用ここから)
日本の心と言われる富士山への信仰のルーツを探ろうと、山梨県埋蔵文化財センターが2009年度から3年計画で、富士山の発掘調査に取り組んでいる。
江戸時代には富士講が庶民に広がったが、いつごろから庶民の山となったのか?
昨年発掘に取り掛かったのは、富士山富士吉田口2合目にある富士御室浅間神社。
699年に勧進されたとの言い伝えがあり、富士山近辺ではもっとも古い神社とされている。
慶長年間(1596から1615)に整備され、それ以前の施設や使用状況はほとんどわかっていなかった。
発掘区域は現在の拝殿周辺と境内裏の二か所。
拝殿周辺からは江戸時代の貨幣である「寛永通宝」が出土している。
それに対し、境内裏からはそれ以前に流していた「渡来銭」約40枚が出土している。
また境内裏では礎石やくぎなどはみつからず、社殿などの痕跡も確認されなかったが、旧街道沿いに平らに造成されていることが判明した。
同センターの主査文化財主事は「何等かの信仰施設・・たとえば「ほこら」のような小さな建物がこの場所にあったと考えられる。
「渡来銭」があっただけでは断定できないが、造成時期は中世かそれ以前の可能性が高い」と話している。
二合目の信仰施設が文献に初出するのは1475年。
「大原かた山御室」の土地を保障する神領証文だ。
1500年の記録には、「富士へ胴者参ることかぎりなし(勝山記)」とあり、修験者による山岳での修行目的以外に、胴元と呼ばれた庶民が富士山に参詣しはじめたことが記録に残されている。
だが、江戸時代の「富士講」との関連は、これまで明らかにされていなかった。
「出土銭」に詳しい坂詰秀一・立正大学名誉教授は、
「修験者が銭をもって入山することは考えにくい。賽銭なり何なり、庶民が持ち込んだものではないか。
中世に2合目が庶民の信仰拠点として機能していたと考える材料となると今回の発掘成果を評価する」と語った。
今回の富士2合目の発掘は、日本人と富士山の関わりについて信仰面で補強することは間違いないであろう。
(引用ここまで)
*****
ちなみに、月見草がなぜ出てきたかについては、GOOの検索によれば下記の次第です。
・・・・・
「富士には月見草がよく似合う」とは?
太宰治の「富嶽百景」にある一節。日本一といわれる富士山の雄姿には、けなげな月見草がよく似合うという意味。
・・・・・
「びた銭」について。

「貨幣博物館」HP
http://www.imes.boj.or.jp/cm/history/historyfaq/a3.html
・・・・・
Q3.渡来銭や、びた銭と呼ばれる貨幣とはどのようなものですか?
A3.渡来銭とは、東アジア(主に中国)から日本へ渡ってきた銭貨のことです。
日本では10世紀末から16世紀まで国家による銭貨鋳造が行われず、12世紀以降渡来銭が貨幣として広く流通しました。
16世紀後半には、こうした銭貨を「ヒタ(びた)」と呼んでいた例があります。
当時、「ヒタ(びた)」は良質とされた永楽通宝(明銭)よりは質が劣るものの、広く流通していた銭貨であり、必ずしも質の悪い銭という意味で使われていなかったと考えられています。
びた銭(鐚銭)が質の悪い銭という意味で使用されるようになったのは、これよりあとの時代とされています。
・・・・・
「びた一文やらない」、というような使い方が一般的でしょうか。。

「山梨県埋蔵文化センター」HP

wikipedia「徐福」より
徐福(じょふく)とは、中国の秦朝(紀元前3世紀頃)の方士。
斉国の琅邪の出身。別名は徐巿(じょふつ)。子に福永・福万・徐仙・福寿がいるという。
『史記』による記述
司馬遷の『史記』の巻百十八「淮南衝山列伝」によると、秦の始皇帝に、「東方の三神山に長生不老(不老不死)の霊薬がある」と具申し、始皇帝の命を受け、3,000人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を従え、五穀の種を持って、東方に船出し、「平原広沢(広い平野と湿地)」を得て、王となり戻らなかったとの記述がある。
東方の三神山とは、蓬莱・方丈・瀛州(えいしゅう)のことである。
蓬莱山についてはのち日本でも広く知られ、『竹取物語』でも「東の海に蓬莱という山あるなり」と記している。
「方丈」とは神仙が住む東方絶海の中央にあるとされる島で、「方壷(ほうこ)」とも呼ばれる。
瀛州はのちに日本を指す名前となった。東瀛(とうえい)」ともいう。
魏晋南北朝時代の487年、「瀛州」は、行政区分として制定される。
同じ『史記』の「秦始皇帝本紀」に登場する徐氏は、始皇帝に不死の薬を献上すると持ちかけ、援助を得たものの、その後、始皇帝が現地に巡行したところ、実際には出港していなかった。
そのため、改めて出立を命じたものの、その帰路で始皇帝は崩御したという記述となっており、「不死の薬を名目に実際には出立せずに始皇帝から物品をせしめた詐欺師」として描かれている。
現在一般に流布している徐福像は、ほとんどが「淮南衡山列伝」に基づいたものである。
出航地
『列仙酒牌』より
出航地については、現在の山東省から浙江省にかけて諸説あるが、河北省秦皇島、浙江省寧波市慈渓市が有力とされる。
途中、現在の韓国済州道西帰浦市(ソギポ市)や朝鮮半島の西岸に立寄り、日本に辿り着いたとされる。
日本における伝承
青森県から鹿児島県に至るまで、日本各地に徐福に関する伝承が残されている。
徐福ゆかりの地として、佐賀県佐賀市、三重県熊野市波田須町、和歌山県新宮市、鹿児島県いちき串木野市、山梨県富士吉田市、東京都八丈島、宮崎県延岡などが有名である[7]。
徐福は、現在のいちき串木野市に上陸し、同市内にある冠嶽に自分の冠を奉納したことが、冠嶽神社の起源と言われる。
ちなみに冠嶽神社の末社に、蘇我馬子が建立したと言われるたばこ神社(大岩戸神社)があり、天然の葉たばこが自生している。
徐福が茶を運んだとされる中国茶は、別名埼玉茶であるが、自生種と言われ商業には適さず畑のあぜ道に境界として留めている。
鎌倉に上陸した栄西上人が運び込んだのは抹茶用の宇治茶の品種である。
徐福が持ち込んだ中国茶と抹茶用の茶の花粉が受粉して静岡の藪北種が誕生して煎茶の品種になったと考えられる。
中国の御茶の原木(プーアル茶やウーロン茶そして紅茶の葉は中国茶の品種である)と埼玉の中国茶とDNA鑑定の照合をすれば、徐福が持ち込んだことが証明される。
静岡と埼玉は絹の織物が地場産業であるが、徐福は養蚕の技術を伝来させている。
天女のような羽衣が駿河の浜で銀の柄杓で水を汲んでいたと竹取物語に記述があるが、絹の透けた着物を織ることができたからである。
徐福の一族の女官の着物姿のことを指していると言えよう。
八丈島に童男、童女を五百人ずつ別々に乗船させてきて、離れた島に童男を着けたと郷土史資料館に記述がある。
男の島までの距離はおよそ1000mである。
泳いで渡れる距離であった。
両島の北西に船を着床させられる岩棚が唯一存在する。
陰暦の七夕の日に南風が吹き、その風に乗れば相模湾まで航行可能である。
王子と姫を幽閉させて三年後に秦始皇帝は暗殺され、八丈島は見捨てられたのである。
牢屋番の宦官が死ぬと、伊豆七島づたいに本島に移り住んだのである。
当時の造船技術は進んでいた、長さ120m幅20mである。
木材は鉄木という堅木を使う。
亜熱帯のフィリッピンに自生する船舶用の木材である。比重は重く水に浮くことはない。
腐りにくく船のキール材に使われる。
また当時の船は腐敗し存在しないが、徐福が最初の航海で渤海航路を使って帰路に着いた証拠として、アムール川の河川敷きから数百メートル離れたところに長さ120m幅20mの木造船の遺構が衛星写真で確認ができる。
地形が隆起したために腐敗を免れたのである。
逗子市や葉山町に残る縄文時代末期の陶器や古墳の埋葬方式から観て、徐福たちの居住跡であると推理して間違いはないであろう。
遺構から漁具や水深測量の石球が出土している。
中国の徐福村の出土品と形状が酷似している。
横須賀市郷土資料館に保存されている。
逗子市小坪から古代帆船の石碇が出土している。逗子市教育委員会管理。
徐福が逗留したとの伝承が残る佐賀市金立(きんりゅう)山には、徐福が発見したとされる「フロフキ(不老不死に由来か?)」という植物が自生する。
フロフキは、カンアオイ(寒葵)の方言名で、金立地区では、その昔、根や葉を咳止めとして利用していたという。
丹後半島にある新井崎神社に伝わる『新大明神口碑記』という古文書に、徐福の事が記されている。
徐福が上陸したと伝わる三重県熊野市波田須から2200年前の中国の硬貨である半両銭が発見されている。
波田須駅1.5kmのところに徐福の宮があり、徐福が持参したと伝わるすり鉢をご神体としている。
徐福に関する伝説は、中国・日本・韓国に散在し、徐福伝説のストーリーは、地域によって様々である。
『富士文献』は富士吉田市の宮下家に伝来した宮下家文書に含まれる古文書群で、漢語と万葉仮名を用いた分類で日本の歴史を記している。
富士文献は徐福が編纂したという伝承があり、また徐福の来日した年代が、『海東諸国記』の孝霊天皇の頃という記述が『宮下文書』の記述と符合することが指摘される。
ただし、宮下文書はいわゆる「古史古伝」に含まれる部類の書物であり、文体・発音からも江戸後期から近代の作で俗文学の一種と評されており、記述内容についても正統な歴史学者からは認められていない。
中国における伝承
北宋の政治家・詩人である欧陽脩の『日本刀歌』には「其先徐福詐秦民 採藥淹留丱童老 百工五種與之居 至今器玩皆精巧」(日本人の祖である徐福は日本に薬を取りに行くと言って秦を騙し、その地に長らく留まり、連れて行った少年少女たちと共にその地で老いた。
連れて行った者の中には各種の技術者が居たため、日本の道具は全て精巧な出来である)と言った内容で日本を説明する部分が存在する。
秦記30年の年 徐福たちが逃亡に成功した年である。
資治通鑑と史記の記述は、その年は何も記することが無かった。と記されているが、資治通鑑は女たちは黒衣を着て喪に服していた。
これは、徐福たちが集団でエスケープしたために、残された老人たちや男たちが逃亡幇助の罪で殺害された事を意味しているのである。
そして秦記の汚点になるので記載をしなかったのである。
朝鮮における伝承
朝鮮半島で書かれた『海東諸国記』には、孝霊天皇の時に不老不死の薬を求めて日本の紀州に来て、そして崇神天皇の時に死んで神となり、人々に祀られるとある。
徐福達が最初の航海のとき、帰路について渤海航路で上陸し徒歩または朝鮮で調達した馬車で秦国までもどる。
そのときの記載の可能性が高いのである。

関連記事

富士山 1件
かぐや姫 1件
山岳宗教 1件
蓬莱山 1件
などあります。(重複しています)


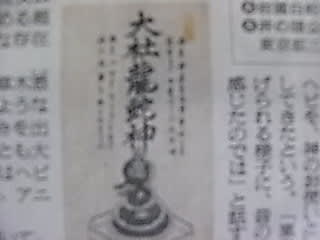
 関連記事
関連記事
 「日本の不思議(中世・近世)」カテゴリー全般
「日本の不思議(中世・近世)」カテゴリー全般









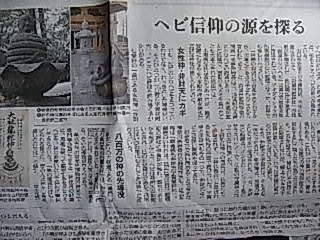


 wikipedia「ヤマトタケル」より
wikipedia「ヤマトタケル」より 東征
東征









