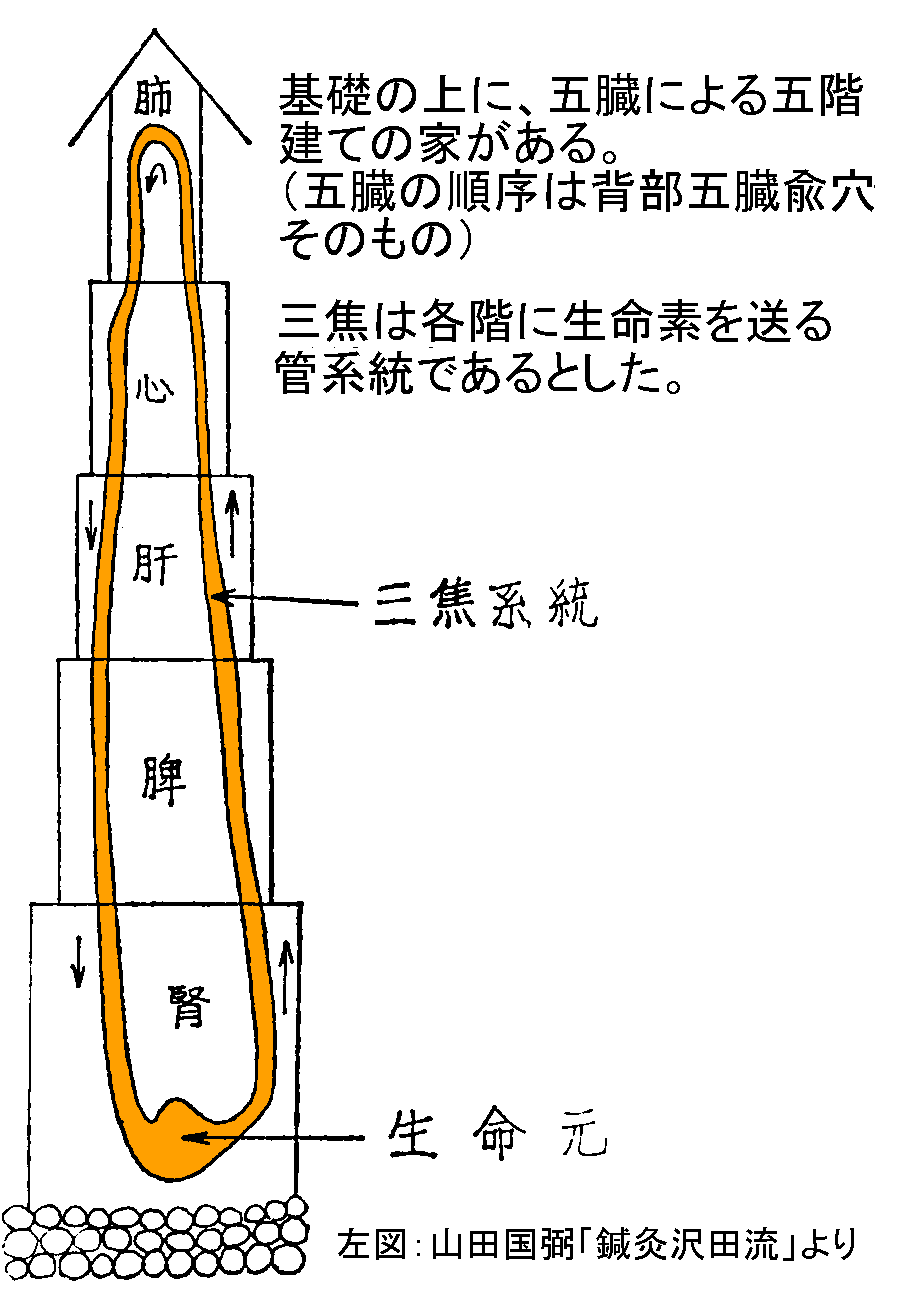1.鍼灸専門学校が急増した結果、学生・学校とも苦しくなった
近年の鍼灸師制度のエポックは、鍼灸師が国家資格になったことだろう。これにより肩書き的に資格価値が向上したのだが、就職口や収入が増えた訳ではない。福岡の裁判以降、鍼灸も柔整も専門学校は倍増し、入学しやすくはなったが有資格者は倍増した。受診患者が増えたわけではなく、有資格者が増えた分だけ、一人当たりの年収は低くなった。
大儲けしたのは、入学定員を増やした鍼灸や柔整の専門学校だけといえそうだが、ネットが普及した現在、国家試験をパスしただけでは儲けるのが難しいことが広く知られるようになり、入学希望者が減少してきた。学生が定員割れを起こして経営難になった学校も少なくない。
2.鍼灸学校卒後の新人鍼灸師の進路
通常は医療関係の学校を卒業すると、その専門を活かすべく病院勤務の正職員となり、規定の給与や待遇が補償され、簡単には解雇されることはない。しかし鍼灸も柔整も西洋医療システムの枠外に存在しているので、卒後の生き方が限られてくる。
詳細は差し控えるが柔整には収益モデルがあり、柔整師になれば儲かるという常識がこの半世紀続いてきた。一方鍼灸師は、保険取扱いをするために医師同意書が必要というネックがあることや、慰安的要素もあまりないこと、自費治療中心となることなどにより、少人数の患者に対して全力を傾けて治療するというスタイルになる。来院患者も多くないので儲かりにくい。ゆえに店舗も貧相なもので、院長一人でやっている零細鍼灸院が大部分である。仮に無給だったとしても、手間がかかるだけの鍼灸学校新卒者の卒後教育を行う余裕などとてもない。
3.鍼灸師の経済
鍼灸師はどれほどの年収を得ているのだろうか。データ(2006年頃)によれば1年間における鍼灸医療の延べ受領3000-3500万人、1界の治療費を4000円とすると総合治療費は1200~1400億円と推定。就業鍼灸師は、約60,000~65,000人、施術所数は42,000カ所と推定。これらの数値から鍼灸師一人あたりの年収を算出すると230万円、施術所あたりの収益は330万円と推定される。国民医療費における鍼灸の総治療費の占める率をみると、国民医療費を35兆円としれば0.4~0.5%にしか過ぎない。
引用文献:藤井亮輔、坂井友実、佐々木健 他:就業者実体調査にみる鍼灸マッサージの 現状と課題(第2報)、医道の日本、2006
4.鍼灸師の努力は盛業鍼灸院を目指すこと以外にない
いくら鍼灸師側が、今の制度が悪いと叫んだとしても結局一人相撲に終わってしまう。社会を動かすには力不足ということ。それが分かっているから、鍼灸師の仲間同士が一つの目的に向けて一丸となって歩むことに意義を見いだせない。努力の方向は、ただ自分の治療院を盛業させることに向けられる。ただし開業しない鍼灸師の方が多い。ある調査では、開業しているのは有資格者の約3割で、柔整は約7割だった。当然のことだが開業しても成功する保証はないのである。
一方、鍼灸学校の新卒者の希望を聞くと、「まずは実力ある先生の見習いとして2~3年働き、実力を養成しつつ開業したい」という者が多い。大きな医療施設で勤務鍼灸師として安定した生活を送りたいという者もいる。これらは実にまともな要望である。が、このような希望が叶うことはめったにない。求人がないのだからやむを得ない。求人があるのは接骨院での無資格マッサージ要員ばかり。
5.山下九三夫医師によるAMT制度の提言
山下九三夫医師(故)が1981年(昭和56年)の時、医道の日本誌にAMT制度の構想について独自の提言をした。AMTとはAcupuncture and Moxibustion Therapist を略したもので鍼灸師のことである。単に日本語を英語表記にしたのは、PT、OT、STなどのパラメディカルと同列に位置づけ、病院内で活躍の場を広げたいからだと思われる。現在の医療制度の中に鍼灸を取り入れ、鍼灸師が病院で活躍できるようにするという目的を達成するため、鍼灸師教育体制の質の向上、医師の鍼灸に対する正確な評価、そして法改正が必要だという趣旨であった。
この5年ほど前には、日本初となる明治鍼灸短大ができたことや日産玉川病院東洋医学科の創設が続き、鍼灸界にもついに新しい波がやってきたのかと、期待した鍼灸師も多かったと思う。
この山下九三夫の提言したAMT制度について、代田文彦先生に意見を聴いてみると、「山下氏は周りから散々批判され辟易とした。ちょっと自分の想いを書いてみただけじゃないか」と逃げ腰になっていたという。ただしAMT制度は沈滞した鍼灸界を活性化させる重要な提言なので、日本東洋医学雑誌に再検討の記事が掲載されている。(末尾の引用文献参照)
6.AMT制度が誕生したらどうなるのか(夢物語として)
1)病院で鍼灸が行うようなれば、一挙に鍼灸師の活躍の場が広がり、鍼灸師の生活もPTやOTの待遇程度に落ち着くだろう。鍼灸学校教育でも病院鍼灸師を目標とした教育スタイルが確立するので、1日に1コマ(90分)を3コマないし4コマ程度の授業時間で、4年程度の就業年限となるだろう。より大きな変化は座学のみならず病院における実地教育も取り入れるられることである。教育カリキュラムにはPT、OTの例が参考になる。
2)病院システムの一貫として鍼灸が運営されるので、「鍼灸科」あるいは「東洋医学科」と標榜することが望ましい。初診は科長である医師が鍼灸治療の適否を判断し、治療そのものは鍼灸師に委任する。医師自ら漢方薬を処方するのもありである。チーム医療として定期的に症例検討会を行う。
3)病院鍼灸では、病院付近の開業針灸にとって経営的に驚異であるから、病院鍼灸は保険取扱はしないことにする。それだけでも開業鍼灸師の大半は患者減となってしまうので、救済の意味から開業針灸での保険取扱は簡素化する。
4)十年~二十年の後、鍼灸師は新規開業は禁止となるのと当時に、病院鍼灸では保険を使うことになる。すなわち現行のPTやOTと同じように、医師の間接的指示のもと、鍼灸師の判断で治療をは行うようになる。
救済措置として近隣の開業鍼灸師は、希望に応じて病院勤務できるよう特別教育を用意し病院鍼灸師の一定比率を近隣の開業鍼灸師枠として設ける。
引用文献
○若山育郎、形井秀一 山口智 篠原昭二 山下仁小松秀人:病院医療における鍼灸
-鍼灸師が病院で鍼灸を行うために- 日東医誌、Vol.65 No4(2014)
○矢野忠:現代における日本鍼灸の存在意義、社会鍼灸学研究2010(通巻5号)