


●正倉院がまもり伝えた宝物(ほうもつ)の一つ
螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)高度な技法で華やかな意匠を表わされたも正倉院宝物。
●正倉院宝物は「聖武天皇」の所蔵していた物故「宮内庁 正倉院所蔵」となり国宝には指定されません。
●頭部がまっすぐの五弦琵琶は、インドが発祥の地です。撥受けは、たい瑁(たいまい)を貼り、
貝殻を使った螺鈿(らでん)で、熱帯樹と飛鳥や駱駝(らくだ)に乗り琵琶[四絃琵琶]を弾く胡人を表し、
側面には紫檀(したん)に夜光貝の切片を貼るなど第一級の美術工芸品でもあります。
同時代の五弦琵琶としては世界で唯一のもので、聖武天皇(しょうむてんのう)[701-756]の遺品です。
**************以上コピペです*************************
さて、螺鈿細工の歴史は古く、紀元前3000年頃のエジプト文明にまでさかのぼるそうです。
エジプトから「唐」そして「朝鮮」遠くシルクロードを経て・・・その終点が「正倉院」となるわけです。
ですから、 日本で螺鈿細工が作り始められたのは奈良時代。と言うことになるのでしょうか!
こちらも正倉院蔵


●螺鈿(らでん)とは、主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられる装飾技法のひとつで
貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を切り出した板状の素材を、
漆地や木地の彫刻された表面にはめ込む手法、およびこの手法を用いて製作された工芸品のこと。
●螺鈿はアワビや夜光貝、白蝶貝などの貝がらの輝いた部分をうすく(0.1ミリ以下)して使います。
「螺」は巻き貝をさし、「鈿」にはかざるという意味があるそうです。
最後に
京都出身の名工(漆・螺鈿作家)
人間国宝黒田辰秋(くろだたつあき)氏
螺鈿「中棗」・・・葛切りで有名な「鍵善」さんが先頃オープンされたの個人美術館で
目にしました・・・蔵されているんですね!4月の初旬に訪問!


精緻な造形が美しく暫し見入りました。
はい、皆様本日は螺鈿のお話しでした。
3000年も前エジプトから始まった工芸・・・誰が、どう工夫して、生まれたのでしょうね?
素晴らしく、奥深く、そして不思議なお話でした。
本日ご訪問くださいました皆様ありがとうございました・・・
中井悠石拝


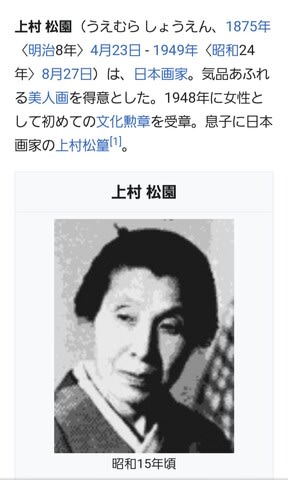





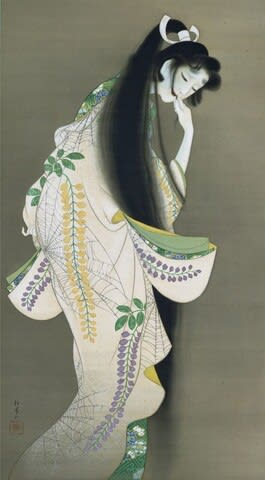














 コンセプト概要はこちらからどうぞ
コンセプト概要はこちらからどうぞ










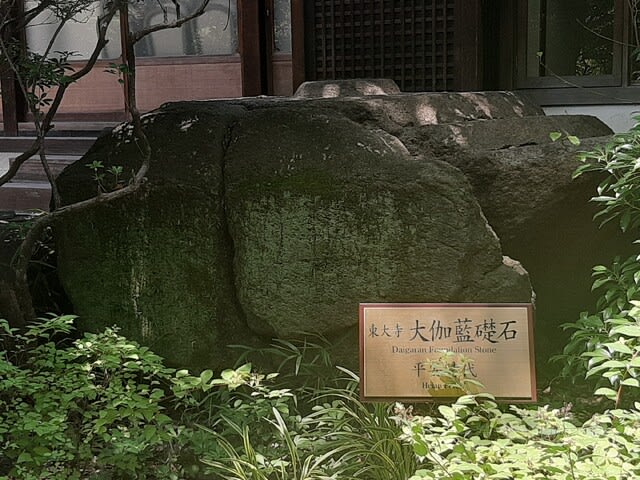
















 この二枚は以前、描いたもです。
この二枚は以前、描いたもです。



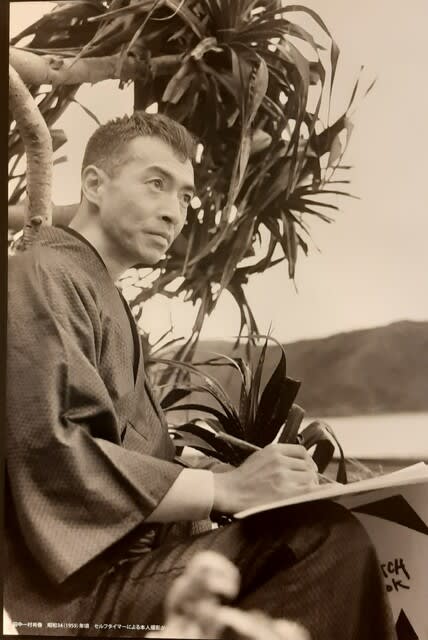
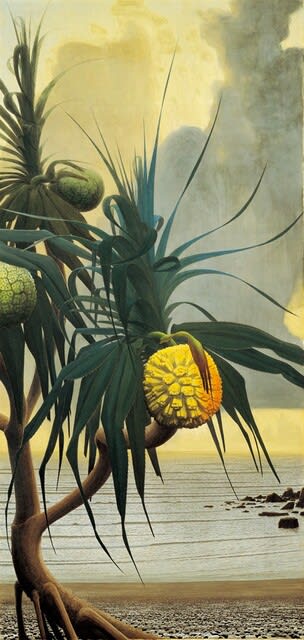
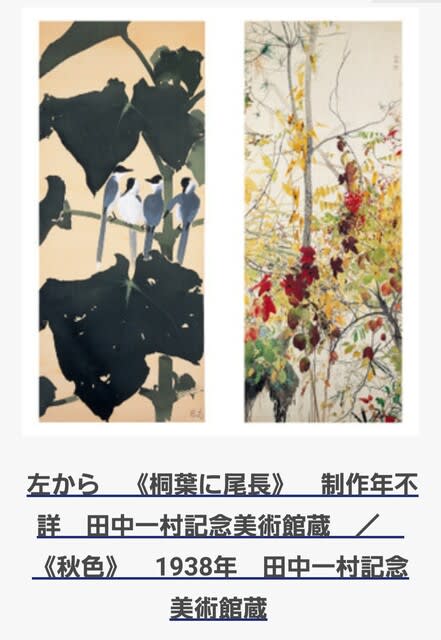
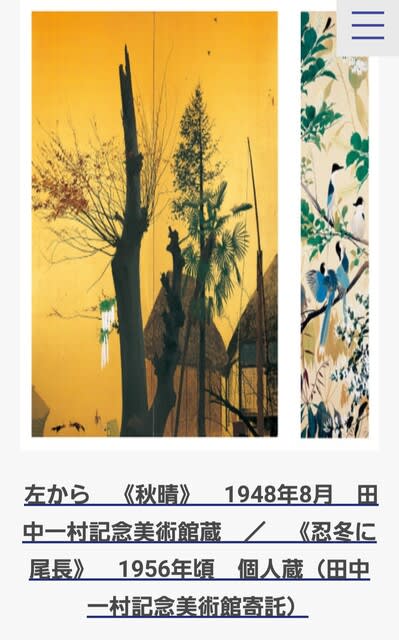



 名もなき職人さん達の手に!敬礼です!
名もなき職人さん達の手に!敬礼です!



















