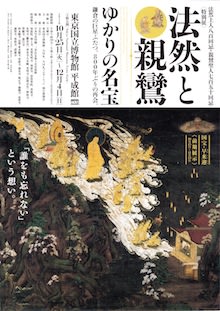江戸東京博物館で開かれていた大関ヶ原展を観に行ってきた。日曜日ということもあってか、非常に混んでいた。根強い人気である。人が多すぎて、思うように見れない。確かに行列があまり進まないので、その分、ゆっくり見えるのだが、屏風とかの全体像とかがわかりにくいし、好きなところでじっくり見ることはできなかった。
この大関ヶ原展は、現存する最古の「関ケ原合戦図屏風」をはじめ、本多忠勝ら徳川四天王の具足や槍、石田三成の愛刀「正宗」、島左近の兜、大谷吉継の刀、家康にもたらされた「洋時計」など、国宝、重要文化財を含め、約150点以上が出品されている。また、ジオラマ・プロジェクションマッピングで、関ヶ原の合戦の様子を時系列に紹介して西軍、東軍それぞれどのような陣形を組んでいたのか、何時ころ形勢に変化が見られたのか、裏切った者は誰だったのか等々わかりやすかった。宇喜多秀家の寝返りや、大谷の踏ん張り、島津家のわずかな手勢で敵陣を突破して逃げ抜いた説明はわかりやすかった。
さらに、関ヶ原合戦前日に密約を交わした誓約書など、関ヶ原合戦にまつわる貴重な古文書を展示。有力武将たちがしたためた文書から、“信頼”“裏切り”“凋落”などが読み取れ、当時の情報戦が浮かび上がってくる。天下分け目の関ヶ原合戦のみならず、“戦場外の戦場”も読み解いている。戦場で家康を象徴した金の扇、結構大きいのには驚いた。長く江戸城に保管されていたもので、実際に慶長5年9月15日(西暦1600年10月21日)の関ヶ原の戦いでも用いられたそうである。本多忠勝の『蜻蛉切』。その切れ味を表して蜻蛉が刃先に止まっただけなのに真っ二つになったと言われる。鋭く光っていた。
以下、関ヶ原の戦いを覚書で、メモしておきたい。
福島(東)対 宇喜多(西)この両軍の激突で始まった戦は(一説には、先鋒の福島隊より先に、井伊、松平の小隊が仕掛けたとも言われる)各所で激戦が展開されていく。1600年7月、石田三成 は 「徳川討伐」 の挙兵を宣言!関ヶ原という場所は四方を山に囲まれたくぼ地であり、その中に入った東軍を、山の上に布陣した西軍が完全に包囲している状況。これは誰がどう見ても 「西軍有利」。実際、後世にこの布陣図を見たドイツ軍の将校も、見た瞬間に「西軍必勝!」と叫んだそうである。
大谷吉継(西)の孤軍奮闘、黒田、細川(東)と石田三成隊の死闘など、後世に語り継がれた名勝負が続く中、一方で数々の諜報、謀略という裏側での駆け引きも密かに進んでいた。 関ヶ原には参加はするが動かない勢力。寝返りを思慮する者達。多くの武将が、疑心暗鬼の不安を抱える中、西軍の大勢力である小早川秀秋が動いた。徳川方からの調略の結果か、石田三成への私怨(三成の報告により、大幅な減封を受けた)か、味方であるはずの大谷隊に軍勢を向けたのだ。多勢に無勢の大谷隊は玉砕。圧倒的有利と言われた西軍は、これを境に大混乱に陥り、敗退した。
石田光成は「内府ちかひの条々」 を交付して諸国の大名に集結を呼びかけた。「内府ちかひの条々」 の 「内府」 とは 徳川家康 の事で、「ちかひ」 とは 「違い」、つまり間違っているという意味。その内容は、家康 が勝手に婚姻(結婚)や知行(領地)の斡旋を行ったり、無実の 前田家 や 上杉家 を攻撃しようとしたり、他にも勝手に手紙をやり取りしたとか、城の一部を無断で改修したとか、大なり小なり様々な 徳川家康 の罪状を並べたて、家康の討伐を訴えた文章(檄文)。そして、豊臣五大老の中国地方の大名 「毛利輝元(毛利元就の孫)」 を総大将として軍勢を整え、関所を封鎖して西側の大名家が 徳川軍 に参加できないようにし、さらに 大阪城 にいる東軍の武将の家族を人質に取って、必勝体制を整えて、挑んだ。しかし、石田三成 と他の 「武断派」 の武将の確執は、「朝鮮出兵」 の中で起きていたといわれる。石田光成はもともと 豊臣秀吉 の一番の側近で、秀吉に様々な報告を行ったり、秀吉の命令を各地に伝達する役目を持っていた。そのため彼によって、失敗や罪状を秀吉に報告され、処罰を受けた人が多くいたのである。それでいて自分は 豊臣家 のトップにいる彼は、とにかく多くの武将から陰口を叩かれまくる存在であった。そこで、小早川秀秋も大の 石田三成 嫌い!だった。と言うのも、朝鮮出兵の時の彼の失態を 石田三成 が 豊臣秀吉 に詳細に報告し、彼は 秀吉 におもいっきり怒られたあげく、領地も没収されていたのである。しかもそのあと、彼と 秀吉 の仲を取り持ってくれたのは他ならぬ 徳川家康 であった。
関ヶ原の戦いで一進一退の最中、徳川家康は痺れを切らし、小早川秀秋 の部隊に鉄砲隊を向け、一斉射撃した!東軍から鉄砲を撃たれたのだから 小早川秀秋 は怒って西軍に付きそうだが、秀秋 はこれにビビって 「家康が怒っている!」 と思い、あわてて寝返りの準備を始めた!徳川家康 が 小早川秀秋 が小心者であることを見越して行った催促だったとも言われている。関ヶ原が東軍の勝利に終わると、家康は寝返った小早川秀明らの軍勢に石田光成の佐和山城を攻め落とさせるとともに、大阪城を接収する必要があり、そこには豊臣秀頼親子がいて、さらには西軍の大将的な位置にいる毛利輝元がいて、黒田長政・福島正則を介して、輝元を大阪城から退去させ、開城を実現した。
この戦いで徳川についたものは、300年の栄華が待っていたし、刃向かった者に栄華が訪れるのは、明治維新まで待たないといけなかったといわれる。また、明治維新の主力になった、薩摩藩、長州藩、長宗我部系の坂本龍馬を代表とする土佐浪士たちは、すべて関ヶ原で敗者になった末裔で、その彼らが幕府を倒すパワーの源になったといわれるのも歴史は続いていたのかもしれない。











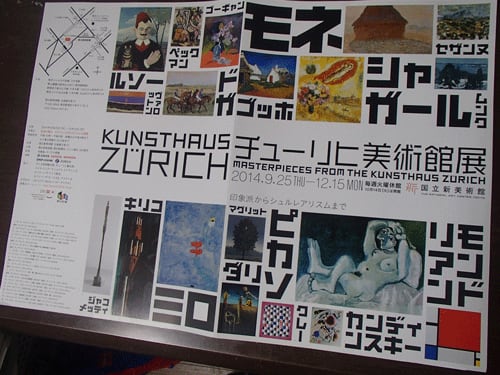






 タローは、キャパに勇気と熱意を与えたという。まさに「キャパのまなざしは、戦地にあっても、そうでない時も、状況ではなく、立ち会っている人間に迫っていきます。そこにある事実を、ただ情報として伝えているだけではない。いろいろな読み込みが可能で、美術館に展示される意義があると思っています」である。
タローは、キャパに勇気と熱意を与えたという。まさに「キャパのまなざしは、戦地にあっても、そうでない時も、状況ではなく、立ち会っている人間に迫っていきます。そこにある事実を、ただ情報として伝えているだけではない。いろいろな読み込みが可能で、美術館に展示される意義があると思っています」である。