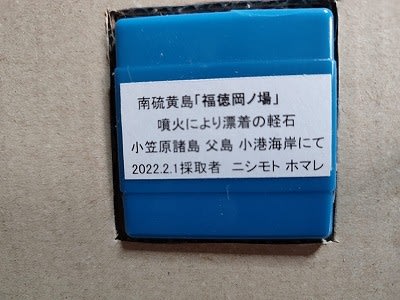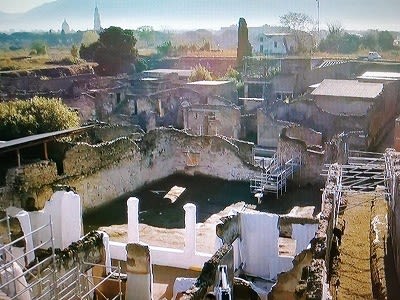『忠臣蔵』の大石邸跡@笠間市笠間

笠間の佐白山に登る山道の入り口、笠間日動美術館の手前に『忠臣蔵』で知られる大石内蔵助の祖父で、笠間藩家老だった大石良欽(よしたか)の邸宅跡が小公園となっている。
笠間日動美術館は年に数度は行くが、立ち寄ったことがなかった。

浅野家・大石家と笠間市の関係の説明板。
浅野家が笠間の地を去ってから57年後、元禄15年(1703)12月14日に赤穂浪士が吉良邸に討入って主君・浅野内匠頭の本懐を遂げた。

討ち入りに参加した四十七士のうちの3人が笠間藩出身者とか。

笠間義士会により建てられた大石内蔵助良雄像。


何やら、曰くありげな碑も立っている。
*「忠臣蔵って何?」
以前は芝居や映画、テレビドラマでよく目にしたが、最近は「忠臣蔵って何?」という人も少なくない。
かく言う私もその一人で、高輪・泉岳寺の赤穂浪士の墓に参り、本所の吉良邸趾を訪れた程度、芝居・映画・ドラマなど、その類の何一つ見ていない。
従って確固たるイメージが湧かない。
戻ってから幾らか調べてみたが、見方・考え方、登場人物も多様で、何だかよく分からない、が本音である。
“お話し”の方が面白いのかも知れない。

笠間の佐白山に登る山道の入り口、笠間日動美術館の手前に『忠臣蔵』で知られる大石内蔵助の祖父で、笠間藩家老だった大石良欽(よしたか)の邸宅跡が小公園となっている。
笠間日動美術館は年に数度は行くが、立ち寄ったことがなかった。

浅野家・大石家と笠間市の関係の説明板。
浅野家が笠間の地を去ってから57年後、元禄15年(1703)12月14日に赤穂浪士が吉良邸に討入って主君・浅野内匠頭の本懐を遂げた。

討ち入りに参加した四十七士のうちの3人が笠間藩出身者とか。

笠間義士会により建てられた大石内蔵助良雄像。


何やら、曰くありげな碑も立っている。
*「忠臣蔵って何?」
以前は芝居や映画、テレビドラマでよく目にしたが、最近は「忠臣蔵って何?」という人も少なくない。
かく言う私もその一人で、高輪・泉岳寺の赤穂浪士の墓に参り、本所の吉良邸趾を訪れた程度、芝居・映画・ドラマなど、その類の何一つ見ていない。
従って確固たるイメージが湧かない。
戻ってから幾らか調べてみたが、見方・考え方、登場人物も多様で、何だかよく分からない、が本音である。
“お話し”の方が面白いのかも知れない。