ヱビスビール記念館@ 恵比寿ガーデンプレイス内

2ヶ月ほど前に調べ事があって恵比寿に行き、面白い街と思って何度か訪ねた。
渋谷・代官山・白銀台・広尾などに隣接しながら、下町的な雰囲気を残した家や店が多い。
サッポロビール工場跡地の再開発事業として、1994年(平成6年)に開業した「恵比寿ガーデンプレイス」により大きく変貌したようだが、駅前には立ち飲み横町なども有って楽しい。
路地裏歩きをしていたら、ガーデンプレイスにたどり着いた。

開業して20周年を経過、混雑も無く建物や庭木も馴染んでいる。
奥まった場所に「ヱビスビール記念館」と云うのを発見。

入り口の“入場無料”の看板に引き寄せられて入ったが、地下2階、天井も高く豪華な雰囲気だ。
受付で「約40分間のガイドツアーが間もなく始まります、料金は500円ですが、2種類のビールの試飲が出来ます」とのことで、どの様なものか申し込んでみた。
待つほど5分、「ブランドコミュニケーター」と呼ばれるお嬢さんの案内で、ツアー開始された。
このミュージアムはヱビスビール生誕120年の記念日に当たる2010年2月25日に、「ヱビスビール記念館」として誕生したこと。
1889年(明治22年)に畑や山林が広がっていたこの地に醸造場が完成し、1890年に「恵比寿ビール」が発売されたこと。

当時のビールは今よりとてつもなく高価だったこと、瓶も現在の倍以上大きく、口金はワイの様なコルクであったこと。

普及の為に銀座にビヤホールを開業し、つまみがスライスした大根だったこと。

「恵比寿」という地名も、駅の名前も、実は、ヱビスビールからきていること。

などなど、ヱビスの歴史や秘話を目と耳から体験出来た。
博物館ほどではないが、多くの資料が展示されていた。

ツアーの締めは、中央のホールで2種類のビールの試飲。

テーブル中央に、小麦とホップが入った小さなケース。
小麦の焙煎の程度によって味や香り色などが異なったビールが出来るとのこと。


高度な技術を会得したバーパーソンがタップから注ぐビールはきめ細かな、クリーミーな泡。
最後の一滴までしっかりと味わうことが出来る。
缶ビールを美味しく飲む注ぎ方も披露してくれた。
三段階に分けて注ぐ方法で、これを知ればれば、缶ビールもかなり美味しく飲める。
単純ですが、一気に「エビス」のファンになりました。












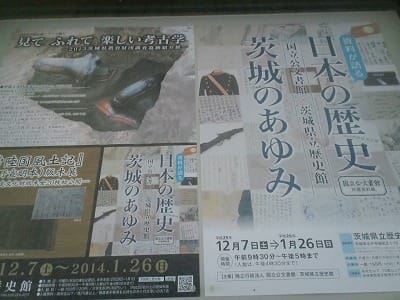
![74af978c4a46abe42c0b68d1d142af7d1[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2b/0c/4dc9dcb5728501479b2834622120f604.jpg)















































 、
、

